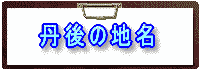
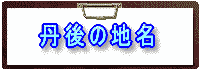
���ɐ�
���ɐ��i�����S���̂݁j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
�����҂̍���
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ƃ��邻���ł���B �@�q �L���_�_�K�V�ÐՎ�����������䌴�o���{�O�|�V�ꎧ����ʗL�V���������V�����A ���_�V�c���ʐ���p��Ύg�L�����P���J�V�Ƒ��_���㙙���錩�_�����n�ȕ��V��N�O����R���N���A ��쉻���J�o�Ӌ�u�n���ȕ��V�����n�L�o���S�����v�c�{�V�L�쌱�Ғ���������L���Ȏ����㐢�ЋL�H�A�c�@
�@�q �y�l暁z�ݖ쌴�� �y�I�z����j�}�X �y���ׁz�� �y�L�z���ߒ����_���R�Z�������� �y���z�쌴�� �y���l�z���߃m�������_���Ѓ�❌��_�Ѓg�p�_�E�����]�o�^���j���l�V�����^�t�B�l�V���T�l�X���j�ʃV�e�ϐ��i���z�N�V�e❌��_�Ѓn�쌴���j�A���x�N�o�G���쎮�l�كj��❃m�����琳���L�Pਕ�(�|���ɘH)�V�́A�a�����]����S❌��T�g�ǑH�N�另���D�_�����͋V������ݗt�W������ਃg�~�G�^���T���o❌����`�쌴�j�V�e�쌴���n❌����i���x�V�T�e�����j�ЎO�P���A�������V�_�Ѓn�i�������ÃN�V�����j�X�X�^���Ѓm�_铌ܒ��}�V�������ÃN��N�ȏ�m铃g�~�����Ѓj�ꌎ����i���������U��j�h��(�T�J�V�o)�g�]�t�_���A���僒�m�j�e�^�o�l��m�@�N�j�V�Q�Ɗe�R�������`�P���j�Q���V�ăm�������g�ٌ������j���t�a���j�j��l�畞�����V�e��̃X������e�n�уm�R������e�n���m�R�O�����e�n�����ۃe���e�����e���c�L�X�����ݑ��x��(�����j��)�G�C���A�G�[���[�G�[���[�A���V�e�e�ރm�h�ă��[������e���Q�g�A�� (�y�L�z�͖L���������_�Ў撲���E�y���z�͒O��A�n�_�Г��u���{�E�y���l�z�͒O�㍑�����_�Ѝl�E�c�u�͒O��c�ӎu�������ł���B)�@
�@�q
�@�q �@�]���āA�����ЁE❌��_�Ђ͉����S�̒��S�n�ŁA�S�ɂɋ߂��A���⍪�E���㍪�T���̕��z����n�ł��낤�B ���ׂĂ̎����͂���❌��_�Ђ��w���B�⍪���͌��݂͔����l�_�Ёi���ߎs�l�j�̋{�i�ł��邪�A���͂���❌��_�Ђ̂��_�E�������ŁA�C�����Ƃ�������Ă����悤�ł���B�ׂ̌j�ю��̎��̂���i�����Ɠ`��鍲���P�x��̍⍪�C�����A�⍪���͂�͂茳�X���̂�����̗̎�ł������Ǝv����B �@���̎��ɍĐ�����❌��_�Ђ͕��ʂ̑��X�̐_�Ђł͂Ȃ��B�l���̃C�f�I���M�[�ʂł̎x�z�ƍ��Ƃ̈��ׂ��F�肷�邽�߂́A�V�����������W�����Ƃ̂��߂̌S�Ƃƕ��ԁA���邢�͂���ȏ�̂悤�₭���f��������̂��̒n�̎x�z�̋��_�Ƃ��ẮA���Ƃɂ�鍑�Ƃ̍��Ƃ̂��߂�❌��_�Ђł���B�����������Ǝg�������헪�I�����I�_�Ђł���B�����Ђ�❌��_�Ђ͉����S�̐S���ł��������n�������Ă͂Ȃ��B�l���߂����ɂ͍s���Ȃ��悤�ȏ��ɁA�厖�Ȏx�z�̂����т��Ȃ��������肷�邾�낤�B���͐����͌��������A���������̐����ƂȂ瓖�R�����ɒu�����낤�B �@��N�i701�N�j�̒O�g�ɎO����������n�k���������B�c���ɖ}�C�������Ƃ����L��������B���N�ɓ��{�Ƃ������������߂Ďg���Ă���B���̂P�Q�N��ɒO�㍑�����܂ꂽ�B�܂����N�ɂ͕��y�L����̒����o�Ă���B❌��_�Ђ͂��̂Q�P�N��ɍďo�����Ă���B�c���������������̎����̍쐬���Ǝv����B���݂̓��{���ɂȂ���悤�ȍ��̔w��������Ă���������ł������B
�@�q �����ɂ͒|��S�������Ă���B�����������̌S���ɉ����Ă��܂����P�����̌̒n�Ƃ���_�Ђ�����B �@�ł͂ǂ����{���̌��ɐ����A�ƒT���̂͂��Ԃv�ł��낤�B���ۂ̘b�͂ǂ������킩��Ȃ��̂ł���B�킩����̂Ȃ�A�����Ƃ����̐̂ɂ킩���Ă������낤�B �����Ƒ�������Ă݂�ƁA�O�g�S���{���̖L���_�̌̒n�ł��낤�B������������S��❌��R�Ɉڂ�A���̌�^�ӌS�Ɉړ����āA�^�ӌS����ɐ��֑J�������̂��낤���ƁA���݂Ɏc�镶�����猩�����͍l������Ǝ��͍l���Ă���B�܂����������������l����Ƃ������Ƃł��邵�A���͕����ʂ�Ƃ͉�������Ȃ��B �����炠�邢�͌��ɐ��͗^�ӌS�ł���A�����ɐ��͉����S�ł���A�������ɐ����O�g�S�ł��邩���m��Ȃ��B�������ɐ��͈�ЂƂ�����Ȃ��B�܂��v����ɑS�����ɐ��ł���B�ł͂���Ɍ��������ɐ��͂ǂ����낤���B����Ȏ����l���Ȃ���A�i�߂Ă������B
�@�q (�O��̍��̕��y�L�ɞH��) �O��̍��B �O�g�̌S�B �S�Ƃ̐��k�̋��̕��ɔ䎡�̗�����B ���̗��̔䎡�̎R�̒��Ɉ䂠��B���̖��ވ�Ɖ]�ӁB���͊��ɏ��Ɛ����B �@���̈�ɓV�����l�~�藈�ė����ށB���ɘV�v�w����B���̖���a�ލ��V�v�E�a�ލ��V�w�ƞH�ӁB���̘V�炱�̈�Ɏ���A�ނ��ɓV����l�̈߂Əւ��摠���B�����߂Əւ���͊F�V�ɔ�яオ��A�����߂��ւ��Ȃ�������l���܂�ʁB�g�𐅂ɉB���ēƉ���������B �@�����ɘV�v�A�V���Ɉ���ĞH�͂��u��Ɏ��Ȃ��A���͂��͓V�����A���A���ƂȂ�ނ�v�Ƃ��ӁB�V���A���ւĞH�͂��u���Ɛl�Ԃɗ��܂�ʁB�����]�͂�����ށB���͂��͈߂Əւ��������܂ցv�Ƃ��ӁB�V�v�A�H�͂��u�V�����A���ɂ��\���S�𑶂Ă�v�Ƃ��ӁB�V���A�]�͂��u����A�V�l�̎u�͐M���Ȃ��Ă��ƂƂ���B�����^�Ђ̐S�������Ĉ߂Əւ���������v�Ƃ��ӁB�V�v�A���ւĞH�͂��u�^�����M�Ȃ��͗��y�̏�Ȃ�B�́A���̐S���Ȃ��ċ���������v�Ƃ��А��ɋ�����B���������Ђđ�ɉ����A�������Z�ނ��Ə\�]�ɂȂ肫�B �@�����ɓV���A�P������������B�ꚭ���߂g�����̕a������B���̈ꚭ�̒��̍��A�Ԃɐς݂đ����B���ɂ��̉ƖL���ɂ��ēy�`���x�݂��B�́A�y�`�̗��Ɖ]�ӁB���ꒆ�Ԃ�荡���Ɏ���܂ŕւ��䎡�̗��Ɖ]�ւ�B �@��ɘV�v�w��A�V���Ɉ���ĞH�͂��u���͌Ⴊ���ɔA�b����ďZ�߂�B�X�����o�ŋ����ˁv�Ƃ��ӁB�����ɓV���A�V�����ĚL�Ԃ��A�n�ɘ낵�Ĉ��Ⴋ�A�����V�v��Ɉ���ĞH�͂��u���͎��ӂ��Ȃ��ė����ɂ͔�炶�B���͘V�v�炪��ւ�Ȃ�B���ɂ��}���̐S�����ɏo���V�ɂ���ށv�Ƃ��ӁB�V�v�A�����т�ċ������Ƃ���ӁB �@�V���܂𗬂�����̊O�ɑނ��ʁB���l�Ɉ���ĞH�͂��u�v�����l�Ԃɒ��݂��ɓV�ɂ��҂炸�B�܂��e���Ȃ��́A�R�鏊�m�炸�B��≽�ƁA���Ɓv�Ƃ��ӁB�܂�@�ЂĚl�V���A�V�����ĉ̂ЂĞH�ӁA �@�@�V�̌��@�U���������@�������@�ƘH�f�Ђā@�s���m�炸�� �@���ɑނ苎���čr���̑��Ɏ���ʁB�������l��Ɉ���ĉ]�͂��u�V�v�V�w�̈ӂ��v�ӂɁA�䂪�S�͍r���ɈقȂ邱�ƂȂ��v�Ƃ��ӁB�����䎡�̗��Ȃ�r���̑��Ɖ]�ӁB�܂��O�g�̗��Ȃ�L�̑��Ɏ���A�̖ɋ���ĚL�����B�́A�L�̑��Ɖ]�ӁB �@�܂��|��̌S�D�̗��Ȃ�ދ�̑��Ɏ���ʁB�������l��Ɉ���ĉ]�͂��u�����ɉ䂪�S�Ȃ���������ʁB�Î��ɕ������P�����Ƃ�ދ�u�ƞH�Ӂv�Ƃ��ӁB�T�����̑��ɗ��܂�B���͈����|��̌S�̓ދ�̎Ђɍ����L�F���\���̖����B�i�������j�i��݂͏��w�ٔł́w���y�L�x�ɂ����́j �@
�@�q �ØV�`�H�B�ߍ]���ɍ��S�^�Ӌ��ɍ����]�A�����B�V�V�����A��ה������V���~�B�����]�V��ÁB�����A�ɍ������A�݉����R�B�y�������A���`��فB���^�ᐥ�_�l���B�����V�A�����_�l��B�����ɍ������A���������A�s���ҋ��B�ތ�����������V�߁B���B��߁B�V���T�m�A���Z���l�A�V��B�����l�A�s���A�V�H�i�ǁB���גn���B�V�����Y�A�����_�Y����B�ɍ������A�^�V���폗�����ƁA���������A�����j���B�j��B�Z���Ӕ��u���A�햼�ߎu�����B�����ɐ������@�A�����ސ����䔄�B���ɍ��A���V��c����B�ꑦ�{��V�H�߁A�������V�B�ɍ������A�Ǝ�A�H�r�s�f�B�@ ��̂��w�^�Ȃ̂ŁA�u�]���ɓ`���H�ߓ`���v�����ĉ������B �@�@�@�@�@�u�]���̓V���v�i�ΔȂ̔��̐X�ƐV����_�Ёj �@�@�@�@�@�u�V���`���̓�v�i�V����_�АՂ� �@�@�@�@�@�u������Ð_�Ёv�i�]���̂����k�̒��V���ɂ͎����ЁE������Ð_�Ђ�����A�V�������J��j�B �@��L���ꂼ���HP���`����悤�ɁA�]���̉H�ߓ`���͐V���̉��q�E�V�����������炵�����̂Ƃ�����B �w�O��H�̎j�Ղ߂���x�i�~�{���K�E��47�j�́A �@�q �ƁA���a47�N�Ƃ������炩�Ȃ葁������w�E����l���������B �q�W��A�V�E���̓N�V�t���n�̒n���ł���B�鍻�͍��S�̎��ł��낤���A����������ȌĂі��͕��������Ƃ��Ȃ��B���Ԃ�͎��̂悤�Ȃ��Ƃƍl����B���߂́u❌��������{�v�̋����̓}�i�C�Ɠǂނ��A�C�T�i�R�Ƃ��ǂ߂�A�ǂ߂Ȃ����Ƃ��Ȃ��B�}�i�䁨 �鍻�R�͕�R���܉ӂ̐^���@�̌Ù��E�J�����̎R���ł��邪�A���̎��͌Â��A�����Ԃ�ƌÂ����炱�̂悤�ɌĂ�Ă����Ǝv����B�J���̒n�͒O�g�^�ӌS�ƂȂ��Ă���B�܂��S�͂Ȃ������Ǝv���邪�A�O�g�S�ł͂Ȃ��A�^�ӌS�ƂȂ��Ă���B �c���Ɉɋ��ގq�ԂƂ���A���łɕ��y�L�ȑO����̎R���ł���A����Ȏ��ォ��ǂݑւ����s���Ă����ƍl������B �@�w�����̍ō��_�Ƒ�a����̌��n�x�i�C�����蒘�j�́A �ɋ��ގq�̖��̂̋N���ɏA���ẮA�������������Ƃ��Ă͌��݈⑶���Ă͂��Ȃ��̂ł���B �Ƃ��āA  �@�����̓i�R�Ƃ��ǂ߂�B�Ƃ��������̕����������ǂݕ��ł��邪�A�|��S�ދ�Ёi��h���D�̎����Гދ�_�Ёj�̃i�O�ƚL�ؑ��i��R�����L�A���B�����Ж��ؐ_�Ђ��������邩��A�i�L�M�ł͂Ȃ��i�L���{���̌Ăі��ł��낤���j���ĊO�ɂ���Ȃ��Ƃ����m��Ȃ��B�������i�R�Ɠǂ݁A���ꂪ�]�a���Ă��̂ƍl������B�ǂ�����}�i��̂��Ƃł��낤�B �@�L�ؗ��E�ދ�Ёi�핶���y�L�j�A�ɋ��ގq�ԁi�c���j�Ƃ���������y�L�̎���̌Ăі��ł���B�ޗǎ���ɂ́A���̂悤�Ƀ}�i��͌Ăёւ����ċv�����A���łɂ��̂��Ƃ͖Y����Ă����̂��낤���B�����o�������l�ɂ��M�����Ȃ��悤�Șb�ł���B  �@�q ��ʂɂ̓t�i�L�Ƃ͑D�������낤�ƌ����Ă��邪�A�������̉\��������B�H�ߓ`���͑D�؎��̓`�������m��Ȃ��Ȃ�B�t�i�L�̒n���͑S���ɂ��Ȃ葽���B�ɐ��̑D�ؒ��͑����Ȃǂ̓����ł���B�O�o�́w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�́A  �@�q �Ƃ��Ă���B�w�Î��L�x�������Ă����B �@�q ���ɖʔ������������Ă��āA�ȒP�ɂ͘b���i�܂Ȃ��B�ǂ����ōēx�Ƃ�グ�Ă݂����Ǝv���B
�@�@�c���ܔN�M�q�~�\�ꌎ�\�l�� �@�@�Č�����c����� �@�@�א�z���璉���ގ�
�@�q ![��]���E�c��_��](motoiseko21.jpg) �@�c��_���́A���{�̋{�R�ɒ����A���ʂɖ{�a�A�����ɘe�{��Ђ��J����B�{�a�̍Ր_�͓V�Ƒ�_�A�e�{�̍Ր_�́A���a���V��͗Y���A�E�a���}�@��X�P���ł���B�����ċ����̎��͂ɖ��Д��l�Ђ̏��K�����ԁB�{�a�Ƙe�{�̊Ԃɗ����̐��ƌĂԌÖ�����B�{�a�����i�������Ƃ���ɒ���������B���̒����͍��̒����ł���B���̒����͋��s�����̖�X�{�_�ЂɌ��Ă��Ă��邪�A���ɂ͗Ⴊ�Ȃ����̂ł���B�_�y�a�̑O����A�����̐����͂��߂Ƃ����Ɣw��̎��R�тɕ���ꂽ�Ј�́A�_���тČ×������Ђł��������Ƃ���Ă���B �@�c��_���́A���{�̋{�R�ɒ����A���ʂɖ{�a�A�����ɘe�{��Ђ��J����B�{�a�̍Ր_�͓V�Ƒ�_�A�e�{�̍Ր_�́A���a���V��͗Y���A�E�a���}�@��X�P���ł���B�����ċ����̎��͂ɖ��Д��l�Ђ̏��K�����ԁB�{�a�Ƙe�{�̊Ԃɗ����̐��ƌĂԌÖ�����B�{�a�����i�������Ƃ���ɒ���������B���̒����͍��̒����ł���B���̒����͋��s�����̖�X�{�_�ЂɌ��Ă��Ă��邪�A���ɂ͗Ⴊ�Ȃ����̂ł���B�_�y�a�̑O����A�����̐����͂��߂Ƃ����Ɣw��̎��R�тɕ���ꂽ�Ј�́A�_���тČ×������Ђł��������Ƃ���Ă���B�@�R���ɂ��ẮA���_�V�c�̂Ƃ��A�V�Ƒ�_�̌�_�̂ł���_�����A��a���}�D�W��肱���֑J���A�l�N�ԕ�ւ����A�n�T�g���{�̋��Ղł���Ƃ����A�u�O�㋌��W�v�ɂ��A�u�V�Ƒ�_���������_�V�c��F�J��a���A���v���m�ɐ������Ԍ��J�{�v�Ƃ���B���Ђ̐_�Ж��ג��ɂ́A���_�V�c�̌��V�Ƒ�_����a���}�D�̗����瓖���g���{�֑J�K�̓r���A���̒n�ɂ��炭���������B�̂��ɐ��ɒ����������߁A����������_�{�Ə̂���悤�ɂȂ����Ƃ���B����A�u�{�Õ{�u�v�ɂ́A�u�����N��ڈ���]�p���鎞���C�q�e���V������������@�_�Ќ[�֓����O�͐X�O�{������g���{�����������K�����{���ҋߑ�V�����ҋp���@���v�Ɩ��C�q�e�����S�ގ��̋F��̂��ߌ��������ƋL���A�ߑ�̒n�����u�O�㕗�y�L�v������|�̉��N���̂���B�Гa�̑��c�́A���N�Z�\��N�ڍb�q�̔N�ɂ���Ă����������N(��Z�ܘZ)�l���̔N�I�������D���c��A�{�Ôˎ勞�ɍ����ɂ��_�y�ЁA�䋟���A�֑��Ȃǂ̏C�����m����B�@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@�q �@�ނ��G�̂ƌ��߂���B�������Õ����ɋL�ڂ��Ȃ�����Ƃ����Ă��A���ɐ��ł͂Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A���ɋL�ڂ��������Ƃ��Ă����̂܂ܐM������Ƃ������̂ł��Ȃ��A���͑�������ɋL�^�������̂ł���A�����Ƃ��Ƃ������Ƃ��悭����B�S�ǂ��̎ЂȂNjL�^�ł��邩�ƈӐ}���ď����Ȃ����������m��Ȃ��B�����������ʊϔO���Ȃ������Ƃ������Ȃ��A���������Â��傫�ȎЎ��ɂ͂����Ă����������퍷�ʏW�c��������̂ł͂���Ƃ����A�{���̐M�Ƃ������̂͂�������������u���ЂƂ��āv�Y�܂ꔭ�W���Ă���̂����m��Ȃ��B �@�q �@ �i�O�d���j���C�S���C���m�c�ɂ���_�ЁB�Ր_�͓V��͗Y���ق��Q�U���B�u�Î��L_��Ɂu���ߌ���A�u���_�{�{�L�v�Ɂu��͒j�_���ߌ��ɍ����v�Ƃ���A�n���ƊW�Â��l�����Ă��邪�ڍׂ͕s���B���쎮���Ђɔ�肳��A���ۂX�N�̎�ɂ�荲�ߐ_�Ђ̐ΕW�����Ă�ꂽ�B��X�ЂƂ��̂��i�x��o�F�_�����l��)�A�m�c�E�܌j�����̎Y�y�_�Œ��m�{�Ƃ��̂����i�ɐ������_�Ќ��^)�B �����S�N���Ђɗ�i�A��39�N�_�a���嗿���i�ЂɎw��A��41�N���R�E�܍��ށE�l�_�c�E���v�E�m�c�E�܌j�E�O���E�_��E���J�E���J�̏��Ђ������B���a18�N���Ђɏ��i�B��Ղ�10���W���B���Ă̓����̍L��ŁA�V�폗�x��Ə̂����x�肪�s���Ă����B�@ ���̒n������̎Y�n�ł��邱�Ƃ́A��́u�K�J�_�Ёv�̏��Ō����Ƃ���ł��邪�A�܂��T�i�͂��߃T�k�E�T�j�E�V�m�E�V�i�Ȃǂ͓S�̌Ö��ł�����Ƃ����i�u�Ñ�̓S�Ɛ_�X�v�j�B �@�q �@�R���ɂ͑傫�Ȕ֍��i���킭�灁�Ђ̂Ȃ��������̐_�̂�肵��j�ƁA���K���I�ɕ��ׂ���̑��^��������܂��B�Ď��̓��A���̗y�q�����璭�߂�ƁA�[�z���Ƃ������R���ɒ��݂܂��B�_��̌��i�ł��B�݂Ȃ��������A�~���炸�Ɂu���v���F���ĉ������B�K�����A���邱�Ƃł��傤�B�@
�@�q
�@ ![�^�����̔�i��]���ցj](hisenhi4.jpg) �^�����́u�����͂��������S���c�v�́u��F�v�̉̔�̂Ƃ���ŁA���͔��Ȃ̂��Ȕې�Ȃ̂���킩�ȁA���A���A�ߐ�c�B�N������Ȏ����������҂͂Ȃ������ȁA�Ȃǂƍl���A���͂��̐_�Ђ���D���Ȃ̂����A����Ȃɑ����̂Ȃ�A���Ă����A�낤���ȂǂƖ��N�v���B �^�����́u�����͂��������S���c�v�́u��F�v�̉̔�̂Ƃ���ŁA���͔��Ȃ̂��Ȕې�Ȃ̂���킩�ȁA���A���A�ߐ�c�B�N������Ȏ����������҂͂Ȃ������ȁA�Ȃǂƍl���A���͂��̐_�Ђ���D���Ȃ̂����A����Ȃɑ����̂Ȃ�A���Ă����A�낤���ȂǂƖ��N�v���B�@�S�`�����������A������������p���ł��炢�����Ɗ肤�B���Ȃ炸�Ƃ��A���n�̂Ԃ�ǂ荇���̒鍑��`�푈�ɂ���o�����̂́A�܂��҂炲�߂�A�����Ȃ鋦�͂����߂�ł���B �@��̂Q�R���䕗�̃w�h���ł��̔�̕ӂ�����܂����܂܂ł���B�����������{��i�\���j������Ă��邪�A���ꂪ��ꂽ�B �������N���߂��邪�P�O�Z���`�ȏ�͐ς����Ă���B�V�C�̂������Ȃ�܂��������A�J�̓��Ȃ��ςȂ��ƂɂȂ邾�낤�B �@���͑�]���͎�̏o�g�A�ނ̒킳��͕��߂ɂ����ċ��y�j�����Ȃǂɍv�����ꂽ�B
�@�ʐ^�͖k���������Ă���B�˂������肪�����P�V�T�����ŁA�E�֍s���Ε��m�R�A���֍s���Ε��߂ɂȂ�B��炸�ɂ܂������ɍs���i�Ԃł͍s���Ȃ������m��Ȃ����j��Ղ�����B����������悭������B�͎�k��ՂƂ����A�Õ����̏Z���Ղƕz�ڊ����o�y�����B���́w���O�����V���x�̂O�S�D�P�O�D�V�̋L���i���݂�web��ɂ��邪�A�Ȃ��Ȃ邩���m��Ȃ��̂ŃR�s�[�����Ă�������i�ʐ^���j�B�u���O�����V���v�P�O���V���̃j���[�X�j�A �G�����Z���ՂQ���m�F�@��]�����ς��͎�k����̒����� �@�q  �@�͎�y�n��搮�����Ƃɔ����A�V�����玖�O���������Ă����B�����Ώۂ́A���̒��S�n�𑖂鍑���P�V�T�������̖�T�O�O�������B �@�͎�y�n��搮�����Ƃɔ����A�V�����玖�O���������Ă����B�����Ώۂ́A���̒��S�n�𑖂鍑���P�V�T�������̖�T�O�O�������B�@�����̌��ʁA�P�ӂ���T���l���ƂU�E�T���l���̒G�����Z���Ղ��m�F���ꂽ�B�ߋ��Q��̎��@�ŌÕ����������畽�����㏉���ɂ������y�킪�o�y���A������Ղ����邱�Ƃ͕������Ă������A�Ñ�Z���Ղ����������͓̂��n��ł͏��߂āB �@���̂ق��A���܂ǐՂƌ�����ēy��⏰�ꂩ���P�i���߁j�A�Z���̎��͂ɂ߂��炷�a�A�{�b���y�t��̔j�Ђ��������������B����ɂV���I�㔼����W���I�̂��̂ƌ�����z�ڊ��̔j�Ђ��o�y�����B �@�����ɓ������������ς̏��{�w������́u�͎�n��ŏZ���Ղ����߂Ċm�F�ł��A���ӂɏW�����L�����Ă����\�����l������B�z�ڊ��͌�Ɋ����g�p�����������������{�݂����ӂɑ��݂������Ƃ��������̂ŁA����̒����ł��̎��̂ɔ��邱�Ƃ��o����̂ł́v�Ɗ��҂��Ă����B�@ �@�z�ڊ����o�y�����Ղ͉����S�ł͂��������Ȃ��i�a�]�ł��o�Ă���悤�ł��邪�j�B�O��ł��O�㍑�������Â��Ƃ�����ޗNJ��̕U��p���i�Ԗ쒬�j�A�O�㍑�{�̒n�Ƃ������꒬�j�R������ł����o�y���Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B�㗬�̕��m�R�ł͘a�v���p���⑽�ێs�p�����A�����Ȃ爻���p���A�X��S�s������c�̎O�c�˔p���A�����꒼���ɓ����E�����E���������ԂƂ������A����炭�炢�����Ȃ��B�z�ڊ��Ƃ����̂́A�w���̎��T�x�iweb��j�ɁA �@�q ��������܂ł̊��ɂ́A�����ɕz�̖ڂ����Ă���B����͖،^����S�y���Ղ����邽�߂ɁA�،^�Ƃ̊Ԃɕz��������ł���B�����������͕z�ڊ��ƌĂ�Ă���B��������ɓ���ƕz�ڊ��͂������ɂȂ��Ȃ��Ă������B���l�̈�ς��z�̑���ɉ_�ꕲ�i���炱�j���g�����@�������炵������ł���@ �@�V���I�㔼����W���I�͔`�ޗǎ���ł���B�͎�Ɂi���̖����������p����������������ł���j����ȓr�����Ȃ�����Ɋ����悹�����@�����ɂ����������������L�^��`���͉����Ȃ��B�O��w�܂�̒���i�n�悾�����悤�ł���A�L���Ȍo�ς̊�Ղ͋������Y�ł��낤���A�����������Ȓn���̏ꏊ�ł���B���̊��͎��@���낤�ƍl�����Ă���悤�ŁA�u�͎�p���v�ƌĂ�邻���ł���B�͎�p���̂����߂��ɂ͒O�㍑�{�������S�Ƃ������������m��Ȃ��B�Ί݂�����}���o�y���Ă���A���オ�����قȂ邪�A���邢�͍����������������������͐�Ǘ��̓n���l�̏W�����������̂����m��Ȃ��B �@���ꂾ����Ñ�j�Ƃ����̂͐l�C������̂��낤�B�ꖇ�̊��̔j�Ђ̏o�y�ł���܂ł̒ʐ����Ђ����肩����B ����ő�]���̓��{���O�{������傫�Ȋ�ő傫�Ȑ��ŁA�u���������ɐ����I�v�Ƃ����悤�B���ɊO�{�͑傫�ȑ傫�Ȋ�����Ă悢���낤�B�g�c���ނ��͎瑾�_�{(�L���_�Ё��V�c���̊O�{)���u�Â̊O�{��(���Ɏ�)�����z���v�Ƃ��Ă���B�������ɐ��O�{�̐Ւn�Ȃ̂ł͂Ƒz�����Ă���A��͂肷�����l���A���݂����̏��̉��l�͎����Ȃ��B�M���R�Ƃ����Ⴂ�u�˂̒���ɒ������邪�A�����͓����Ƃ������ł���A�M�͒O�ɒʂ��邵�^�C���͉����^�^����z�킹��A�����Ă����ɂ͑�����̈�ڏ��m�������Ɠ`���͂����B�O�ƓS���W����n�����m��Ȃ��B�͎�ƒn�������Ԃ̎Ђ���o�����̂Ǝv����A���Ԃ�{�����Ď瑾�_�{�Ə����Ǝ��͍l���Ă���B�J�O���Ȃ킿���R����삷��_�Ђł������B�Ă��Ȃ��R�Ɠǂނ��A����͒m��Ȃ����A�O���{�����ăJ�S(��)�_�ЂƏ����ăR�̐_�ЂƓǂ�ł��邩��A�����Ƃ��ǂ̂��낤�Ƃ��������Ȃ��B���邢�͖{���͍���A���邢�͍��X�_�ЂƏ����ăJ�O�����Ɠǂ�ł��������m��Ȃ��A���ꂪ�R�[�����ƂȂ����B������͑�{���\�͂̂�����ɂ���̂ŁA�����炪���������m��Ȃ��B ����̃}�l����̂ł͂Ȃ����A�����炪�����C�ɂȂ�B�{���ő�̍z�R�Ől���P�O�O�O���𐔂����͎�z�R�̎�ȎY�o�z�͉����z�ł����������ł���B�܂����Ď瑾�_�{���s�b�^���ł���B �Ȃ��Ȃ������܂ŏ������Ԃ�����܂���̂ŁA�Ƃ肠���������ǂ�ʼn������B �@���̂�������O��ł͂��邪�A�O��Ƃ��������ǂ��炩�ƌ����ΒO�g�ɋ߂����ł���B�O�g�ׂ̗̕��m�R�s�ƍ����Ƃ��܂������������A���݂͂����ł��邵�A�ߋ��ɉ����Ă������ł����������m��Ȃ��A�����S�S�̂��ǂ��ƂȂ�����Ȋ����̂���A�O��Ƃ����Ă����Ƃ͂Ȃ����[�ȏ��ł���B �@���s�{�����S��]���͕���18�N1��1���ɕ��m�R�s�ƍ��������B���s�{�V�c�S�O�a���E���s�{�V�c�S��v�쒬�������ɕ��m�R�s�ɍ��������B
�@�q �@ ����͂��̎Ђ̎��q�͋S�̎q���ł���Ɖ]���Ă���悤�Ȃ��̂ł���B����Ȃ��Ƃ͊W�̏��Ђɂ͏�����Ă��Ȃ��̂ŕs���ɂ����܂Œm��Ȃ������̂ł��邪�A�V����ǂ�ł��Č������B�w���s�V���x�i2006.1.29�j�ɁA�i�ʐ^���j �@�q  �@�ߕ��̓��܂��Łu�S�͓��A���͊O�v�ƈꕗ�ς�����|���������镟�m�R�s�O�a���̑匴�_�Ёi�яG�r�{�i�j�œ�\�����A�ߕ��̓��ɋS�ɕ����鎁�q���ߑ����킹�����āA�{�Ԃɔ������B �@�_�Ђł͐ߕ��̓��̓O����A�ы{�i��Q�q�q���_�Ћ����ɏW�܂�A�O��ɖ\���т�����Ė��������S���A�u�S�͓��A���͊O�v�Ɠ����Ԃ��Ȃ���{�a�ɏ�������A��N�̌��N���F��B���̓��́A�S���߂��ΌZ�s����i�Z�Z�j�玁�q�̒j���l�l���ԂƐɐ��߂������A���Y�{���A�Օ��̃p���c�𒅂��āA�T�C�Y���m�F�B�p�[�}�����Ă����㕗�̂���ł������Ɍ��߂�S�������B�S�����͖{�a�O�ŁA�|�_��n�ʂɂ��������āu�S���������I�v�Ƌ��сA�{�ԂɌ����đ����A�C�������Ă����B�@ �匴�_�Ђɂ��͏ڂ����́u�O��̓`���v�Ɉ����Ă����̂ŁA����������ĉ������B �@�q �n���̏Z�����ӂ��ԋS�ƐS�����Ƃ�K��A�ƒ�̖���u�S�}���v�������A���m�R�s�O�a���匴�̑匴�_�Ј�тōs��ꂽ�B�q�ǂ������͋S�̖K��ɂт�����B��l�͉ƒ���̋S����������Ă��炦��Ƃ����āA����U�镑���Ċ��}�����B �匴�_�Ђ̒ǙT���́u�S�͓��A���͊O�v�Ƌt���ɂ�����������B���Ă��̒n�悪������S�˂̗̒n�������z���Ƃ���A�{�a�֒ǂ����ꂽ�S�͐_�l�ɂ����S����B�\�N�O�ɁA�n���́u�匴�b�������̉�v���e�Ƃ̋S���}����s�����n�߂��B �S�g��ԋS�ƐS�̈ߑ��ɂ܂Ƃ����j�����Z�l�͊e�˂�K��B�u�����S�͂���v�ƌĂт����A�������Â��q�ǂ��̓����Ȃł��B�ʊ��ɓ����Ԃ���q�ǂ��������B�S�͂ɂ��₩�Ɍv���\�˂�����A�ܐF����n���ĉ�����B�@ ��S���ɉ��������Ƃ����̂́A�ߐ��I�Ȕ˂������̔ˊw�Ґ搶�̏鉺���j�ςł͂Ȃ��낤���B��S�̂ɂ͂������_�Ђ�����A�����̗̖����������Ă���B�����Ƃق��ɂ��u�S�͓��v�������Ă������Ǝv���邪�A�������������Ȃ��B�u���̎Ђ̋S�͓��v�͋�S���Ƃ͊W���Ȃ��Ǝv����B�S�̎q�����낤�ȂǂƂ������邢�͓{�肾���l�����邩���m��Ȃ��B���V�͋S�ł͂Ȃ��ƁB���������z�������m��Ȃ����A�������N�V�t���n���⌳�ɐ��������������Ȃ�A�V�c������C��������S(�G�艤)�̎q���ł͂Ȃ��̂��Ƃ����^��͏o�Ă���B�����g�̋S�Ȃ̂łȂ��낤���B���邢�͕����g���S�ƌĂсA�����g�͐_�l�ƌĂ�ł���̂ł͂Ȃ��낤���B���Ƃ��Ƃ͓���������ɕ����B�_�ƈ����ɁB�������Ȃ���ΐ_���Ȃ��B����ł����A�����J�ƃe���̊W�̂悤�Ȃ��̂����m��Ȃ��B�e���ƃe����̊W�����m��Ȃ��B�݂��Ɉˑ��������A�����ꍇ���Ă���B�����ǂ��炪�ǂ��Ȃ̂����̋�ʂ����Ȃ��قǗ��҂͂悭���Ă���B �@�q �����͑��̏��ł����Ɍ����p�S�̓��v���̓V��_�Ђ��V�ڈ�Ӑ_���J��A�������R�쒬�̓V��_�Ђ��V�ڈ�Ӑ_���J��ȂǂƏЉ��Ă���B�ǂ����V��ЂƂ͕Жڂ̎Y�S�_�ł���A�V�ڈ�Ӑ_���Ր_�Ƃ��Ă���Ǝv����̂ł���B�V�ڈ�Ӑ_�̗��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B �@�q ������́w�ዷ�H�x(��43�E�W����)�́A �@�q �@�����ዷ�̎q�����A���̕����Ɏ��������悤�ȏ��ɐ��܂ꂽ�B�Y���ɂ͂Ȃ���������ǁA�[�˂̋��ŁA�Y�k������A��͑c��Ɏ�����Ă�����āA�����Y�ƍ��������̂ł���B�@ �����Ƃ��ŋ��̖��ʌ����͂���ȊO�ɂ������Ƃ����Ƃ����Ƃ����Ă��̕���͑��ΓI�ɂ͏��������ł��邩���m��Ȃ��B�����������������_�l�Ԃ��A�Ȃ����݉��l�̂��߂����ɖ��ӂƂ͊W�̂Ȃ��喳�ʌ���������̂ł���B�܂��͑�{��f�B�ŋ��̖��ʌ����̌��͖��ʂȐl�Ԃɂ���B����l�͐ŋ��ł�������Ń��V���̂͒p���������Ƃ������o���Ȃ��B���̂��߂ɓ����Ă��܂����A��K��������Ă͂��܂���ŁA���������s���ʼn^�c����Ȃ���A�{���͎����̂��悭�Ȃ�͂��͂Ȃ��B�P�O�O�O���~�ɂ��Ȃ�Ԏ��A����ł��P�O�O�p�[�Z���g�ɂЂ������Ă��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��B���ŕ������ׂă��_�Ɏg���邾���ł��낤�B����ɂQ�O�O�O���~�ɂR�O�O�O���~�ɁA�c�ǂ�ǂ�c��ނ��Ƃł��낤�B�d�g�݂�ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�q �o�Y�����镔����{�݁B���ʂɎY������݂�����̂Ǝ���ŏo�Y������̂Ƃ̓������B�Y�����̓f�x���A�^���A�q�}���A�J�����ȂǂƂ��A���o���������˂Ă�����̂�����B��������Y�̊��ɂ��A�Ƃ̉��������̂�������āA�ʉ̐�����������̂ł������B�L�I�ɂ݂���L�ʕP�̏o�Y�̂悤�ɁA�Â��͏o�Y�̂��߂̉������͂����R���A�C�ӂȂǂɗՎ��Ɍ��ĂāA�Y�����߂ΔR�₷�����킷��������̂ł������B����������܂ł́A�������̎Y������݂��A�Y�w���Y�̊��̊�(21�`75��)�����ɂ����镗���A�u�������A�։ꔼ���A�ዷ�p���݁A���˓��C���݁A�ɓ������ȂǂɌ����A�։ꔼ���ł�1964�N����܂Ŏg���Ă������̂�����B����ŏo�Y����ꍇ�ɂ́A�j��(�y��)��Q��(����)���Y���Ƃ����B���̊ϔO��������Ă����ƂƂ��ɁA�ꉮ�̒��̔�r�I�u�����ꂽ�i���h�Ȃǂ̐Q���ŏo�Y������悤�ɂȂ�A���̕���1955�N����܂őS���̔_�R�����ōs��ꂽ�B�_���̊��̌��d�ȏ��قǎY�������g���A�_���œ���(�Ƃ���)�Ȃǂ̐_���ɂ��Ƃł͏o�Y������Ζ������ނ�����A�Y�w���Ƃ��瑼�ֈڂ��A�Ղ�̍ۂ͎Y�w��_�Ђ��痣�ꂽ���Ɉڂ����B�܂��A����̘F�ӂŏo�Y�����萷��ɉ��ďo�Y���鏊������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�員 �䂫 �@�Y����ʏ�̏Z���Ƃ͕ʂɐ݂���K���͐��E�̊e�n�Ɍ�����B���̏K���͋��Z��Ԃ������ꍇ�ɂ͔D�Y�w�ƐV�����̈��Â���̕X�̂��߂��ƍl�����Ȃ��͂Ȃ����A�ނ���A�o�Y�Ƃ������̂�����I�Ȍ��ۂƂ͒������قȂ���ʂ̂ł����ƂƂ݂Ȃ���A���ꂪ����I�Ȍ��ۂƍ����荇��Ȃ����߂̏��u�ł���ƍl��������Ó��ł���B�܂��A�o�Y�͏����݂̂ɋN���錻�ۂł��邽�߁A�j���Ə�������ʂ���X���̋����Љ�ł́A�o�Y��j���A���ɕv�����������Ԃ��痣�ꂽ���ōs�킹��ꍇ�������B�Y�����݂�����Љ�ł͌��o��o�Y���s����邱�Ƃ������A�j�����Y���ɋ߂Â����Ƃ͊댯�ł���ƍl������B�����ɁA�����̂̃����o�[�ɂƂ��Ă͐_�����d�v�ȏꏊ�ł����邽�߁A�悻�҂�����ɋ߂Â����Ƃ͏d��ȃ^�u�[�ƂȂ�B�@�@�@�@�@�g�� �b���q�@
�@�q �@�\���i�{��j�̓��݂ɒ����B�_�Ђ̐X�͓�k�̏M�`�ɉ��т鏬�R���Ȃ� �@���ʂɖ{�a�A���E�ɘe�{�A����ɖ��ЎO���Ђ����сA���{�̍c��_�Ёi���{�Ƃ������j�Ƃقړ����z�u�ł���B�u�O�㋌���L�v�ɕʋ{�ƋL����鑽��_�ЁE���Nj{�E �@���q����ɐ��������u�_���ܕ����v�ȗ��ɐ��_���ł́A�Y���V�c���N�`�P���ɓV�Ƒ�_�̐_��������A�O�g�i��j�̗^���{����L���_�����a�Ð_�Ƃ��Ĉɐ��̎R�c���i���O�d���ɐ��s�j�Ɍ}�����̂��A�ɐ��O�{�̎n�܂�Ƃ����Ă���B���̗^���i�Ӂj�{�ЂƂ����������A�ߐ��̒n���u�O�㕗�y�L�v�� ![�L���_�Ёi��]���V�c���j](gekuj4.jpg) �@���n��^�ӂ̔���m���䌴�Ƃ��ւ�^��Ƃ��B�^�Ӌ{�Ɖ]�B�Ր_�L�_�{�������̒n�ɂ��ėY�������N�_���L�ė��N���B�R�c���j�A���Ȃ����Ɖ]�B �@���H���_�Ђ͎��ɉ]�O�㍑�O�g�S�䎡���ވא_�ЂȂ�ւ��Ƃ��B���\���Б��O���{������{��苫�����܂�����Ɛ_���Ђ��邠�肳�܂��͂炷�B �ƋL���A����W�ɂ͎��̂悤�ɂ݂���B �@�L��{�n���헧����A�����X�n���E�V���������A�Y�����V�c�m��F�����A�{�V�ܔN�㌎����{���A�l���O�\�O�㐄�Ï����\�꒚���N�O�{�J�����ɐ��� �@�u�a���O�ː}��v�͗^�Ӌ{���u�^�ӌS���v�ɂ���Ƃ��A�V�c�������]�ˎ���ɉ͎�g��O�����Ɋ܂܂�Ă������ƁA�܂������̏���������ɂ��̒n��^�ӌS�Ƃ��Ă��邱�ƁA�O�{�K�{�͓c�������̖����E���\�ȍ~�̐_���ً���ɂ��݂ȗ^�ӌS�Ƃ��邱�ƂȂǂ���A�ߐ��܂ł��̒n���^�ӌS�Ə̂���Ă����Ƃ�����B�������������ɂ͈�т��ĉ����S�Ƃ���Ă���B �@�u�����S���v���ڂ̓��Ђ̗R���́A�Y���V�c���N�A�V�c���_�q���A�O�g���O�g�S����̖��ވׂɍ����L���_���ɐ����x��̊O�{�Ɉڂ������A���炭���n�M���R�ɒ��������̂Ɏn�܂�Ƃ���B����u�{�Õ{�u�v�́u���З^���{�����q�e���V�������A�_�Ќ[�֓����ȓ��Јח^���{�Ҕ����v�Ƃ��A�p���V�c��O�c�q���C�q�e�����S���ގ��̕��Ƃ��Č��������Ƃ����B ![�L���_�Ёi�O�{�j�i��]���V�c���j](gekuj6.jpg) �@�����N�i��Z�ܘZ�j�l���A���㌎�̔N�I�������D�ɂ��ƁA�{�Ôˎ勞�ɍ��������R����j�g�̕a�������F�肻�̕��Ƃ��Đ_�y���E�䋟���E�֑������Ă���A�Ȍ�Z��N�Ɉ�x�̎��N���ƂɎГa�c���Ă����Ƃ����B�����N�ԁi�ꔪ�Z�l�|�ꔪ�j�̊o�����i�V�c���ѓc�ƕ����j�ɂ��A�ޖ؈����߂���Гa�����܂ŎO�N�]���v���A���J�{�̎��ɂ́u�Q�W�삵�����m�R����{�Â܂ŏh�܂�ĂȂ��v�Ƃ���A���̒n����тŐ��h����Ă������Ƃ�����������B �@�l�ΘZ�l�l���̎З̂��������i�V�a���N�{�×̑������j�B�@ �{�a��������Ǝ��͂�ł��閖�Ђ������グ�Ă����ƁA�������č��肩��A��K�E�V�c�E�I�{�E��{�E��X�E�a���E�䙚�E���E����E�m�b�E���{�EꝌ��E��E��V�E�����E���������E�H�ˁE�_��E�����E�ɏ��E���{�E���́E��E�ۘQ�E�����E�E�V�E�b�V�E���E��颁E�H�E��V�E�匴�E�P��E�֖{�E�P�ˁE���g�E�E�ۗ{�E���B�{�a�̌������č���ɑ���V�{�A�E��ɓy�V�{������B �@�q ��y��_�{�z�����S���{�Õ{�u�A�V���L�H�A���͎̉�̓��O�{�͌Â֖��q�e�������̋����𐪔��̎��������鏈�Ȃ�A���{�O�{�̊ԂɌ����E���J�Ɖ]�Ӎݖ�����A���e���̉Ɛb�̎c��čݖ��ƂȂ��Ƃ��A���q�e���͗p������̍c�q�ɂĉX�ˉ��̒��A�_�Ќ[�֓��̏��A�ȓ��З^�ӕx�Ҕ��B�@ ���炭�R�E����(���E�͎�)�̒n���͂��̐_�Ђ̂����肩�琶�܂ꂽ�̂łȂ��̂��Ǝ��͍l���Ă���B�͐�̉^���J���҂Ƃ��������������邪�A����͊��������Ă̘b�ł͂Ȃ��̂��B�����̒ʂ�Ȃ���j�����͉��̋�J���Ȃ����낤�B �@�q ���̕ӂ�͓y�w偂������T�J�Ƃ����ƕ��y�L�͓`����B��]�R�̒���ɉ_��(�Â��͗^�ӌS�ɑ�����)�Ƃ����W�������邪�A���̌��ɐ��O�{�̂�������_���ƌĂ����ł���B�����̉_�͒w偂����m��Ȃ��B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||