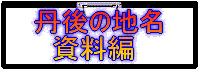 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
《河辺八幡神社の概要》 舞鶴市の東北部。引揚記念館のすこし先、野原の方へ行く道中の河辺谷を流れる河辺川の河口付近。河辺中の道ぶちに鎮座する神社。 怖ろしく古い神社で、丹後風土記残欠に河辺坐三宅社とあり、式内社・三宅社に相当すると北吸の三宅神社と比定論争をしたこともある。 貞治3年(北朝元号・1364)8月25日と銘を刻んだ石燈籠がある。 昭和41年3月6日、少年の放火で、本殿が消失、木彫の神像三体も黒焦げとなった。等身大の大日如来像、大般若経約三百巻がある。 河辺中、西屋、室牛、河辺由里、河辺原、栃尾と河辺谷六字の氏神で、多くの伝統芸能が伝わる。9月15日の獅子舞祭に奉納される古い面をつけて舞う「田楽」も、府登録文化財、市無形文化財に指定されている。  《境内社》 境内社・疫神社、大川神社、蛭子神社、愛宕神社。後に合祀→元栃尾の愛宕神社、元西屋の大谷神社、元室牛の天照皇太神社、元河辺原の荒神社、元河辺由里の若宮神社
《丹後国加佐郡旧語集》 〈 《丹哥府志》 〈 【八幡宮】(祭八月十五日) 宮の内に古代の獅々頭並鋒釼の類伝はる。 《田辺旧記》 〈 《加佐郡誌》 〈 由緒 古老伝えて曰ふ「当社は往昔三宅八幡宮と称したが中世社号を転じ八幡神社と称する様になつたのである」と、現今保存してある古幟の内には三宅社と記したものがある。丹波風土記で「河辺座三宅社」とあるは当社のことであって亦延喜神名帳に出た三宅神社であることも疑いない。創立年代は詳ではないとはいえ再建年代は至徳六年正和二年正慶六年寛永四年等であること今現に存する棟札に依って明らかである。 境内神社 疫神社(祭神 素盞鳴尊) 大川神社(祭神不詳) 蛭子神社(祭神蛭子命) 左に掲げたものは近代氏子が区内の無格座を本社境内へ合併したものである。 愛宕神社(祭神加具槌命 相殿 大物主命 火産霊命 稲蒼主命ウガノミタマ) 大谷神社(祭神素盞鳴尊 火産霊尊 稲蒼玉命 他不詳) 天照皇大神社(祭神加具槌命) 愛宕神社(加具槌命) 荒神社(祭神不詳) 若宮神社(祭神大山祗命其他不詳) 相殿(稲蒼玉 大国主命) 《京都府地誌》 〈 《舞鶴市史》 〈 八幡神は早くから仏教と習合したが、民間に流布するのは本地垂迹説の完成する中世以降とされるから、同社の起源については、「神名帳」所載の三宅神社が、八幡神の流布によって祭神が替ったか、あるいは創建当初より八幡神を祀ったか、検討の余地が多い。 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石灯籠 田楽舞 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年に1度の河辺八幡神社の大祭り。河辺谷の6字がすべて揃う。  谷の一番奥に位置する栃尾は8時30分出発である。それまでにここ極楽寺(兼、神社、消防団本部。東大浦村役場はここに置かれていた)で舞(大刀振りなど)を奉納し終えている。幟や笠鉾、太鼓屋台を引き、舞手を従えて約4キロ下の河辺八幡へと向かう。 祭が終り、屋台を引いて栃尾へ帰る頃はもう薄暗くなるという。  やってくると、合流する。 祭礼行列にはさらに河辺由里、室牛、西屋が合流して、大行列になる。  出迎えるように、少し先へ出て待っている。  今回は舞鶴市教委がこの祭礼の様子をビデオ記録していた。市の広報課のおネエさんとポリスマンも忙しそうな様子であった。  ここに3段の石段と、先にもも1つ石段がある。 おジイちゃんおバアちゃんの多い所は思わず手伝いたくなるが、そんなことをしていいのかどうか。 見物だけにしておこうか。     だいたい11時くらいであった。  ここへ登ってくるのは、舞殿で演じられる大刀振りなどの囃子のため。  「村には子供がいませんもので、外へ出た二世、三世に祭のときだけ頼むんです」という。 「学校へはバス通学なもので、子供達は地域を知らないんです、隣の村の名さえ知らない」。「××兵衛のとこへこれ持っていっといてくれ、と頼んでもその屋号がわからない」。自分の村でさえ知っているのは同級生などのいる家だけで、そのほかの家はまったく知らない。 子供が少なくなれば、子供がいてもその子すらも村社会からほとんど切れてしまうのだ。子供社会としてなければ村とは切れる。衝撃的な話も伺ったのであった。  「式内三宅神社 明治十三年八月吉日 願主 西屋村 田中竹三郎」 とある。 西屋あたりに式内社・三宅神社があったのではなかろうか。江戸期の記録にも見当たらないが…  ここは原だろうか。こんな練り込みを演じていた。  本殿前の広場に各地域が陣取ってゴッツォを広げている。 その石灯籠が貞治三年の銘を刻む南北朝時代のものである。 さて私どもはメシもない。朝飯も喰ってなかったな。ワリワリときた日には朝6時からメシ喰うのも忘れ、カメラぶら下げて飛び出して来るだけの者ばかりである。うまそうだワイ、とヨダレを垂らしていたので、哀れと思われたのか、酒とゴッツォを恵んで下されたのであった。      この祭礼とは別に「鉾の舞」「獅子舞」「太鼓の舞」「膝ずり」の伝統芸能(府文化財)がある。それが見たいのだが、それは今年はもうすでに終えたそうである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007-2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||