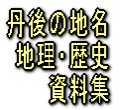 |
古代丹波歴史研究所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 ここだろかなぁぁぁ。そう書いてあるわなぁぁぁ。  丹後の知の宝庫・宮津図書館の横のガラスばり大部屋で、アカデミックな雰囲気というよりもショッピングついでの感もあるが、内容はちょっとそこらでは聞けない超学術もの。ぜひ入って聞いて下され。 伴先生はいつも何とも愛想の良い面倒見のよい方で至れり尽くせり、そのスタッフたちも自然それに見習って、それが身についていてまことによろしいお仕事のスタイル。 この人を見ていると古代の丹後の女王たちはいろんな面ですごかったのでなかろうか、という気がしてくる。 トップがこうでないとスタッフもダメになる、を見る思いがさせられる。エラそうにふんぞり返ってる組織トップなどはぜひ見習うがよろしいかも…  奈良女子大学副学長 小路田泰直先生  古代丹波歴史研究所所長 伴とし子先生  この時の動画もあるが、アップは著作権の関係からムリ。  小路田先生を囲んで… 丹後若狭など畿内権力の中枢に近い日本海側地域は大変な所であるはず、げに越前からは継体天皇が出ている。丹後だってもっと古代に大王が出ていても何も不思議はない、そんな古い時代に国家を支える生産力も技術も持たない段階でエジプトや中国なみの統一古代国家があったとしてのハナシで、しかし少なくとも丹後は国内に冠たる先進リーダー地域であったのであろう、新しい権力はだいたい外からあるいは下層から発生してくるもので、文化の真ん中から上から発生してくるなどはなかろう、地方や下層が相対的にしっかりしていることが新しい時代を迎える前提条件、中央が肥大化するだけでは滅亡、正史にはないが、これはワタシめの考えで、丹後がないことには新しい日本はうまれることはなかった、だいたいはそんな丹後びいき信念者たちのあつまりのハナシ… 翌22日は現地へ足を運んだ。台風接近で小雨が降ったり止んだりの天候。  丁寧な案内板がある。(案内板はこう作れよの手本か)  龍穴 元禄九年(1696)の浦嶋口伝記によると「小舟に乗りて水乃江の湖中、白鷺岬亦は龍穴の辺りに釣魚して遊ぶ。或る時は図らずして一霊亀を得て舟の中に入れる」とあり、龍穴が出てくる。この龍穴には、「龍宮に通ずる穴」「浦嶋子が龍宮より帰郷した穴」「浦嶋子が龍宮より帰郷時に休息した場」など、様々な説話が残っている。この穴に白い犬を放った時、この地の北東、海岸にある隠れ里(注)の風穴に出たとの伝承も残る。浦嶋伝承は、中国の風水思想が背景にあるといわれている。 『丹哥府志』天保十二年(1841) 「龍穴一に風穴といふ、殊に此穴より清風吹来りて夏などは至て涼しき事なり、かくれ里より此穴に通ずといふ左もあらんと覚ゆ、穴の傍に碑あり島子龍宮より此所に帰り来るいわゆる龍穴是なりといふ。」 出展:「丹後郷土史料集 第一輯」昭和十三年(1938) 『丹後州宮津府志捨遺』安永九年(1780) 「霊穴 本書にみへたり。此穴の傍に立石有碑文を彫刻す、「浦島か子従二龍宮一此所へ帰来則爰龍穴と伝」と記す、此碑は奥平候の代官菅沼吉兵衛といふ人建しといふ、俗に風穴ともいふ也」 出展:「丹後郷土史料集 第二輯」昭和十五年(1940) (注)隠れ里 浦島漁港から北へ約1km行った海岸に7~8m四方の穴があり、この穴の中に入り祈願すれば、霊験あらたかで願いが叶うとされている。この隠れ里の伝承は、亡くなった人をこの穴に安置し、霊は海の彼方の常世の国へ行くという思想があったとの推測のもと、かつては両墓制があったことを示すのではないかとの説がある。その仮説を裏付けるように、この地より南へ約4kmの海岸にある「雷神洞(はたがみぐろ)」、別名かくれ里とも言われる別の横穴からは、昭和二年(1927)に素焼の徳利や平皿、人骨と木棺などが数多く発見されている。 『丹哥府志』天保十二年(1841) 「本庄浜村より海岸にそふて舟行十町斗も行く所に二、三間四方の穴あり、穴の深サ幾許あるをしらず、穴の内は立派に掃除Lて小さき幟を多数たつ、如何様なる訳なりやと尋ぬれば穴の内に是は神体といふものもなけれども穴の内へ入りて祈願をこむれば極めて霊験あり此幟は願満の幟なりといふ、以前は穴の口に至りて思のまま願をこむれば何によらず膳椀の類まで穴より出たりとかや、抑斯様の噺は奇怪にわたれども但馬なぞにては海岸山谷こ限らず武家の内にて天井より銭の落ちたり戸棚より衣服の出たる事ども往々これあり、皆狐狸の所為なり奇怪といへば奇怪なれども何ぞ怪しむにたらん」 出展:「丹後郷土史料集第一輯」昭和十三年(1938) 郷土の歴史と文化を守る会  記念撮影  ここからDown Load (2L版くらいまでなら綺麗に印刷できます)  ここからDown Load (2L版くらいまでなら綺麗に印刷できます) 宝物資料室で宮嶋宮司さんよりお話を聞いた。1時間ばかり。  玉手箱↑。亀甲紋櫛笥で室町時代の今で言えば「櫛などの化粧品入れの箱」 浦嶋明神縁起絵巻掛幅↓というものか、室町時代のものという。浦嶋さんは亀に乗って龍宮へ行ったのではなく舟で行った様子が描かれている(亀に乗るのは江戸期になっからのハナシ)。 誰でも知っているつもりの浦嶋伝説だが、飛鳥時代からの長い長い伝承の歴史があり、残された関係する膨大な古資料を調べるだけでも一生かかると言われる。思っている知っているつもりのほどには甘いものではない。   小舟で「蓬莱山の国(とこよのくに)」に行く浦嶋太郎と乙姫(名は違うかも)の様子も描かれている。 蓬莱山と書いてトコヨと読んでいる。逸文風土記では「蓬山」と書いてトコヨノクニと読んでいる。 「蓬」はヨモギ、「莱」は「アカザ」という草で、「藜」(レイ)とも書かれる、ヨモギより大きく名の通りに赤い部分があり食べられる草だという。草冠をとった「黎」は黒の意味もあり、こんなことからかトコヨノクニには黒ヨモギが生えていてそれを徐福が取りにきたというハナシがよく聞かれる(というかそんないわばアホクサイ説ばかり)。  仙境(とこよのくに)に遊ぶ嶼子が描かれた部分。よく書物などにも引かれているところ。 甘い甘い通説、その根拠としているかなり後の世のせいぜい江戸期のおとぎ話の、いわば修正浦島太郎像をひっくり返すようなお話もいろいろうかがった。 そのほか…どれも大変に興味深いものであった。(フツーとは頭が何個か分抜き出ているような別次元の辛口の浦島太郎の話ばかり、しかしウロ覚えで本意通りに正しく聞けていたかはわからないが…)   ツンダメはこの堤防の先の方にある。海は荒れ模様。 |
会の記録 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2019 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||