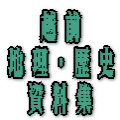 |
津守郷(越前国敦賀郡)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津守郷の概要《津守郷の概要》 どれもムズ古代地名だが、これらの郷で、今も遺称が残っているのは鹿蒜神社くらいで、あとは確かな証がなく、アバウトな推測説しか書きようがない、誰もがナットクのハナシはムリのようである。(しかも敦賀市より足を伸ばして調べた地はなく、旧敦賀郡内にはなるが、今はほかの自治体となっている地については、あくまでも机上調査によるもの) 天平神護2年(766)10月21日越前国司解(東南院文書)に、「敦賀郡津守郷戸主秦下子公麻呂」は坂井郡田宮村の西北2条6粟生田里1坪奥田に口分田6反240歩を所有したとある。…家族分合わせての口分田であろうか、新たな墾田であろうか。しかしこんな遠くに田があってもどうやって耕作するのであろう。 あとはずっと下るが南北朝期の貞和2年(1346)3月日の「西福寺文書」で、「行豊田地売券」に「合壱町者(字長沢) 在越前国敦賀津守郷道口之内」とあり、新御所又三郎・余呉又次郎に売渡されている。これから津守郷は今の敦賀市道口・長沢を含む一帯と考えられる。笙の川下流域の広い範囲である。 天香山命之後ともいい、火明命八世孫大御日足尼之後也ともあり尾張氏同族である。津守氏は欽明朝の己麻奴跪が遣百済使、皇極朝の大海が遣高麗使、斉明朝の吉祥が遣唐使として派遣されるなど、たびたび対外交渉の任務に就いているほか、遣唐・遣渤海主神(神主)の任を負って派遣された氏人もある。古い渡来氏のようである。だいたい港や交易といった生命線はそうした人々によって開発されたものであろう。 津守郷の主な歴史記録『大日本地名辞書』津守郷。和名抄、敦賀郡津守郷。今敦賀町是なり、此地古来北陸の津頭にして、知津事ありけるにより、津守の名も起りしならん、摂津国西成郡り住吉、菟原郡の住吉の両津並に津守郷と称したるも、此例に同じ。(今敦賀に津内てぬ地名存す) 敦賀は垂仁紀に角鹿と記し、異俗の人来泊の浦とす、霊異記に都魯鹿津と云ひ、万葉集には角鹿津とあり、延喜式には北陸諸国の漕運皆之を此津に会せしめ、其功賃を規定したる由見え、当時一方の要津たりし状想ふべし、諸国運漕功賃、佐渡国海路、自国津漕敦賀津、船賃石別一束四把云々。 しらま弓つるがの船路夜もなほおして引きこす波のかげかは、〔夫木集〕 敦賀金崎港より舞鶴へ五十海里、三国三十六海里、金石七十海里。 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2024 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||