 |
八田郷(やたごう)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八田郷の概要《八田郷の概要》 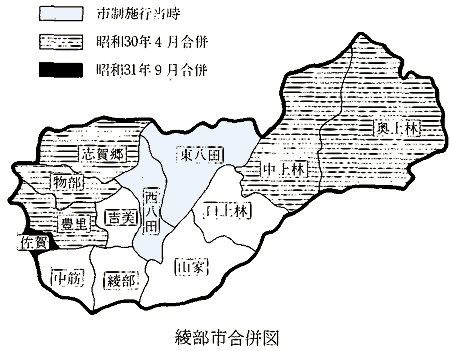 八田は矢田とも書くように、ハタやハッタでなくヤタである。由良川の支流八田川流域に位置する。 八田郷は、奈良期~平安期に見える郷で「和名抄」丹波国何鹿郡16郷の1つ。平城宮跡出土木簡に「□鹿郡八田里庸米六斗」とあるのが初見。郷域は現在の綾部市東八田地区の八代町・黒谷町・於与岐町・上杉町・梅迫町・安国寺町・中山町と西八田地区の上八田町・七百石町・中筋町・岡安町・渕垣町・下八田町に比定されている。 《古代》 郷域には高槻茶臼山古墳(前方後円墳)はじめ多くの古墳が確認されているが、ほとんどは未調査。旧石器が1点検出されているが、弥生末期以前に遡る遺跡は今は検出されておらず、だいたい古墳時代になって開発された土地と思われる。 この時代の残された記録はなく、出土品も限られていて、神社史や伝承や地名あたりから探ってみるより手がない。 域内には式内社が2社ある。島万神社は天平9年の痘瘡流行時に平癒を祈願して八田・吉美両郷民が創建したとされる、その通りならばそう古くはないが、それでは社名と合わず、「万」がどこか気になる、この社名は本来は金属溶鉱炉の意味かも知れない。 福太神社は、此社地ヲハ八田ト云ハ八田郷ノ親村。往古大破シテ丹後国高野郡斎ノ社(竹野神社のこと)ニ住玉フ 当村ニ教アツテ又本ノ如ク明神ヲ引移スト 故ニ誤テ斎明神ト云人アリ(丹波志)とあり、八田郷発祥の由緒を伝える。福は「銅や鉄を吹く」だろうし、フクダは網野銚子山古墳や網野神社あたりを福田というし、伊根町の筒川庄にも福田村があり、宝蓮寺という宇良神社の別当寺があった。それらと同じ名である上に、さらに当社は齋神社(竹野神社)の分社のような記録で、当社付近から八田村は広がったという。 景行紀に、碩田国直入縣禰疑野(大分県竹田市菅生付近とか)に土蜘蛛・八田らがいたので撃ちて破ったとあり、「豊後国風土記」にも同じ記事がある。場所は大きく違うが八田とは意外にも土蜘蛛であったかもの記事である。八田は丹後の産鉄民が切り開いた土地かも、と推測される。 式内社ではないが、飯宮(上杉八坂社)は、社伝によると崇神天皇の10年秋、丹波国青葉山に玖我耳という強賊がいて良民を苦しめるので、勅命を受けた日子坐王、丹波道主命が軍をひきいてきたところ、丹波国麻多之東において、毒蛇にかまれ進むことができなくなった。時に天より声があったので、素戔嗚尊ほか三神を祀ったところ験があって病が治り、首尾よく賊を平げることができた。帰途、この地に祀ったのに由来する(「郷土誌 東八田」)という。 「麻多」は江戸期でも、東股村、西股村として残っている、マは万と同じでここでは溶鉱炉の意味、賊というのは産鉄民のこどであろう、退治したというのではなく、退治した者と退治された者は同じ者の伝承の原則にそえば、日子坐王、丹波道主命が開いた彼ら自身すなわち、権力側の呼び名に従えば、皇国史観の呼び方のように言えば「丹後の土蜘蛛の社」ということになる。 齋神社は、丹後鬼神退治麻呂子親王願神ナリト(丹波志)という。 齋神社というのは竹野神社のことと思われる。 八代には浦島神社があるが、由緒不詳、しかし社名から丹後の浦島太郎さんだろうと思われる。浦島太郎さんが冬期は当地へ来て、銅か鉄を採った地だったと思われる。 これらを総合すれば、八田は竹野神社の産鉄民(鬼)を中心に、開発され、高槻茶臼山古墳造営時の古墳時代初期の当時は丹後・丹波を通じて最も文化の高い、最も経済力の高い先進地域であったと思われる。平安時代となれば、面積の割には人口がないので、資源を取り尽くし、燃え尽きたのかも知れない。 なお八田は久美浜町海士の式内社・矢田神社のヤタと同じで、同社の元々の鎮座地・安田、アタのこと、すなわちワタで海のことと思われる。 任那の四村に安多(あた)、委陀(わた)が見られ、こうした海人語も「純粋な日本語」と言っていいのかどうかはアヤシイ。純粋な日本語や日本人などはないかも知れない。いろいろな人や文化が混じり合って出来たクニのようである。 また後の渡来氏族・秦氏などのハタもこの意味かも知れない。八田はプレ秦氏というか天日槍系の人達と呼ぶか、あるいはもっと古い渡来人であったかも知れない。 史料としては下って、仁平2年(1152)8月11日の東光院所蔵大般若写経奥書に「丹波国何鹿郡矢田郷東中村」とあり、寿永3年(1184)4月16日付の平辰清所領寄進状案に丹後国加佐郡大内郷の四至として「東限丹後(波)国何鹿郡八田・上林 八幡宮御領川上大坂」がある。 《中世》の八田郷 鎌倉期~戦国期も八田郷が見え、元弘3年7月日の祐忍言上状に「丹波国八田郷岩王寺」。 鎌倉末期頃と推定される足利氏所領奉行人注文に「八田郷」とあり、上椙三郎入道・倉持新左衛門尉などの奉行する地となっている。 建武元年12月27日の上杉朝定書状によると「八田郷内能登房跡」が光福寺(のちの安国寺)に寄進されており、これが上杉氏と安国寺の関係を知る初見史料。 上杉氏は当郷上杉荘を本領とし、足利尊氏・直義の母上杉清子は光福寺の地蔵菩薩に安産を祈願し尊氏を産んだと伝える。塔頭常光寺(大正初年廃寺)は清子の別邸であった。 建武2年3月1日の足利尊氏寄進状によれば、後醍醐天皇より賜った「日向国国富庄内右崎郷地頭職」を「丹波国八田郷光福寺」に寄進している。 建武3年2月9日の上杉朝定寄進状では「丹波国八田郷上村内貞行名」が安国寺に寄進され、暦応元年10月5日の某宛行状では「丹波国八田郷次郎丸内田弐段并家敷畠弐段」が妙行房に宛行われ、康永3年11月13日の某宛行状では「丹波国八田郷次郎丸鳥居野〈乗信房跡〉が満々房に宛行われている。 永和3年2月28日の室町幕府奉行人連著奉書では「貞行名」以下の寺領が安堵され、至徳4年6月29日の将軍家足利義満寄進状では「夜久野内今西並八田郷上村内貞行名」が安国寺に再寄付されるなど、室町幕府の手厚い保護が加えられていた。 応永5年11月24日の将軍足利義満下文によると当郷内「本郷」が上杉憲定に宛行われ、この本郷を除く部分は応永7年5月3日の将軍家足利義満安堵下文によると仁木義員に宛行われていた。その後この本郷は上杉憲実、ついで同房顕に譲与されている。 一方、応永29年5月14日の足利義持御判御教書および永享元年11月19日の足利義教御判御教書によれば「八田郷上村内貞行名」などの寺領が安国寺に安堵されて、応永33年7月14日の将軍家足利義持下文によると「八田郷上村」は御料所となっていたがこの日上杉憲実に返付され、同年7年20日の細川道観(満元)遵行状で沙汰付けられた。 舞鶴にも八田がある。今の西舞鶴の市街地の中心地が八田であった、その後田辺城築城で八田村は由良川沿いの地に移転となり、今はそこ、大川橋のたもとにある。呼び名はハッタとなっている、それが元々の呼び方であったかは不明。 《交通》 《産業》 《姓氏》 八田郷の主な歴史記録
伝説関連情報 |
資料編の索引
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『何鹿郡誌』 『綾部市史』各巻 その他たくさん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2017 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||