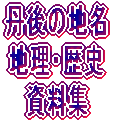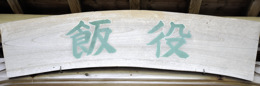京都府宮津市中野 京都府宮津市中野
 京都府与謝郡府中村中野 京都府与謝郡府中村中野
−天橋立観光−
主なものだけ
(文珠地区)
 智恩寺(智恵の文珠) 智恩寺(智恵の文珠)
 ビューランド展望台(飛龍観) ビューランド展望台(飛龍観)
 股のぞき 股のぞき
 天橋立温泉(智恵の湯) 天橋立温泉(智恵の湯)
 知恵の餅(橋立名物) 知恵の餅(橋立名物)
 知恵の輪 知恵の輪
 廻旋橋 廻旋橋
 天橋立観光船 天橋立観光船
 日本三景:天橋立 日本三景:天橋立
 磯清水 磯清水
 橋立明神 橋立明神
(府中地区)
 丹後一宮・元伊勢・籠神社 丹後一宮・元伊勢・籠神社
 真名井神社 真名井神社
 傘松公園 傘松公園
 西国28番札所:成相寺 西国28番札所:成相寺

 郷土資料館 郷土資料館
 国分寺址 国分寺址
|
飯役社の概要

↑一宮・籠神社の少し手前(西側)、国道178号線(軽トラが走っている道)の脇に「飯役社」と呼ばれる小さな社がある。今はただこれだけしかないが、なかなか歴史のある面白そうな神社。神額には「飯役」と書かれているが、少し古い地図などには「院薬神社」とも書かれている。
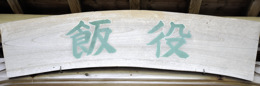

『京都府の地名』によれば、
飯役社 (現)宮津市字中野
中野集落の南方、海岸近くの森に簡素な社が建つ。祭神は御食津命。
「宮津府志」は飯役社の所在を府中溝尻村、「丹哥府志」も飯役大明神を溝尻村とする。中野には飯役・飯役前・飯役後・飯役浜・大門・大門東切の地名があり、溝尻には、東大門・ドイ・ドイノ下があり、同じく小松に、飯役ノ上・飯役立がある。飯役の直接関係地名は中野・溝尻などにまたがっている。
飯役はもとは印鑰で、国衙で国の正印と鑰を用いる印鑰神事が行われたのがしだいに年中行事化して、印と鑰を神体として在庁官人の守護神としての印鑰社が国衙の近くで祀られることになったといわれる。丹後国田数帳に与謝郡拝師郷のうち「一町 印鎰社」とあるから、おそらく丹後の国府の印鑰社は鎌倉時代末には成立し、一五世紀中頃にも存続していたことがわかる。 |
国の正印と国倉の鑰を祀るのだから国衙の守護神のような神社であったことになる。守護神は身近に置くものだろうから、この近くに丹後国庁があったのではないのか。「府中」というのはだいたいこの辺り、中野や大垣を呼んでいるし、近くには丹後一宮がある。国府がこのあたりにあっても何もおかしくはないのだが、しかしその明確な遺跡がない。まあ他の地からも見つかってはいないが…。
飯役社の北東側500メートルくらいの場所に大頂寺があるが、その周辺が中野遺跡で、ここからは8世紀に遡る奈良期の瓦が出土している。これが国府なのではないかとか、いや国分尼寺だとか推測されているが、「西寺」と書かれた土器もあり、一応は廃寺跡と考えられている。小地名の調査など、地名も馬鹿にはできない、というかワラにもすがりつくような話ではあるが、文書がなければそんなものでもと、いろいろ取り組まれているが、現在の時点では見つかってはいない。
国府といってもその位置は時代によって変わることがあるために、いつの時代かが問題だが、恐らく与謝郡に移ったもっとも初期の頃の国府がこのあたりにあったのではなかろうかと私は推測したりしている。
古代丹後の中心を考える上で何とも面白すぎるドキドキする神社なのである。
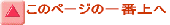
吹飯社と根子宮
『宮津市史』は、
| 国府にかかわる神社として「印鑰社」と呼ばれる神社の存在が知られている。印鑰とは印と鍵を指し、国司の国務執行にとってもっとも重要な国印と府庫の鍵を意味する。印鑰社とはそれを祀る神社であり、印鑰・印役・印薬などの文字があてられている場合もある。図ののように国分寺跡と籠神社の中ほどにある飯役社がそれに相当すると考えられている。印鑰が祀りの対象となるのは、一一世紀末から一三辻紀初めにかけての時期に、印鑰の扱いに大きな変化が生じたことにかかわると考えられており(木下良、前掲書)、印鑰社の成立もそれ以前にはさかのぼり得ない。 |
として、印鑰社は平安時代に入ってからのもののようである。ではそれ以前にはここには何もなかったのかと言えば、そうではなく、ここにはすでに大変に重要な神社があった。
『元初の最高神と大和朝廷の元初』には、
与佐官と吹井社・吹井大明神の縁起
浮渓大明神(吹井社)が、飯役宮と改称せられたのは、同地に、印鎰社があって、浮渓大明神と合祀せられ、豊宇賀能売神の飯盛りの役と印鎰の鎰とが重なって、その名称を生じたものである。浮景の浦に存在して、丹波道主、氷沼道主、豊宇賀能売神等をお祭りした古社である。
与佐宮大神即ち、真名井大神、籠宮大明神とは、極めて関係が深く、幕末以前までは、籠宮大神の御神幸の祭礼に、御神輿の御旅所となっていた宮処である。
この社は、所謂神仏習合時代に、本地仏として、鬼子母尊神を祭っていた関係もあって、本来は、与佐宮大神の所管社であらねばならぬに拘らず、室町時代の中期以後日蓮宗に属する寺院、妙立寺の鎮守となっている。
この寺に、飯役大明神縁起が伝えられているから、これを左に妙録しよう。… |
吹飯の浦
吹飯・浮景・浮溪などと書かれるが、フケイ神社がすでにあった。そしてこの神社前の阿蘇海を「吹飯の浦」、あるいは「ウケの浦」と呼び、日本三吹井の一として名勝であったという(丹後・和泉・紀伊)。吹飯神社がここにあったから、吹飯の浦と呼ばれたと思われる。
『宮津府志』
『丹後旧事記』
| 吹飯の浦。與佐郡板列の庄府中の海なり豊宇賀能(口編に羊)の神比治の真奈井ケ原より通ひて與佐宮大神へ御饗を奉り給ひし跡なりとて此神を飯役大明神と称す。是所謂與佐宮神戸所也依て爰の海を宇気の浦と云なり。… |
『丹後与謝海名勝略記』
【府中七ケ村】此古府なり。江尻、溝尻、小松、国分、大垣、難波野、中村なり。扨此海浜をなへて吹井といふ名所なり。但これより中村の西を記す。
続古今集冬 橋立や與佐の吹井のさよ千鳥 とをよつ沖よさゆる月影 (衣笠内大臣) |
『大日本地名辞書』
【天橋立】…略…○吹井浦、与謝郡板列庄府中七ケ村の浜辺をすべて吹井といふよし、続古今集冬部、
橋立や与謝の吹井のさよ千鳥 とをよる沖にさゆる月かげ 衣笠前内大臣 |

↑画面の一番右手、中ほどより上の小さな森が飯役社。
内陸に真名井の池を抱く西舞鶴湾を「九景が浦」とか「笛が浦」と呼んだのと同じで、真名井の別名・ウケイの転訛したものと思われる。
こんな名の神社があるのなら、真名井の池(フケイの池)がなくてはならないが、付近には池はおろか小川もない。頭を抱えざるをえないが、−
『元初の最高神と大和朝廷の元始』には、
吹飯の浦
丹後旧事記に、
与佐郡板列の庄府中の海なり豊宇賀能口+羊の神比治の真奈井ヶ原より通ひて与佐宮大神へ御饗を奉り給ひし跡なりとて此神を飯役大明神と称す。是所謂与佐宮神戸所也依爰の海を宇気の浦と云なり。
と見え、続古今、衣笠内大臣の歌に、「橋立や与佐の吹井のさよ千鳥遠よる沖に洩るる月影」とあり、千載集、藤原基家の歌に、「小夜千鳥吹井の浦に音つれて小島ヶ磯に月かたふきぬ」と見える古来の名所である。往古、籠神社の御撰供進所のあったところで、御本宮から西へ約七八丁の地帯にあり、此処に、御饌の井、即ち真名井があったと伝えられるところがある。この井は、既に寛保年中にうめられて、わずかに池の形だけを存していたが、先年道路の改修で、更に、変改せられて、漸く所伝によって昔を偲ぶに過ぎない状態になっているのは惜しまれる。
前述の如く平安朝の古歌にも見える所謂飯盛りの古伝承地で、紀州の吹井、摂津の飯盛山と共に全国有数の名跡であったが、今は日本三景天橋立の景勝の内に含まれ、或は比治山説話の蔭にかくれて、その附説の如く、文人墨客の間にさえも忘却せられようとしている。しかし、これは、今後改めて見直される点があらねばならぬ。 |
今はもうまったく姿形がないが、かつては真名井があったという。
 同書によっていま少しこのあたりの古代地名を見ておくと、− 同書によっていま少しこのあたりの古代地名を見ておくと、−
| …太神宮本記に見える吉佐宮、崇神天皇の御世三十九年壬戌の年に、天照大神が幸行されたと伝えられる吉佐官は、与謝郡に存在していて、現在の丹後国一之宮籠神社の御本宮の地と伝えられる。社記(一宮深秘、室町中期写本)に、此地は、元真名井原と云ったが、後に、これを府中と名づけられたと記されており、栄昌山妙立寺蔵重要文化財厨子裏書に、「飯守之森道主命之従二神殿一神火出日沼野諸家屋形堂宇民家至迄焼亡(以下略)」と見えている。日沼野は今中野と称する、府中の内である。府中は、中野と大垣を中心として、東に、江尻難波野、西に、小松、溝尻、国分の七ヶ村から成立っていて、北に山を負い、南は天橋立に続く、極めて景勝の地である。南は阿蘇海、東は与謝海、中央に天橋立が長く南方海上に延びていて、日本三景の一に数えられる土地なのである。伊勢国度会外宮の所在地が、山田原と呼ばれるに対して、吉佐官の所在地は、丹後国与佐郡の真名井原と言われた地域であって、これが、小見比沼の真名井原と大神宮本記に記されているのである。東の海浜与謝海に面した処を天の橋立をも含めて久志備の浜と言い、天橋立を境とした西の海の北浜日沼野(中野)の浜を、吹井(吹飯)の浦と称せられる。久志備の浜と吹井の浦は地続きになっていて、上古の真名井原なのである。この真名井原の奥宮真名井社の所在地を奥宮真名井原と云い、天照豊受両大神に御饗奉られたという御饌殿の存在していたところを御饌殿真名井原と言っている。乃ち、与佐郡の吉佐官に関する文献として、貴重な資料に、丹後国一宮深秘があり、この深秘は、その名の示す如くに、古来深秘とせられながら、社家の間に相伝されて来ていたものである。両部習合の仏説を加えて記されており、詳しくは相当の解説を必要とするものであるが、その始めは、鎌倉時代を降らぬ時代の筆述にかかり、現在に相伝されているものは、その略書であって、室町中期を降らぬ時代の書写にかかるものである。 |
一宮の浦とか宮浦とかは呼ばれないで「フケイの浦」である。籠神社の成立以前の浦名と思われる。
和泉国のフケイは大阪府泉南郡岬町の深日港、紀伊国は和歌山県日高郡由良町の吹井かと思う。そうするとフケイと由良は何か関係があるのかも知れない。
吹飯社
 こんな時代の話になれば、『元初の最高神と大和朝廷の元始』(籠神社宮司・海部氏八一代の当主・故海部穀定著)しか私は知らないのだが、同書よれば、 こんな時代の話になれば、『元初の最高神と大和朝廷の元始』(籠神社宮司・海部氏八一代の当主・故海部穀定著)しか私は知らないのだが、同書よれば、
吹井社
天照大神が、倭国の笠縫邑から、丹波国の与佐郡の与佐宮へ御遷座になって、豊受大神と共に、お鎮まりになっていた時に、丹波郡比治山(伊去奈子獄)から、豊宇賀能売神が、お出かけになって、氷沼の道主(粟御子神の子孫)や丹波道主王子八少童女等と共に、御饌御酒等を供えて奉仕された由が、伊勢の古典に伝えられており、又、伊勢酒殿明神即ち豊宇賀能売命が与佐郡真名井原へも、神代に天降っていられたというような説話もあるので、与佐郡の真名井原(与佐宮の宮処)は、比沼の真名井ではあるが、比治(比遅)の真名井の神即ち豊宇賀能売神にも関係があるので、比沼が比治でもあるような状態になっているのである。即ち、丹波郡の比治の神社を藤神社といっているが、与佐郡比沼の真名井にも藤岡の名があり、又、伊勢の豊受大神宮にも藤岡の名がある。氷沼道主の氷沼は氷沼の道主の意であって、比沼の真名井、即ち、与佐郡与佐宮の宮域内に、氷沼の道主が丹波道主命と共に祭られており、その宮を飯役宮(古称浮景大明神)といっている。又、この飯役宮について、丹後与佐海図誌に、
飯役神社、溝尻の東の方田間にあり。(中略)此社奈具神と同体なり。真井原程近き所なれは此社爰に有事むへなり。と云い、又、丹後旧事記、丹後細見録等に、
余社の宮辺を魚井原といふ事は天女宇賀能売命此地に通ひ止由居皇大神へ御饗を奉捧し神戸所有か故に魚井原と伝へて天女を飯役明神と祭ると見え、又、丹後国一宮深秘に、
神代有一翁号塩土翁八人天女降浴二清流一清流者粉河也称粉河故者天女此作レ酒其水色粉流似故粉河云彼天女翁起レ欲取二蔵天羽衣一間輒天不得帰然間成夫婦此処作酒渡世伊勢酒殿明神者勧三請自二丹後国一和朝酒根本是也彼天女在所口伝在之
と見えていて、豊宇賀能売神が与佐宮の神域内へ降臨、或は伊去奈子獄から通われて、与佐宮の大神に御饌を奉られたことを伝えている。飯役宮は、元、当神社の所管社で、古くは、吹井社といっており、その南方の海を吹飯の浦といっていたものである。 |
丹後一宮・元伊勢・籠神社の御旅所であり、後の江戸期の藩主たちも籠神社に参拝の折は、「ダイミョウ道」を通り、まずはこの飯役社から訪れたという。
籠神社の故地とも受け止められるような破格の神社で、籠神社よりも古いと思われる。
籠神社の始まりは実はそれほど古くはなく、大化4年(648)に、真名井原の籠の川(真名井川)のほとりに神籬を起こしたのが始まりとされる。丹後国の成立や一宮祝家の確立と関係する政略的な神社であったかと思われる。
根子宮(奈具社)
 飯役社の東側100メートルばかりの所に「根子宮」がある。 飯役社の東側100メートルばかりの所に「根子宮」がある。

何も道もないし、目印もないが、鎮守の森の残りらしき少し背の高いタモの木が立っているので、それを目当てに行かれるといい。蔓草に覆われているが、払いのけると「根子宮」と彫られた石が出てくる。ただこれだけの祠である。
根子だから猫だろう、国倉米蔵のネズミを退治してくれるように祀ったのだろう、などという話も真面目顔になされているが、そうではないようである。
『元初の最高神と大和朝廷の元始』には、
奈子宮(奈具宮)
豊宇賀能売神に就ては、飯役宮の東方に、根子宮という小社があって、これも道主命といわれているが、実は、根子は奈子であり、奈子即ち奈具で、奈具宮を意味していて、此処に、その所伝が窺われるのである。
豊宇賀能売神は、普通一般には、丹波郡の伊去奈子獄から通われて、与佐宮大神へ御饌をお供えになったと云われることになったのであるから、必然的に、史伝の方が説話に押されて、吹井浦に於ける豊宇賀能売神の祭祀は、忘れられ勝ちになったわけである。しかし、与佐宮大神に御饌をお供えになった道主命と豊宇賀能売神とは、極めて深い関係にあらせられるのであって、飯役宮の縁起には、その御名が見えなくても、根子宮は豊宇賀能売神を祭るところであり、又、別に、飯役宮に、同神を祭る伝があり、尚、豊宇賀能売神が、此地へ通われて、与佐宮大神へ御饌を奉られた伝が存在することは、吹飯(浮渓)の浦が、御鎮座本紀其他、神宮の古伝書に見える天照豊受両大神御変座の古伝地であることを表示するものであると云い得るであろう。
飯役大明神縁起及び口上覚に見える毎年四月の一宮祭祠日に、浮渓(浮景)大明神の宮殿から、正午の膳(御饌)を、一宮(与佐宮大神)へ送ってお供えすることの伝は、崇神天皇の御代、天照豊受両大神御双坐以来の古儀であり、この浮景大明神の宮殿、及び、その別社根子宮には、丹波道主、氷沼道主及び豊宇賀能売神が祭られているのである。
この浮景大明神は、鬼子母尊神を本地仏としていて、明治維新の際、之を除去して、籠宮(魚井原本官という)に所管社として復帰するよう努力せられたのであるが、鬼子母神の信仰が相当厚かつた為に実現に至らなかったのである。前記の口上覚に見えるように、毎年九月十五日から十六日への祭礼には、御神輿が、堂内へ入御、通夜せられた場合もあり、又、毎年四月の例祭には、神輿御神幸のお旅所となっていたのである。明治維新神仏分離の結果、お旅所でなくなり古儀の一端が変改せられねばならなかったことは惜しまれる。
以上の飯役大明神縁起の記されたのは、大体、宝暦から寛政十一年に至る間と考えられるが、(日生は宝暦九年に隠居している)寛政十一年に、日恕が之を集成したもので、記録としては、近代のものであっても、この伝は、伝として吉野朝時代まで遡って考え得る貴重な伝であることは、更に、次に述べよう。 |
吹飯社と同体、あるいは吹飯社の別宮とされた奈具社が根子宮となったようである。
ナグとかナコ、あるいはネコとなったようで、これはあるいは古くは天橋立の本名であったかも知れない、もとをたどればナーガ神と思われ、ヘビである、成相寺の成相は、成合とも書かれあるいはこれもナコかも知れない。成相寺には大蛇がいて、それが海に入って天橋立になったと伝説は伝える。成相の本来の意味が秘められていそうな伝説である。
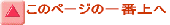
丹波国造・海部氏の足跡
 これらの神社にまつわる信仰上の話は私はよくわからないので置くとして、籠神社の祝家・海部氏は元々は丹波国造であった。 これらの神社にまつわる信仰上の話は私はよくわからないので置くとして、籠神社の祝家・海部氏は元々は丹波国造であった。
勘注系図の天香語山命の注文に、
| 天香語山。亦名は手栗彦命。亦名は高志神彦火明命。天上に於いて生ます神也。母は天道姫命亦名屋乎止女命、亦名高光日女命、亦名祖母命也。爾に天香語山命と天村雲命は父火明命に従い、丹波国凡海嶋へ天降座す。而して神議を以て国土を造り修んと欲し、百八十軍神を率い、当国之伊去奈子嶽に到る時、母道日女命と逢い、因て此地へ天降る其由を問う。母は答えて曰く、此の国土を造り堅めんと欲す、然と雖も、此の国は豊受大神の所所国也。故に大神を斎奉しなければ、則ち国は成り難也。故に神議を以て斎清地を定る。此大神を奉斎れば、則ち国成。故に祖命乃其弓矢を香語山命に授け曰く。此則ち是大神之意者。汝宜しく之を発ち。而其落に随い清地に行くべし。故に香語山命は其弓矢を取り、之を発つ。則ち其矢は当国加佐郡矢原山に到りて留まる。即時根生て枝葉は青々、故に其地を名づけて矢原と云う。(矢原訓屋布)。爾に香語山命が南東に到れば則ち荒水が有。故に其地神籬を建て、以て大神を遷し祭る。而して始めて墾田を定む。是に於て春秋に田を耕し、稲種を施し、恩頼は四方に遍く。即ち人民は豊なり。故に其地を名つけて田造と云う。爾に香語山命は然る后に、百八十軍神を率い退いて由良之水門に到る時に、父火明命に逢う。詔が有る。命は其神宝を奉斎し、以て国土造りを速修せんと欲す。其地を覓めて行き而て遂到当国余社郡久志備之浜に遂到る之時。御祖多岐津姫命とに逢う。因て此地に居ます其由を問う祖命は答えて曰く。斯地は国生の大神伊射奈岐命が天より天降り坐す地也。甚清地也。故に参降りて而して汝の来るを待てり。是に於いて、香語山命は地が速かに天に連き、天真名井之水に通うを知る。すなわち天津磐境に起て始て其神宝を其地に奉斎し、豊受大神を遷し祭る(分霊を矢原山に斎奉る)。是に於て則ち国成る。其時此地に霊泉出る。爾に天村雲命は天真名井之水を汲み、此泉に濯ぐ。其水は和らぎ以て御饌之料と為す。故に此泉を名づけて久志備之真名井と云也。今世に謂う比沼之真名井は訛也(真名井は亦宇介井と云う)。此時、磐境の傍に於て天吉葛が生る。天香語山命は其匏ゑ採り、真名井之清泉を汲み、神饌を調度し、厳かに祭りを奠る。故に匏宮と曰く(匏の訓は与佐)。亦久志浜宮也(此郡を匏を号くる所以は風土記に在り)。爾に香語山命は然る后に木国熊野に遷坐す。而て大屋津比売命を娶り高倉下を生む。道日女命は多岐津姫命と此地に留り、豊受大神に斎仕。 |
とあって、元々は海の彼方に居たが、大部隊で伊去奈子嶽の麓(丹波郡)に移り、勢力を培い丹波国造となった。やがて加佐郡の田造(田辺)へ、そこから由良川河口の由良の水門へ移り、さらに天橋立の久志備の浜に移ったという国造家の一派があった。
いつの時代の話をしているのかよく、というか、まったくわからないが、恐らくは中央国家の「宮津へ移って、丹後全般を見てくれないか」の内々の要請もあったのではなかろうかと思われる。
権力だけが移ったのではなく、人々も移ったのではなかろうか。伊去奈子嶽から矢原山は権力だであったかも知れないが、それ以降は実際に移動したのではなかろうか。移動すれば足跡が残る。民を率い、神社を移し、地名も移しながらの大移動であったと思われるのだが−−
フケイ浦は西舞鶴湾を九景浦(笛浦)と呼ぶのと同じ、フケイ浦の奥は枯木浦だが、これは東舞鶴湾を枯木浦と呼ぶのと同じ。舞鶴湾が阿蘇海にそっくり引っ越してきている。倉椅山、倉椅川、溝尻、傘松山、笶原は対岸の栗田半島に矢原がある。
吹飯神社もたぶん西舞鶴の真名井のあたりにあったのではなかろうか。根子宮(奈具社)は由良の式内社奈具神社を移した。
−−何の証拠もないが、そんな風にも見えてくる。
初期の丹後国府が加佐郡由良にあったのなら、その位置はあるいは奈具神社ではなかろうか。
田造にあったなら、「ウケイ神社」であっただろうか。
府中に移った初期は籠神社と同じ位置にあったのではなかろうか。
《交通》
国道178号線
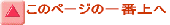
飯役社の主な歴史記録
『丹後旧事記』
飯役神社。府中溝尻村。祭神=飯役大明神。御饌都御神豊宇賀能売命又名豊賀志飯比売命。当社者豊宇賀能売(口編に羊)神比治之真名為通與佐宮御饗奉捧給神戸所之跡也。
吹飯の浦。與佐郡板列の庄府中の海なり豊宇賀能(口編に羊)の神比治の真奈井ケ原より通ひて與佐宮大神へ御饗を奉り給ひし跡なりとて此神を飯役大明神と称す。是所謂與佐宮神戸所也依て爰の海を宇気の浦と云なり。… |
『丹後与謝海名勝略記』
| 【飯役神社】溝尻の東の方田間にあり。案するに是御食津神也、延喜式丹後竹野郡奈具神社者豊宇気比売也云々移二祭大膳職一者號二御食津神一云々此社奈具神と同体なり。真井原程近き所なれは此社爰に有事むへなり。 |
『宮津市史』
中野遺跡
府中一帯では、国府に直接関連するとみられる事象のほとんどの起源が平安時代末をさかのぼるものではなかった。したがって、府中と呼ばれることが多かったこの時期以降の国府の所在は確認されたとしてもよいが、必ずしもそれ以前の国府の存在を示すものではない。しかし、中野遺跡で検出された遺物・遺構は奈良時代にさかのぼるものであり、注目に値する。
中野遺跡は旧府中村中野の大乗寺付近において図41のような調査で確認された(「中野遺跡第一次〜第四次発掘調査概要」『宮津市文化財調査報告』二・三・五・七)。礎石建物・掘立柱建物。井戸・列石などの遺構が検出されたほか、瓦・須恵器・土師器・黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器・輸入陶磁器などが出土した。瓦には平城宮系の軒九瓦と軒平瓦のセットが見られるほか、かなりの量の奈良時代の瓦片が出土するので、奈良時代に瓦葺きの建物が存在したことは推定し得る。
遺構の性格は不明であるが、墨書土器の中に「西寺」と記したものがあり、丹後国分尼寺に比定する考えもある。しかし、寺院跡として確認されたわけではなく、少なくとも瓦葺建物が存在し、平城宮系の瓦が含まれていることからすれば、官衙であった可能性は高い。とすれば、国府の施設群の一部であった可能性がある。
中野遺跡の一帯は小字廻り垣・教光神・クゴンドンなどであり、他の国の国府所在地に見られるような官衙・施設を示す小字地名を検出することはできない。図42は、国分寺跡付近から籠神社にかけての一帯の小字地名を示したものであるが、やはり国府の施設に直接かかわるとみられる小字地名は検出されない。この範囲で目につくのは、国分寺跡の前面付近から東北東へ進み、籠神社に至る道であり、この道は古くからの主要道であったことを示すように、小字地名の境界ないし軸となっていることである。国分付近では、この道を「縄手」と称していたようであり、平安京近郊の久我畷や大縄手・小縄手といった中世史料に見られる道路名を連想させる。
中野遺跡はこの道路の山麓側に立地していることにも留意しておきたい。山麓には小規模な扇状地が形成されており、中野遺跡はその上に立地している。図41に示されているように、標高は約一○〜二○メートル程度の部分である。 |
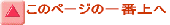
関連情報




|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|