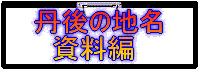 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海臨寺(かいりんじ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
《海臨寺の概要》 海臨寺は舞鶴市の東北・若狭湾に面した田井にある。 山号瑞光山、臨済宗東福寺派、本尊釈迦如来。 寺伝によれば、古くは「海林寺」と書き、水ケ浦の背後の山腹台地(通称: 最初は真言宗、南北朝期に禅宗に改宗、その後、室町時代から江戸時代にかけて末寺二十数ヵ寺を数えた。 江戸初期、現寺名に改称、別所から現在地に移転した。(移転期は江戸中期ともいう) 高浜町日引の正楽寺も水ケ浦別所にあったというが、このあたりの仏教の発祥地なのだろうか。 『京都府の地名』は、「天和二年(一六八二)の丹後国寺社帳には「東福寺派田井村 海臨寺(割注・末二十一寺有)」とみえ、内浦湾に臨む若狭の村、大浦半島・河辺谷・朝来谷の禅宗寺院のほとんどは当寺の末寺であった。 江戸後期の旧語集は「至徳三丙寅年建立」とし、開基曇翁源仙、末寺一二ヵ寺と記す。境内を含めて寺領七・一二六石があった。 江戸末期、当寺から実州・実堂などの名僧が出、本山東福寺(現京都市東山区)の管長・管長代理になっている。 境内に二群五基の宝筐印塔があり、「田井大墓」と称される。一群(三基)は花崗岩製で、一は無銘だが鎌倉後期と推定される舞鶴市内で最大のもの。ほかの二基は各々永禄五年(一五六二)、元和四年(一六一八)の年紀が台座にある。二群(二基)は凝灰岩製で、一に「永禄五年壬戌十月吉日」の銘があり、一に「元亀□□」の年紀がみえる。」としている。 |
資料編の索引
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 本寺京東福寺瑞光山海臨寺禅。 開山曇翁和尚、至徳三丙寅年より元禄十丁亥まで三百拾壱年になる。 本尊釈迦、安阿弥作(快慶作)中門惣門あり。広峯山西方寺は海臨寺隠居所なり。 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 《丹哥府志》 〈 《地名辞書》 〈 補〔田井〕加佐郡○地誌提要、海臨寺は禅宗にして僧曇翁の開基、元中二年創建。○今、東大浦村と曰ふ。 《加佐郡誌》 〈 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海臨寺とその大墓 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《田井校区のすがた》より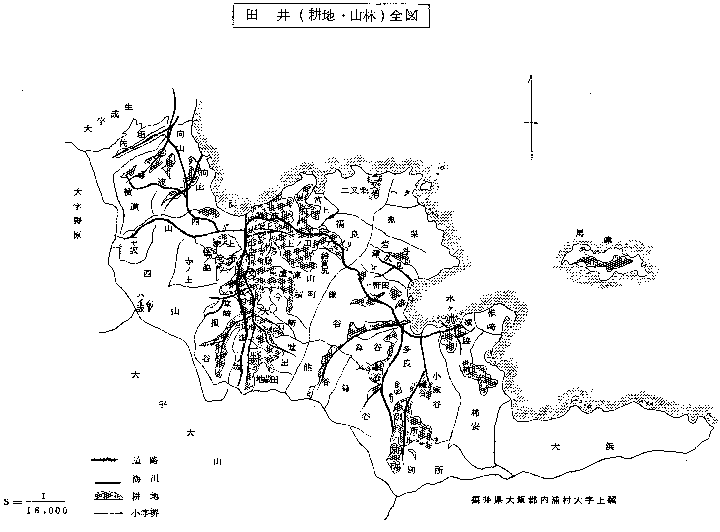 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2007 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||