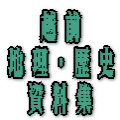 |
敦賀郡(越前国)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦賀郡の概要《敦賀郡の概要》 敦賀郡は古代~近代の郡名で、越前国に属している。 越前国六郡(敦賀・丹生・今立・足羽・大野・坂井)の一つで、越前国の南西端である。郡域のだいたいは今の敦賀市に当たり、若狭湾の東端、京畿からは北陸方面への入り口に当たる。中心部は今の敦賀市で、敦賀湾をU字形に囲み、湾に注ぐ笙ノ川・木ノ芽川などが扇状地や沖積平野を形成している。 《古代の敦賀郡》 (地名説話) 「日本書紀」垂仁天皇2年の 「古事記」仲哀天皇段には、 伊奢沙和気大神(のちの気比大神)が禊のため当地を訪れた皇太子時代の応神天皇と名を交換した際に、 亦の入鹿魚の鼻の血 血浦とか、少し北に 《角鹿国の時代》 郡(評)という、律令期の地方行政区画が施工されたのは、大宝令(701)からではなかろうかと言われる。それ以前は角鹿国であった。一応は独立国だったのだろうが、何しろ小さい、一郡の広さしかない上に、平野部も少ない、独立は力不足で、時代が下れば下るほど中央政権に従属していくこととなったのであろうし、海を向いた国なので、岡には力が及ばないのか、古墳も大きなものはわずかである。 『敦賀郡誌』 角鹿國造及角鹿海直 成務天皇の時、 〔新撰姓氏録考證〕五、廬原公の條 この武彦命は、高霊天皇の皇子大吉備津日子命、次に若日子建吉備津日子命と(古事記に)ある、この若日子建吉備津日子命は、書紀に稚武彦命とありて、日本武尊の扈從仕奉りて東征せる古備建日子命の父なる事、姓氏録眞髪部氏の條に見えたるがに如し、景行紀(日本武の東征より還幸の條下)に日本武尊曰、蝦夷凶首、咸伏二其辜一、唯信濃國・越國、頗未レ從レ化、云々、於是分レ道、遣二吉備武彦於越國一、令レ監二察其地形嶮易及人民順不一、則日本武尊進入二信濃一、云々得レ出二美濃一、吉備武彦自レ越出而遇レ之、とみえたるもので、北陸地方は吉備武彦の征け和せし事を知るべし、さて其功ありし人の子建功狹日命を國造に封されしものなり、氏人は續紀廿六に敦賀直島麿、類聚國史(天長五年)に越前國釆女角鹿直福貴子、三代貫録十四に角鹿直眞福子、また東大寺正倉院文書なる越前國天平二年正税帳に敦賀郡々司少領從八位上勳十二等角鹿直綱手などあり 景行紀によれば、日本武尊の東国平定には吉備武彦も従っていて、 吉備武彦を越國に遣して、其の地形の嶮易及び人民の順不を監察しむ。 と記されている。 『新撰姓氏録抄』 右京皇別下。 笠朝臣同祖。稚武彦命之後也。孫吉備建彦命。景行天皇御世。被レ遣二東方一。伐二毛人及凶鬼神一。到二于阿倍廬原国一。復命之日以二廬原国一給レ之。 廬原国は駿河国西部にあった国(のちの駿河国庵原郡) 『新撰姓氏録抄』 右京皇別下。 『先代旧事記』 角鹿國造 志賀高穴穗朝の御代に吉備臣の祖・若武彦命の孫・建功狹日命を国造に定賜ふ。 『古事記』 孝霊天皇。 此の天皇の御子等、并せて八柱なり。[男王五、女王三]。…。次に日子刺肩別命は、[高志の利波臣、豊國の國前臣、五百原君、角鹿の海直の祖なり] 越国の平定は吉備氏が当たったとされ、これが角鹿国造家の祖だとする。角鹿海直と吉備臣は、同族関係の伝承がある。 また この豪族は海上交通・漁業に従事する人々の統率者で、向出山古墳群の被葬者とされ、当地の気比神の祭祀権を握り、7世紀の後半頃には、大和政権の支配下に入ったと見られている。 この角鹿国を母体として越前国敦賀郡となったのは、8世紀の最初頃であった。 その後の記録には、 「日本書紀」持統天皇6年(692) 九月の癸丑(21日)に、越前國司、 692年といえば、角鹿国だったか、角鹿郡だったか、厳密には不明。角鹿国造氏は敦賀郡司となったと見られる。 天平3年(731)の越前国大税帳(正倉院文書)に、前年の当郡の正税は穀にして6,295斛余で、ほかに頴稲1万530束余・糒295斛余など、これらが正倉15・借倉1に収められた。他郡の倉庫数は丹生郡51 ・ 大野郡59・坂井郡64と見えて、当郡の生産力の低さがうかがわれる。大税帳には敦賀郡少領角鹿直綱手の名が見え、角鹿国造の系譜を引く者と思われる、という。 天平5年閏3月6日の越前国郡稲帳には郡司として綱手のほか、主帳螺江比良夫の名が記される。郡司角鹿氏の一族はその後も「続日本紀」天平神護元年(765)5月丁酉条に敦賀直島麻呂、「類聚国史」采女天長5年(824)閏3月庚子条に角鹿直福貴子、「三代実録」貞観9年(867)3月10日条に鹿角直真福子などの名が知られ、9世紀後半まで「角鹿」を名乗っている。 「和名抄」には、伊部・鹿蒜・与祥・津守・従者・神戸の6郷を載せる。鎌倉期に丹生部の海岸部が気比社領に含まれたことから、8~10世紀の敦賀郡の郡域が、のちの南条郡のみならず丹生郡の一部をも含んでいた。後世の敦賀郡域は、丹生北郡・南仲条(南条)郡の成立に伴って定まり、その時期は越前で「和名抄」以後の郡名として最初に「東条郡」(今立郡を示す)が見える保延5年(1139)以前のこととみられている。 式内社は越前6郡で最も多い43座を数え、うち気比社の7座が名神大座とされる。鎮座地が明らかにのちの南条郡に属する加比留神社・鹿蒜神社・鹿蒜田口神社(ともに現今庄町)のほか、伊部磐座神社や織田神社、横山神社は越前町と見られていて、かつての敦賀郡域が南条部から丹生郡にまで及んでいたことをうかがわせる。 また、白城神社(白木)・信露貴彦神社(沓見)などの朝鮮半島とのつながりの深さを示す神社も見える。 郡内には松原・鹿蒜の両駅があり、松原駅は松島町・松原町の付近、鹿蒜駅は今庄町南今庄付近と考えられている。 松原駅と近江国鞆結駅(滋賀県高島市マキノ町石庭)を結ぶ経路は、黒河川沿いに進んで白谷に越える最短コースか、それとも愛発関の比定地の疋田からいわゆる七里半越(西近江路)をたどる経路のいずれか確定されていない。 松原駅と鹿蒜駅の間は、木ノ芽川沿いに北上して木ノ芽峠を越える経路か、海上を五幡まで進んでから葉原に入って木ノ芽峠を越えたり、比田あたりに上陸して山中峠を越える経路なども利用されたと考えられている。 《中世の敦賀郡》 郡内の荘園・国衙領は気比荘・野坂荘・葉原保・莇野保などがあった、いずれも気比社が領家として関わり、本家は鎌倉期には摂関家・皇室、南北朝期から青蓮院門跡が領した。 気比社はこのほかに敦賀湾岸や丹生郡沿岸部に対する支配権を持っていた。鎌倉期には大縄間浦・沓浦・手浦・大谷浦・干飯浦・玉河浦・蒲生浦の諸浦から海産物などを貢納させていた。室町・戦国期には前記の浦々のほか、五幡・江良・比田などの敦賀湾東岸の浦や山泉などの敦賀平野部の村も気比社の社家の所領となっていて、気比社は中世を通じて郡内に根強い影響力を持ち続けた。 敦賀郡の在地武士はあまり見られず、気比社社家衆(河端・石塚・平松・島・宮内・長屋・石蔵・比田など)が郡内最大の武士団で、南北朝内乱時に新田義貞らを迎えて足利軍と戦ったり、織田信長が越前に攻め入った元亀元年、朝倉氏方に属して信長軍と戦ったりした。 在地武士は、南北朝期・室町期の野坂荘櫛川郷地頭で西福寺の開創にあたって寺地を寄進した山内氏、疋田を名字の地とし戦国期の朝倉氏家臣として見える疋壇氏などが知られる。 鎌倉新仏教諸宗の浸透は鎌倉中期頃から始まり、正元元年(1259)、気比神宮寺内釈迦寺が浄土宗善妙寺に改められ、永仁2年(1294)に気比神宮寺と関わりのある覚円が日蓮宗妙顕寺を開き、正安3年(1301)敦賀に来た他阿真教によって敦賀津の西方寺が天台宗から、井川の新善光寺が真言宗からそれぞれ時宗に改宗するなど、旧仏教系寺院の転宗がみられた。 南北朝期以後も浄土宗の西福寺、日蓮宗の本妙寺、時宗の来迎寺、曹洞宗の永建寺・永厳寺などの有力寺院が相次いで開かれた。慶長5年(1600)以前に成立していたことが明らかな郡内の寺院は、浄土宗14 ・浄土真宗13・曹洞宗13 ・ 日蓮宗7・時宗3・天台宗3・真言宗1の計54か寺、うち22か寺は敦賀とその隣接地(のちの今浜村・泉村)にあった。 室町期の越前守護・斯波氏は敦賀に郡代を置いた、いずれも守護代甲斐氏の一族が務めた。戦国大名・朝倉氏も一族を敦賀郡司として配置し、景冬・教景・景紀・景垣の歴代が任じられた、景冬の子景豊が惣領家に背いた文亀3年(1503)頃、景恒のあと織田信長との対立が強まった元亀元年(1570)頃以降は、郡司が廃され惣領家の直接支配とされた。 敦賀郡が室町期から戦国期を通じて常に1個の行政単位とされてきたのは、当郡が政治的・経済的・軍事的要地であったからである。特に京畿と北陸道諸国を結ぶ敦賀津は、中世を通じて日本海側屈指の要港としての地位を保ち続けた。戦国期には独占的海運業者仲間として川舟座と河野屋座があり、朝倉氏や織豊政権下の歴代敦賀領主からその特権を保護された。 天正元年(1573)朝倉氏を倒し、同3年一向一揆を破った信長は、武藤舜秀を敦賀郡の領主とした。その後同7年舜秀の死後は武藤康秀(舜秀の子)、同10年の本能寺の変後は蜂屋頼隆、同17年の頼隆の死後は大谷吉継と変わった。 室町期の郡代、戦国期の郡司は金ケ崎城を拠城としたと思われるが、武藤舜秀は信長が朝倉景恒・気比社家衆らの拠る金ケ崎城・天筒山城を攻めた際に本陣とした花城山城を敦賀支配の拠点としたと伝える。蜂屋頼隆は笙ノ川西岸に新たに敦賀城を築き、大谷吉継の代の慶長年間頃には3層の天守を持つ城ができていた。ほぼ太閤検地(慶長3年・1598)の結果を示す慶長国絵図によれば、敦賀郡の総石高は2万1,327石余で、今立郡の一部となる今南東郡を除けば、越前で最低であった。 《近世の敦賀郡》 慶長5年(1600)結城秀康が入封して福井藩領となり、秀康は重臣清水孝正を1万1,020石で敦賀に配置。松平忠直が改易となり、寛永元年(1624)弟忠昌の福井入封に際し、全郡福井藩から割かれ幕府領になったあと、同年冬京極忠高に与えられ小浜藩領となり、寛永11年(1634)酒井氏が入封し、廃藩置県に至った。 「正保郷帳」では泉・津内・舞崎・余座・大倉・井河・谷口・樫曲(深山寺)・越坂・田尻・葉原・新保・獺ケ河内・池河内・長沢・道口・鳩原・小河・小河内・市橋・疋田・麻生口・奥麻生・駄口・山中・追分・奥野・曽々木・新道・刀禰(杉箸)・高野・中・谷・吉河・坂下・古田苅・堂・山泉・櫛林・州流・御名・公文名・山(尼谷)・長谷・野坂・金山(関)・莇生野・沓見・原・木崎・櫛川・今浜・新田・徳市・鋳物師・野上・一本松・和久野・二・名子・縄間・沓・手・色浜・浦底・立石・白木・菅谷・本比田・大比田・横浜・杉津・阿曽・挙野・五幡・江良・赤崎・田結・松中の79村2万1,368石余。このうち気比大神宮社領100石、常宮大権現社領33石余、天神社領5石、西福寺領33石余、幸若領100石があった。 寛文8年(1668)、酒井忠国の安房勝山(かちやま)(加知山)藩1万石が成立し、当郡のうち野坂村など10村5,000石(実際は5,482石余)がその所領となる。野坂村に代官所を設けたので野坂領ともいう。 天和2年(1682)、酒井忠稠の鞠山(まるやま)藩1万石と酒井忠垠の井川領が成立。鞠山藩は敦賀郡に5,000石,井川領は代官所の置かれた井川村のほか新保・葉原・越坂・谷口・中・吉河・古田刈・鳩原・鋳物師および今浜村734石余のうち644石余の3,000石であった。井川の代官所には代官・手代が置かれたが、天保6年(1835)廃止され小浜藩が支配した。 寛文3年(1663)の戸数5,993 (うち高持2,460・無高1,130)・人口3万4,980 (うち男1万7,329 ・女1万7,651)。鞠山藩領は、天和3年(1683)の戸数799 (高持637 ・ 無高162)・人口4,197 (男1,941 ・ 女2,163 ・ 出家など93)、享保14年(1729)頃に、小浜藩領1,436戸・6,963人、鞠山藩領1,039戸・5,573人、井川領485戸・2445人、勝山藩領は宝暦10年(1760)、人口2,954 (男1,386・女1,497 ・ 出家など71)であった。 「元禄郷帳」86村2万1,528石余、「天保郷帳」86村2万2,811石余、「旧高旧領」64村18浦2万2,806石余。村高を「正保郷帳」でみると, 1,000石以上4村、 500石以上8村、100石以上41村、 100石未満26村うち15村が50石未満であった。 《近代の敦賀郡》 明治3年4月、井川領と幸若領が福井藩の預り所にされたあと同年12月本保県となり、同4年7月に旧藩領を継承して小浜県と加知山県が成立した、同年11月3県が廃されて敦賀県が置かれた。明治14年福井県に所属。明治7年「改正敦賀県区分表」では第5大区とされ、小区23・組数55 ・ 町数27 ・ 村数58・戸数6,362、会所は敦賀であった。同11年郡区町村編制法により敦賀に郡役所が置かれた、この頃29町78村、 6,361戸・2万8,325人、田畑宅地3,017町1反余。同22年市制町村制施行により敦賀町と東郷・中郷・松原・東浦・愛発・粟野の1町6村となった、このときの戸数5, 776。戸数・人口は、明治41年6,447 ・ 3万6,371、大正9年8,226 ・ 3万8,048。昭和12年松原村を吸収して敦賀町が市制施行、同30年残る5村(東浦村・東郷村・粟野村・中郷村・愛発村)が敦賀市に編入されて郡名は消滅した。 関連情報 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||