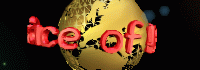
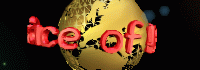
|
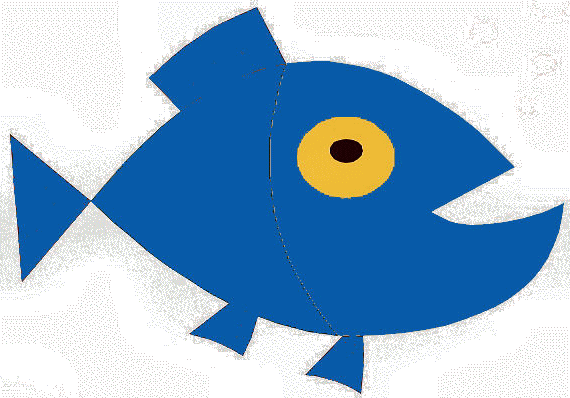 〝海の祇園祭〝 7年ぶりの船屋台巡航。
〝海の祇園祭〝 7年ぶりの船屋台巡航。
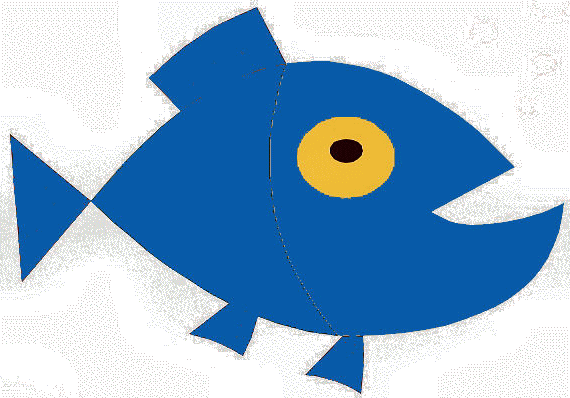 説明も何も不要な有名な伊根祭、2012年は船屋台が1艘、7年ぶりの巡航があった。次はいつ巡航されるものかは、その年のブリ漁の出来次第で不明である、ナニと言っても手間暇かかるし、ゼニもかかるものだから、あると言う時には、行って見ないわけにはいかない。7年先ならまだよいだろうが、それ以上先になればその時はもう生きておれるかどうかもわからないような話でなってしまう。
説明も何も不要な有名な伊根祭、2012年は船屋台が1艘、7年ぶりの巡航があった。次はいつ巡航されるものかは、その年のブリ漁の出来次第で不明である、ナニと言っても手間暇かかるし、ゼニもかかるものだから、あると言う時には、行って見ないわけにはいかない。7年先ならまだよいだろうが、それ以上先になればその時はもう生きておれるかどうかもわからないような話でなってしまう。
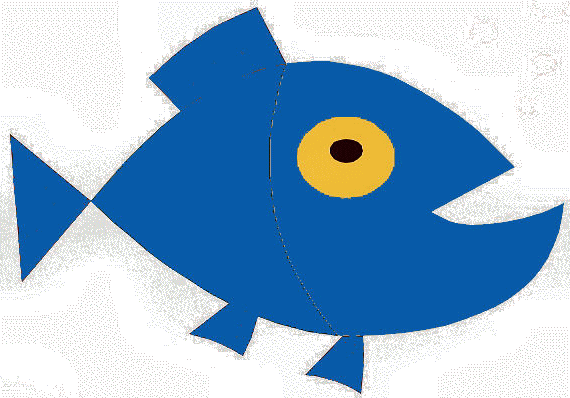 7艘のトモブトと呼ばれる小船を並べて、その上に屋台が組み立てられている。このトモブトはプラチック製のようで、漁に使われないこれ専用のもののようである。釘などは一切使わずに組まれている。
7艘のトモブトと呼ばれる小船を並べて、その上に屋台が組み立てられている。このトモブトはプラチック製のようで、漁に使われないこれ専用のもののようである。釘などは一切使わずに組まれている。
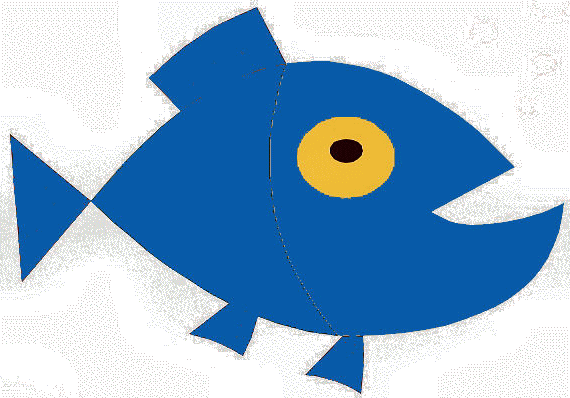 私はまったく不案内者で、彼女はプロの演歌歌手だそう。3名の歌手が出演。豪華な大きな屋根があるので、ステージはカゲになり暗くなる、照明はないので写真は写しにくい、白い紙でも周囲にあればいいが、これまでは船屋台は歌舞伎が演じられてきた、プロの歌舞伎であった。
私はまったく不案内者で、彼女はプロの演歌歌手だそう。3名の歌手が出演。豪華な大きな屋根があるので、ステージはカゲになり暗くなる、照明はないので写真は写しにくい、白い紙でも周囲にあればいいが、これまでは船屋台は歌舞伎が演じられてきた、プロの歌舞伎であった。
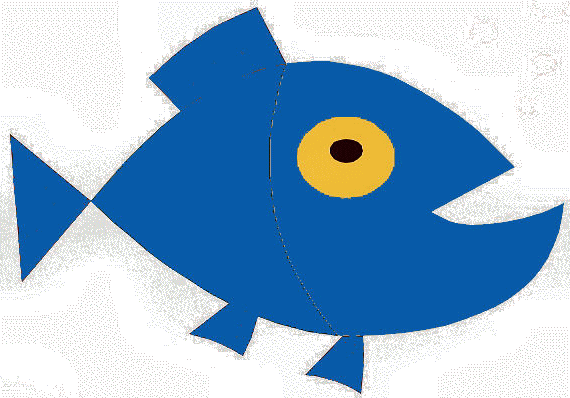 この日は知事も見えられていた。地元の人たちよりもカメラマンの方がはるかに多いよう。おとなしい紳士的な遠慮がちのマナーあるカメラマン・カメラウーマンがほとんどで、前や後は空いていて、空けてくれているのか、こんなに多くとも意外と写しやすい。
この日は知事も見えられていた。地元の人たちよりもカメラマンの方がはるかに多いよう。おとなしい紳士的な遠慮がちのマナーあるカメラマン・カメラウーマンがほとんどで、前や後は空いていて、空けてくれているのか、こんなに多くとも意外と写しやすい。
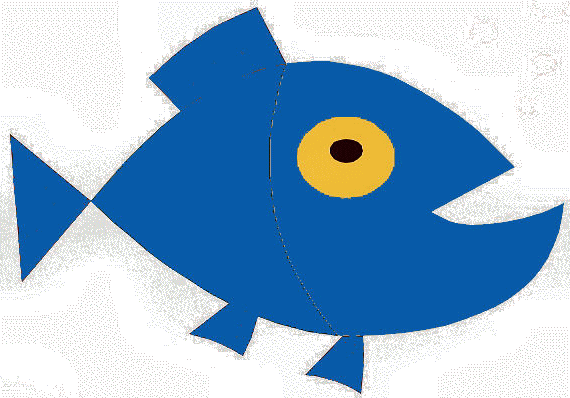 今回は宇良神社に伝わる三番叟が演じられた。最も格調高い「翁の舞」。3月17日の延年祭に奉納されるものだが、延年の舞いと金属とはなにか関係があるのではなかろうか、伊根湾で演じられるのは、偶然的とも言えるが、それを超えた必然があるようで、私は一人何かゾクゾクしてきた。
今回は宇良神社に伝わる三番叟が演じられた。最も格調高い「翁の舞」。3月17日の延年祭に奉納されるものだが、延年の舞いと金属とはなにか関係があるのではなかろうか、伊根湾で演じられるのは、偶然的とも言えるが、それを超えた必然があるようで、私は一人何かゾクゾクしてきた。
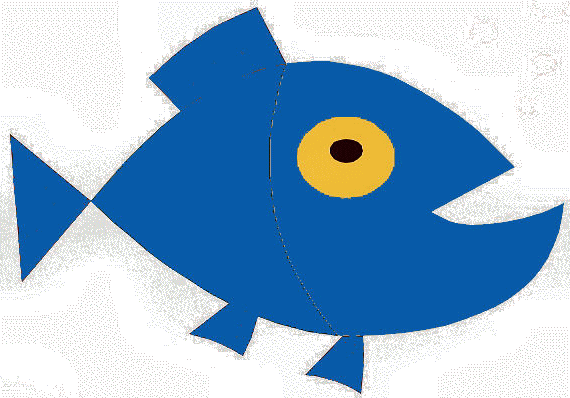 知らぬ人もなかろうが、一応書いておけば、〝海の祇園祭〝と呼ばれる「伊根祭」は高梨(亀島)の八坂神社とその隣にある八幡神社の祭礼である。八坂神社は伊根浦の総氏神で、亀島と平田から芸能が奉納される。祭礼の本祭は7月28日とされている。ここに限らず伊根町あたりの祭礼は豪華丁寧で、昔から伝わるとおりに宵宮・本祭・地下祭などとセットで催される場合が多い、二日から三日にわたる日程になる。 知らぬ人もなかろうが、一応書いておけば、〝海の祇園祭〝と呼ばれる「伊根祭」は高梨(亀島)の八坂神社とその隣にある八幡神社の祭礼である。八坂神社は伊根浦の総氏神で、亀島と平田から芸能が奉納される。祭礼の本祭は7月28日とされている。ここに限らず伊根町あたりの祭礼は豪華丁寧で、昔から伝わるとおりに宵宮・本祭・地下祭などとセットで催される場合が多い、二日から三日にわたる日程になる。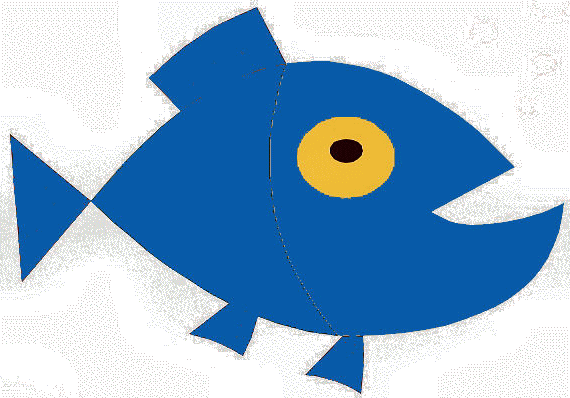 平田は海上渡御でなく、傘鉾と猩々緋の神幟を先頭に雅楽を奏しながら歩いてやってくる、稚児は最後。平田からは「稚児舞い」が奉納される。 平田は海上渡御でなく、傘鉾と猩々緋の神幟を先頭に雅楽を奏しながら歩いてやってくる、稚児は最後。平田からは「稚児舞い」が奉納される。  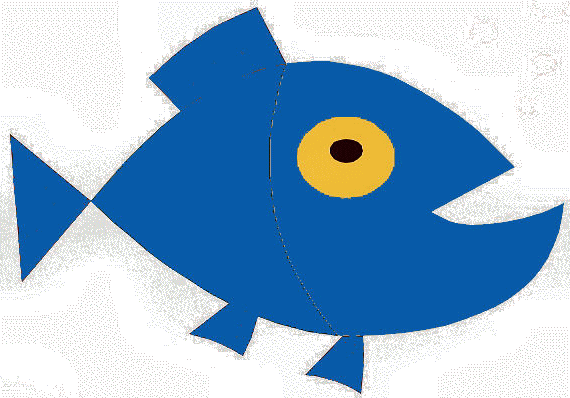 平田の「稚児舞い」は、笙3・龍笛3・篳篥3・太鼓1の雅楽器の奏する楽によって三人の稚児(男1・女2)が舞う一種の神楽舞で、近代になってはじめられたものという。急斜面にある八坂神社境内は広くない、だいたい12:00くらいから神事奉納がはじまる。 平田の「稚児舞い」は、笙3・龍笛3・篳篥3・太鼓1の雅楽器の奏する楽によって三人の稚児(男1・女2)が舞う一種の神楽舞で、近代になってはじめられたものという。急斜面にある八坂神社境内は広くない、だいたい12:00くらいから神事奉納がはじまる。しかしここも暑い、一年で一番暑い時期になるのだからそれも仕方もないことだが、私などはただ立ってるだけでもクラクラとめまいがきて、意識が薄れ何か気分が悪くなってくるものすごい高温の中である、ここで長時間緊張迫られる祭事人などには決死的つとめであろうか、周囲の付き添い人たちがウチワや扇子で風を送る。(そのためもあってか救急車が来た、動画を見てもらうとその音が聞こえる、倒れて石段で顔面強打し出血したという、このあたりは病院がない、診療所があるが、外科はあったかな、ここは町中ではありません、町中でも儲からないとかでないところは多いのだから、お互い十分に気をつけましょう( 。-_-。)  正面が八坂神社本殿。  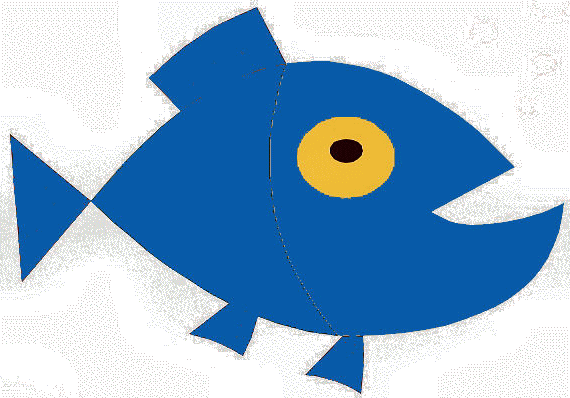 13:00。「神楽船」を先頭に「祭礼船」、さらに「船屋台」と「化粧船」。八坂神社から見ると対岸の耳鼻あたりから渡御が始まる。〝海の祇園祭〝と呼ばれるのはこれである、この後に3艘の「船屋台」が続けば、海上を進み行く祇園祭の山車群を彷彿させる。 13:00。「神楽船」を先頭に「祭礼船」、さらに「船屋台」と「化粧船」。八坂神社から見ると対岸の耳鼻あたりから渡御が始まる。〝海の祇園祭〝と呼ばれるのはこれである、この後に3艘の「船屋台」が続けば、海上を進み行く祇園祭の山車群を彷彿させる。 30分ばかりで、八坂神社下の「宮の浜」に到着する。長い艪をこいでやってくる。  手前の2艘束ねた船が「祭礼船」で、後に「神楽船」が見える。  「宮の浜」に到着。  その先に「神楽船」が着く。「船屋台」はうしろがわに着く。   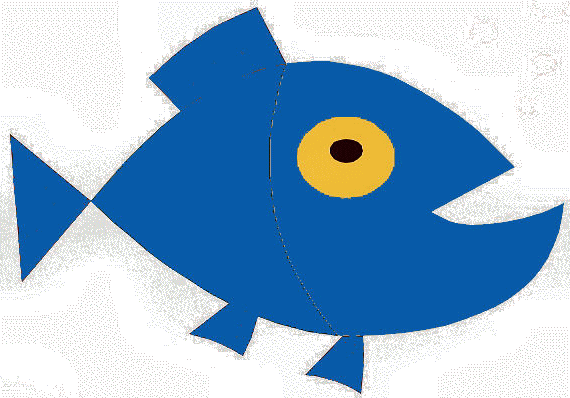 ものすごい数のカメラマンが押し寄せてくる。なんとか写せるような場所をキープしているのは、少々アツカマシイ連中なのか、見れば、ぜんぜん写せそうもない所にもあきらめ顔したカメラマンが一杯一杯あふれている、カメラ2台をぶら下げたのが、まだまだあとからあとからどんどんと押し寄せている。 ものすごい数のカメラマンが押し寄せてくる。なんとか写せるような場所をキープしているのは、少々アツカマシイ連中なのか、見れば、ぜんぜん写せそうもない所にもあきらめ顔したカメラマンが一杯一杯あふれている、カメラ2台をぶら下げたのが、まだまだあとからあとからどんどんと押し寄せている。最初来てみれば誰もいないほどに少なく、アレこんなんなん、これなら写せるわい、と思っていたが、とんでもない思い違いであった。 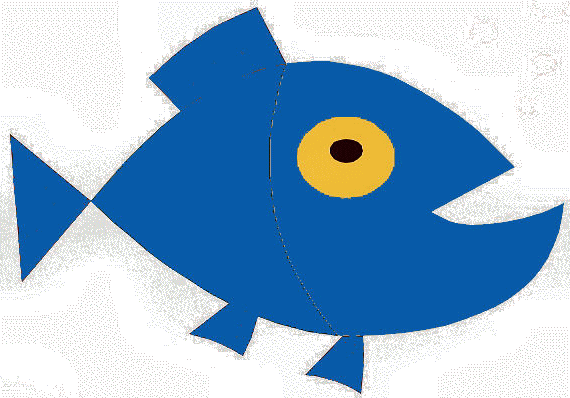 平田が退去したあと宮入りをする。先頭にトッケツが立ち、神楽・シンボチ・棒振り・太刀振りの順ににぎやかに宮へ練込み、まず太刀振り、ついで神楽を奉納し、シンボチ・棒振りの所作があり太刀振りは三人ずつ二列になって振り奉納する。 平田が退去したあと宮入りをする。先頭にトッケツが立ち、神楽・シンボチ・棒振り・太刀振りの順ににぎやかに宮へ練込み、まず太刀振り、ついで神楽を奉納し、シンボチ・棒振りの所作があり太刀振りは三人ずつ二列になって振り奉納する。これも写そうと、当初はしていたのだが、もうあきらめた。人の山に埋まり呑まれていて、満足には写せまい、これだけいたらもうムリだ。来年また来てみよう、作戦を変えればあるいは写せるかも知れない 。゜(゜´Д`゜)゜。 『伊根町誌』 〈 祭神 建速須佐之男命 例祭 七月二十七・八日 古くは陰暦六月二十七・八日であったが、大正十二年(一九二三)から陽暦七月二十七・八日となり、昭和三十四年(一九五九)に伊根町の祭日は八月三日に統一されたが、昭和四十八年(一九七三)にふたたび七月二十七・八日となり現在に至っている。 沿革 創建年代は執権北条泰時の時代の貞永元年(一二三二)八月とされているが、江戸時代の初期に八幡神社とともに、平田・亀島地区住民の氏神として建立されたと推定される。日吉神社(現宮津市字岩ヶ鼻小字宮山)の天文十八年(一五四九)十月の棟札に、「奉造立伊禰山王社御遷宮時百姓中官途之人数」として日出・平田・亀島の代表者の名が記録され、当時伊禰庄八か村(日ヶ谷村・外垣村・岩ヶ鼻村・大島村・日出村・高梨村・平田村・大原村)の氏神は「一宮山王社」(日吉神社)であり、江戸初期に日出・高梨・平田・大原の四か村は分離し、それぞれ各村内に「牛頭天王」を勧請し、「祇園牛頭天王社」と称された。その後明治元年に「神仏分離令」により「八坂神社」と改称し現在に至っている。江戸時代に別当寺は正法寺である。 現在の本殿は安永五年(一七七六)十一月十二日に再建され、社殿の形式は槍皮葺の流造で斗?の木割が太く、古めかしい手法がみられるが、再建にあたって江戸初期の前身建物を模して再建されたものと思われる。… |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||