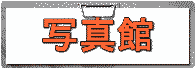
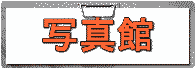
ようこそ、写真館へ No.40
水中綱引き'13
|

 〈 水中網引きの由来には、大蛇説や東西競合説などがあるが記録によれば、時の小浜藩主酒井忠勝が村の願い出により、日向湖を天然の舟溜りにしようと寛永12年(1635年)に若狭湾と日向湖を結ぶ水路を開削し運河を造った。この運河完成とその後の豊漁を祝って、これ以後日向運河で水中網引きが行われるようになった。毎年1月15月には、宇波西神社で海上安全と豊漁を祈願した村人たちが卯詣りから帰り、長床で伊勢音頭を唄い終えると若者らが威勢良く飛び出し、日向橋の欄干から掛け声と共に、次々と海中へ飛び込み寒風吹き荒れ身を切るような冷たさの中で網がきれるまで引き合う行事である。 厳密に言えば「綱」か「縄」かも問題になりそう。HPなどのぞいてみるとも「綱」とも「縄」とも書かれている。だいたいはワラでなってあるものはナワではなかろうか。ナワトビとかシメナワとかはワラ製でなかろうか。ナワはクチナワの言葉があるように蛇を連想するもので古い神事に関わりある物ではなかろうか、などと想像して、これは「水中ナワキリ神事」だと考えたのである。三方五湖といえば縄文文化花開いた地だから、この行事もあるいは1万年の歴史があるかも知れない。 この日は日向以外でも「綱引き」行事などが行われる所は多い。敦賀市西町の綱引きもこの日ではなかったろうか。 神意により勝った方に福がもたらされるという。以前はこうした占い勝負の結果次第で米相場すら上下したという。そんな非科学的な…、と思うのは、現代人の科学信仰に基づく話であって、現代人の科学とやらで自然のすべてがわかっているわけでも未来予想ができるわけでもない、伝統の方法で占われた神意とあらば、マーケットとすれば、頼りない世襲政治屋ども政府の経済政策とやらよりも、よほどに確かに見えるのかも知れない… ↓開催地の地図 場所はここ↑、「三方五湖レインボーライン」の東側入口を少し先へ行った集落で、広い駐車場があり、車で来られても十分にスペースがある。 この運河で行われる「水中綱引き」は、国選択の無形民俗文化財に指定されているすごいもの。その由来は、一つには、昔々この運河で災害による土砂の取り除き作業中に大蛇が出てきて運河を塞いだ、その大蛇を追い払うために、大蛇よりも長い大きな綱を作り運河に張ったところ、大蛇が自分よりも大きな蛇だと思い違をして尾を巻いて退散したという伝説にちなむ。 もう一つは、寛永12(1635)年に日向の浜が侵食されて舟を揚げるところがなくなったため、代わりに日向湖を舟だまりにしようと、時の小浜藩初代藩主酒井忠勝に陳情し、若狭湾と日向湖を結ぶ水路を開削してもらった。その結果、湖が天然の良港となり舟や村を護り、大漁が続いた。水中綱引きは、酒井忠勝による水路完成とその後の豊漁を祝ってはじめられたものとも言われる。しかし確証はない。 綱引きが行われる日向川は「日向断層」上に出来たものだろうと思われる。少しのち寛文2(1662)年には「近江・若狭地震(寛文地震)」が発生して、この断層の東側が3〜5メートルばかり隆起したといわれる。日向断層は日向川からほぼ南北方向に伸びていて日向湖の真ん中を通り嵯峨隧道を通り水月湖の真ん中を通って菅湖に伸びている。さらに花折断層、さらに京都市内へと続く、この地方としては最大級の地震は4時間もゆれたといわれるが、これによって三方五湖全体が西へ傾き、菅湖と久々子湖をつないでいた気山川は干上り、一方西岸の田井七村と海山は水中に没して里人が山野に彷徨した、と記されていて、浦見川が作られたのは三方五湖東側が隆起したために気山川が干上り西側の排水ができなくなったためである。綱引きはあるいはこうした地震おさめの意味もあったかも…  ↓太鼓橋(日向橋)、下を流れるのが運河(日向川)、この橋の上から飛び込む。右手(南側)に広がるのが日向湖。   ↑飛び込む者の目の高さから見た運河、コワーッ、先に張り渡された縄が見える。  ↑ この日の早朝から氏神の稲荷神社の長床で、太さ30cm、長さ40mばかりの綱が約3時間かけてない上げられる、午前中には運河に張り渡され、両岸に固く結びつけらる。大漁旗も飾られる。運河はけっこう潮の流れや変化があるのか、縄の姿がよく変わる。  運河にかかる日向橋から飛び込む、10メートルばかりあるのか、1秒で水面に達する。だいたいは二人一組で次々に続く。         1秒間のできごと。パシャン・パシャン・パシャンの連写速度のカメラではキツイか、ガガガガガガと連写できるカメラがよろしいかも。      一月の海へ飛び込めば、トシヨリはまちがいなく心肺停止だ。トシヨリはトシヨリ。トシヨリが冷たい海水に勝てたりはしない。しかし見ればかなり年配のような人も混じっている。若者が少ないためだろうかのぉ。 水温がいくらなのかわからないが、この日は「大寒」で、気温は5℃ほどか、海の方からの北風が強くて寒い。  ↑縄の方へ泳いでいく。30数人ほどのよう。  東西に分かれて、スタンバイ完了。勝った方に福がもたらされる。  しかし引きちぎれるわけがなさそうである。足がかりのない水に浮かぶ者が引っ張ってみても縄に力などかかるわけがない。岸辺の足が着く所にいる数名の力だけてしか引っ張れない。なってよってある縄をほどきワラの一本一本にしてから引きちぎるか。あるいは最後の手段は噛み切るのだそうで、ガブッと噛みついて、ワラを噛み切っていく。それくらいの根性で1万年を生きてきたのだろうか。 しかしこんな太い綱では、それもワニかサメでもない限りは難しい。    綱は外洋へ流される。  橋の東側にある日向漁港から。左側に日向橋が見える。    ここからずっと常神半島の東側は全部日向である。たぶん海の漁場もそうなのだろう。タコなどとるのだろうか。天正年間には津波によりすでに廃絶していたといわれる「くるみ浦」も日向領である。獲れた魚などは京都大津方面へも行商していたという。
柳田国男「雪国の春」 〈 柳田国男「年占の二種」 〈 |
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||