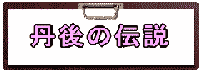丹後の伝説:33集
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「志楽小学校百年誌」に見る小学校の百年 |
小学校の百年とは、戦争の百年であり、戦争抜きには何も語れないし、戦争ばかりを書かねばならない悲しい歴史なのであるが、それが素直に貫かれ書かれているような本である。いい本だと私は思っている。大事に子孫たちに伝えなければならないことだけが書かれている。これが百年の歴史であることを忘れぬようにしたいものである。特に鎮守府の町、軍港の町だからこうであったというわけではなく、全国すべての小学校がこうしたことであった。
小学校の百年誌といったものは全国のどこの小学校でも作っているものとばかり私は勝手に思い込んでいたが、そうではないようで、丹後では舞鶴しか見ない。いや、「小学校 百年誌」で検索して貰えばわかるように、全国でもあまりないようで、私のこれらのHPがトップに出てくるくらいである。舞鶴はたいしたマチでもなく誇れるようなものも持たないが、百年誌は意外にも立派なよいエライ仕事であった。どうしても当「伝説」集では逃せない舞鶴人の立派な仕事である。
しかしそうしてせっかく立派な仕事をしていても、それを正確に評価できる舞鶴市民がいないため、図書館や校長室の書棚でホコリかぶったままで、誰もこの金の卵には見向きもしないものとなっている。どこか上の方から大ボメしてもらわないと、自分らの業績が評価できない、このあたりが舞鶴らしい、自分では判断のできない情けなくも文化不毛地と呼ばれるところであろうか。
戦争の百年の近代のわが村の百年史を垣間見ることができる。ただ学校によっては隠しているのか、発行部数がないのか、せっかく作ったはずなのに、一般市民には見られないものもあるのが残念。さて二百年誌はどう綴られることだろうか。そもそも学校があるのだろうか、ムラがあるのだろうか。ヘタすれば百年誌、コレッキリになるかも知れない。
志楽谷には、明治四年泉源寺智性院に「学校ナルモノ」を設けていました。学制頒布の翌年、明治六年には泉源寺、市場、田中で建てた遵法小学と小倉安岡、吉坂、鹿原で建てた含章小学、それに明治九年に松尾で建てた松尾校がありました。
明治九年四月十五日、鹿原の含章小学と泉源寺の遵法小学を合併して志楽校を創りましたが、わずか一年半後に事情があって再び分立して含章小学、遵法小学に逆もどりしたのでした。その後、明治二十年には遵法小学校を分校に含章小学校を本校として志楽尋常小学校と称し、松尾分校を置いていました。
明治四十二年志楽尋常小学校を鹿原から小倉(現在地)に移転し高等科も併置して志楽尋常高等小学校として松尾を分教場としました。昭和十六年国民学校令により志楽国民学校と改称、昭和二十二年新学制により志楽小学校となり、昭和三十九年には、松尾分教場の児童数が少なくなったので、同分校場を廃止し本校へ吸収されたのでした。
明治九年四月十五日、鹿原の含章小学と泉源寺の遵法小学を合併して志楽校を創りましたが、わずか一年半後に事情があって再び分立して含章小学、遵法小学に逆もどりしたのでした。その後、明治二十年には遵法小学校を分校に含章小学校を本校として志楽尋常小学校と称し、松尾分校を置いていました。
明治四十二年志楽尋常小学校を鹿原から小倉(現在地)に移転し高等科も併置して志楽尋常高等小学校として松尾を分教場としました。昭和十六年国民学校令により志楽国民学校と改称、昭和二十二年新学制により志楽小学校となり、昭和三十九年には、松尾分教場の児童数が少なくなったので、同分校場を廃止し本校へ吸収されたのでした。
軍港建設と新舞鶴町
第四舞鶴鎮守府の設置勅令が公布されたのは明治二十二年でした。日清戦争の影響もあって、着工は二十九年になり、海軍関係施設、工廠、港湾の他要塞砲兵隊、道路、市街建設も並行して進められ、鎮守府が開庁したのは明治三十四年十月で、北国街道や吉坂砲台道路もこの頃完成しました。「夜が明けたら道が出来ていた」と云われる程、突貫工事で進められたようです。鉄道は開道し、市街の人口は増加し、三十九年七月には浜村を主体に、倉梯、志楽の一部(今の龍宮、市場)を併せて、新舞鶴町が誕生しました。新市街(新舞鶴町)は当時の軍艦の名をとって、例えば「敷島」「三笠」のように命名したと云われています。
第四舞鶴鎮守府の設置勅令が公布されたのは明治二十二年でした。日清戦争の影響もあって、着工は二十九年になり、海軍関係施設、工廠、港湾の他要塞砲兵隊、道路、市街建設も並行して進められ、鎮守府が開庁したのは明治三十四年十月で、北国街道や吉坂砲台道路もこの頃完成しました。「夜が明けたら道が出来ていた」と云われる程、突貫工事で進められたようです。鉄道は開道し、市街の人口は増加し、三十九年七月には浜村を主体に、倉梯、志楽の一部(今の龍宮、市場)を併せて、新舞鶴町が誕生しました。新市街(新舞鶴町)は当時の軍艦の名をとって、例えば「敷島」「三笠」のように命名したと云われています。
学校は地方の教育、文化センター
小学校は地方の教育、文化センターとして学校教育は勿論、社会教育も地方の文化的なことに学校を利用しました。婦人会も処女会も青年団も、その他各種文化団体は皆、学校をよりどころにして集まり、活動を続けてきました。大正七年頃から校下では婦人会、青年団などが再興されました。
小学校は地方の教育、文化センターとして学校教育は勿論、社会教育も地方の文化的なことに学校を利用しました。婦人会も処女会も青年団も、その他各種文化団体は皆、学校をよりどころにして集まり、活動を続けてきました。大正七年頃から校下では婦人会、青年団などが再興されました。
出征兵士の見送りと無言の凱旋
日華事変が太平洋戦争に突入すると、父や兄が、先輩が次から次へと戦争にかり出されて行きました。緒戦の勝利は、幼い子どもたちを奮いたたせ、学業半ばで少年戦車兵に、少年飛行兵として、また満蒙開拓義勇軍として故郷を出て征ったのです。志楽からもたくさんの壮丁が応召しました。
戦争、事変に召集する令状を「赤紙」といいました。赤紙が来ると一週間程度の猶予の後入隊しました。妻子ある人にも遠慮なくこの赤紙が舞い込み悲壮な訣別でした。
小学生は、志楽から応召される人、出征される兵士を必ず見送りました。各地の氏神様で兵士の武運長久を祈り、それぞれ松尾寺駅や田中橋、市場橋まで見送りました。大きな幟を立て、日の丸の小旗を打ちふり「勝って来るぞと勇ましく、誓って国を出たからは、手柄たてずに死なれようか……」の軍歌に送られて行く光景は、子ども心にも印象的でした。
戦死の公報が家にとどけられて、遺骨が凱旋されるときは、全校生徒がある地点まで出迎えに行きました。遺骨は白木の箱に納められ白布に包まれて、戦友の胸にしっかりと抱かれて、物静かな歩調で故郷の土を踏まれるのでした。人びとは静かに頭をたれて無言の凱旋を出迎え、戦争のおそろしさ、かなしさが胸を刺しました。
日華事変が太平洋戦争に突入すると、父や兄が、先輩が次から次へと戦争にかり出されて行きました。緒戦の勝利は、幼い子どもたちを奮いたたせ、学業半ばで少年戦車兵に、少年飛行兵として、また満蒙開拓義勇軍として故郷を出て征ったのです。志楽からもたくさんの壮丁が応召しました。
戦争、事変に召集する令状を「赤紙」といいました。赤紙が来ると一週間程度の猶予の後入隊しました。妻子ある人にも遠慮なくこの赤紙が舞い込み悲壮な訣別でした。
小学生は、志楽から応召される人、出征される兵士を必ず見送りました。各地の氏神様で兵士の武運長久を祈り、それぞれ松尾寺駅や田中橋、市場橋まで見送りました。大きな幟を立て、日の丸の小旗を打ちふり「勝って来るぞと勇ましく、誓って国を出たからは、手柄たてずに死なれようか……」の軍歌に送られて行く光景は、子ども心にも印象的でした。
戦死の公報が家にとどけられて、遺骨が凱旋されるときは、全校生徒がある地点まで出迎えに行きました。遺骨は白木の箱に納められ白布に包まれて、戦友の胸にしっかりと抱かれて、物静かな歩調で故郷の土を踏まれるのでした。人びとは静かに頭をたれて無言の凱旋を出迎え、戦争のおそろしさ、かなしさが胸を刺しました。
銃後の守り
生活必需物資が配給統制となり、増産や貯蓄が強く提唱され、銃後の守りを固めることに最大の努力が注がれました。武器の製造のための資源回収として、各家庭にある金属類を一つ残らず供出させられました。
学校でも、児童の服の金ボタンまで供出、また二宮尊徳像、時鐘なども供出しました。
ブラスバンド
昭和十七年二月、ブラスバンドの楽器が寄贈され、迫田先生の指導で楽団が編成されました。大太鼓、小太鼓、トロンボーン、トランペット、バリトン、クラリネット、コルネットなどの編成で、楽長も決め、楽器の音階ができると単調な行進曲などの合奏も練習しました。半年ほどの練習を経ると「露営の歌」などの軍歌もこなせるようになりました。雪の降る中も素足で、歩行演奏の練習もありました。出征兵士の見送りに軍歌を演奏して華を添えました。
ますますゆがめられた教育の方向
戦争遂行のために、生活必需物資まで配給制度に切り替えられ、物資を大切にして、どんな事にも耐え得る精神力を培うための動員や勤労作業など苛酷な肉体労働を強いる生産教育が行われました。体育や作業を通じて、集団的な対抗、好戦的意識が育てられ、先生や上級生から並はづれた制裁が加えられもしました。
昭和十八・九年頃
緊急学徒勤労動員方策や、決戦非常措置要項などの通達が出されて、中学校以上の学徒は、学業を停止して、学校報国隊となって各軍需工場へ勤労動員にかり出されました。ややおくれて、高等科の生徒も海軍工廠や郵便局などへ学徒動員として出動したのでした。
教育会では「舞鶴市教育報国隊」を結成して、志楽小学校でも食糧増産教育に挺身し、校区内の荒廃地を開墾したり、休耕地はもちろんのこと、道路ぶちに豆をまいたり、ついには校庭まで掘り耕して芋を植えるなど、増産につぐ増産に明け暮れる毎日でした。
教員の中には、徴兵にかり出されたり、激務と疲労で病気欠勤するなど、人事面では補充に難渋をきわめたこともありました。また、五・六年生児童は「名誉の家」へ作業奉仕にも出かけました。
昭和十九年六月中旬には北九州方面の大空襲があり、舞鶴二中(現東舞鶴高校)から本校へ生徒六名が警戒に来ました。ついに、府教委から「教育に関する戦時非常措置方策」が通達され、中学校以上の学徒は修業年限短縮や、学徒の兵役徴集まで行われたのでした。
終戦の直前
昭和二十年三月三十日から、京都府の指令に基づき授業は停止され、四月には教室や廊下、講堂の天井テックスは、焼夷弾の戦禍から免れるため取り除かれました。四月二十九日の天長節拝賀式は講堂が軍需品の倉庫になっていたので校庭で挙行されたのでした。
奉安殿の御真影は、一大事が起っては大変と秘かに池内小学校へ移されました。
生活必需物資が配給統制となり、増産や貯蓄が強く提唱され、銃後の守りを固めることに最大の努力が注がれました。武器の製造のための資源回収として、各家庭にある金属類を一つ残らず供出させられました。
学校でも、児童の服の金ボタンまで供出、また二宮尊徳像、時鐘なども供出しました。
ブラスバンド
昭和十七年二月、ブラスバンドの楽器が寄贈され、迫田先生の指導で楽団が編成されました。大太鼓、小太鼓、トロンボーン、トランペット、バリトン、クラリネット、コルネットなどの編成で、楽長も決め、楽器の音階ができると単調な行進曲などの合奏も練習しました。半年ほどの練習を経ると「露営の歌」などの軍歌もこなせるようになりました。雪の降る中も素足で、歩行演奏の練習もありました。出征兵士の見送りに軍歌を演奏して華を添えました。
ますますゆがめられた教育の方向
戦争遂行のために、生活必需物資まで配給制度に切り替えられ、物資を大切にして、どんな事にも耐え得る精神力を培うための動員や勤労作業など苛酷な肉体労働を強いる生産教育が行われました。体育や作業を通じて、集団的な対抗、好戦的意識が育てられ、先生や上級生から並はづれた制裁が加えられもしました。
昭和十八・九年頃
緊急学徒勤労動員方策や、決戦非常措置要項などの通達が出されて、中学校以上の学徒は、学業を停止して、学校報国隊となって各軍需工場へ勤労動員にかり出されました。ややおくれて、高等科の生徒も海軍工廠や郵便局などへ学徒動員として出動したのでした。
教育会では「舞鶴市教育報国隊」を結成して、志楽小学校でも食糧増産教育に挺身し、校区内の荒廃地を開墾したり、休耕地はもちろんのこと、道路ぶちに豆をまいたり、ついには校庭まで掘り耕して芋を植えるなど、増産につぐ増産に明け暮れる毎日でした。
教員の中には、徴兵にかり出されたり、激務と疲労で病気欠勤するなど、人事面では補充に難渋をきわめたこともありました。また、五・六年生児童は「名誉の家」へ作業奉仕にも出かけました。
昭和十九年六月中旬には北九州方面の大空襲があり、舞鶴二中(現東舞鶴高校)から本校へ生徒六名が警戒に来ました。ついに、府教委から「教育に関する戦時非常措置方策」が通達され、中学校以上の学徒は修業年限短縮や、学徒の兵役徴集まで行われたのでした。
終戦の直前
昭和二十年三月三十日から、京都府の指令に基づき授業は停止され、四月には教室や廊下、講堂の天井テックスは、焼夷弾の戦禍から免れるため取り除かれました。四月二十九日の天長節拝賀式は講堂が軍需品の倉庫になっていたので校庭で挙行されたのでした。
奉安殿の御真影は、一大事が起っては大変と秘かに池内小学校へ移されました。
百年の中の一こま
大正七年度卒業
山本此衛太郎(田中)
… ストライキ!志楽小学校外史ともいう可き顕現されざる大事件が五年の時に起こった。空前にして絶後、一年先輩の六年生と複式授業を受けていた。先生は京都師範出身二十四・五歳だったと思うが厳格なスパルタ式教育の実践者であった。殴られた者も数人あった。たしか秋九月の終り頃であったと思う。同監休校!昼食が終って午後の授業が始まる前、われわれ悪童のリーダー○ちゃん、六年生のリーダー○ちゃんボスである。「勉強止めて遊びに行こう」と号令を出した。何の抵抗もなく五六年の男子全員学校裏の志楽川堤防に集った。一部の者は自分の字まで帰って遊んだ、何の話合いもなく各自寝ころんだり走ったりして、結構楽しく時を過した。ストライキをやる確かな理由も何もなかった。先生に対する一種の疎外感がみんなの頭の中にあったと思われる。そして数時間が経過した。「早く学校へ帰って来い」と指令が来た。ボツボツ全員教室に帰った。顔面蒼白の先生が教壇に突っ立って居られた。みんな着席するや、先生は「馬鹿ッ」と一言叫んで握り拳をふるわしておられた。何んとなくその日は終った。
翌日中村校長先生の特別訓戒・説諭をうけた。
「昨日お前達のやったことはストライキと英語で言うものである。君達のやったことがどんなに異常事でどんな結果が生れるかわからない。等々時間一パイ或は教え、或は諭し、或は叱りを受けた。一同はこどもながら徐々に事の重大さが理解され出した。当局ではいろいろ問題があったらしい。まもなく森先生は転任になった。最近全国的な学園ストを新聞でテレビで見るたびに往時を回顧して感慨に耽るのはわたくし一人であろうか。…
儀式・制裁のこと
昭和十五年度卒業
谷奥 昭(田中西)
儀式
学校では、一年間に一月一日の四方拝、二月十一日の紀元節、四月二十九日の天長節、十一月三日の明治節という祝日があり、全校生徒が参列する式があった。
その儀式の様子を紹介しょう。
式のある日は、朝九時に学校へ行った。
まず、奉安殿の前に校長先生が教育勅語を捧持され、歩かれる道幅を中央にして両側に生徒・先生が整列した。
奉安殿というのは、天皇陛下の御写真(御真影と呼んでいた)と教育勅語を収めておく倉である。志楽校の場合、今の岩石園のところにありました。鎖に囲まれていて、普通の場合だれも立ち入ることはできなかった。また、御写真は宮内庁から京都府知事を通して下賜され、保管していた大切な写真であった。明治天皇の場合も、大正天皇の場合もお亡くなりになった時は、その写真は返されたそうである。
さて、全校生徒が整列し最敬礼した中を、校長先生は御写真を奉持され、講堂の御写真安置所に向われる。校長先生の捧げ持たれる手に真白い手袋が着用されているのが印象的であった。
まず、全校生徒が講堂へ入場する。正面に向って左から一年、二年の順番であった。一番右側の窓ぎわに先生が入場され、次に一番左側の窓ぎわには、村長さんを始めとして来賓の方々が着席されました。
駐在所のお巡りさんが、金ピカの礼装に長いサーベルをつった姿が印象的でした。生徒は立ったままで約一時間三十分の長い式であった。
「ただいまから○○○式を挙行いたします」と開会が宣せられ、全員起立してオルガンに合わせて一同礼、来賓、先生方は着席される。この時は咳払いもできず、鼻水をすずることもできなかった。
次に、御写真安置所の幕が開かれる。(御開帳といった)校長先生がステージに上られて、白い手袋をはめられた手で右、左とレールの音もおごそかに開かれ、天皇陛下の御写真が目に映る。
そこで国歌「君が代」の斉唱があった。
そして、御写真に向って最敬礼をする。最敬礼をするときは、校長先生がステージ下の中央に御写真に向って、うやうやしく立たれ、最敬礼をされる。一同はこれにならって最敬礼するのだった。
この後、校長先生がステージにお立ちになる。そこで次席の先生が教育勅語を捧持される。教育勅語は巻物になっていて、黒いおぼんに入れて、その上にふくさがかけてあった。校長先生は、うやうやしくお受け取りになり、ふくさを取って、巻物を押しいただいてからひもを解かれ、ひもを巻物の端に順序よく巻きかけられ、巻物が静かに開かれ一礼される。そのとき一同は静かに頭をたれる。おごそかな声で〃朕オモウニ〃から始まり、最後が〃御名御璽〃であった。
この教育勅語奉読の頃になると、生徒の中には長時間の起立と緊張のため、目まいを起してバタンと倒れる者が出ることがしばしばあった。式の時間中、多いときは四、五人も倒れたことを覚えている。
教育勅語の奉読が終ると、勅語奉答歌〃あなとうとし おおみこと〃を歌った。
奉答歌が終ると御写真の閉帳があった。
そして、校長先生の〃今日の佳き日〃にちなんだお話しがあった。その頃生徒達は疲れ切っていた。寒い時には、足が棒のようになって冷たかったし、しもやけの手がうづいたりした。鼻水をすする音、咳払いする音が目立ちはじめるのもこの話しの頃であった。したがって私などは、お話しは耳に入る前に忘れてしまっていた。
最後に祝日の奉賛唱歌を歌った。寒い日は、歯がガツガツ鳴って満足に歌えなかった。
式が終ると教室へ入って、今日の式の行儀について、たいてい小言を聞いた。けれど紅白のマンジュウをもらったのはうれしかった。
制裁
支那事変が激しさを加える頃になると、何とはなしによく先生に叱られた。
いきなり何の理由もなしに、横面に先生の大きな手がとんでくることもまれではなかった。
授業中は、黒板を指す竹のムチが頭に降ってきたこともあるし、チョークをぶっつけられたこともあった。
先生には、それなりに〃良い子〃〃強い子〃にしようとしての制裁だったことはわかるが、今もって疑わしい無暴な制裁も幾度か経験した。
若い軍隊帰りの先生で、ささいなことで女生徒を殴り倒すというハプニングを見せつけられたこともあった。
戦時の国民学校
昭和二十年度卒業
奥本 和暢(神戸市)
昭和十五年に志楽尋常高等小学校の最後の一年生として入学した私達三十五人の学年は、翌二年生から国民学校となりました。
徴用工員世帯や疎開児で人数が増えて七十人を越すようになって五年から男女二組になり、昭和二十一年春最後の国民学校児童として卒業しました。昭和十六年から太平洋戦争が始り二度と繰返したくない異常な小学時代を経験しました。
国民学校の教科書は生命を投げ出して皇室を中心に神国日本を敵国から守る事を教える内容で一杯で、朝礼では校長先生から戦局の話ばかり、歌うは軍歌ばかり、図画では空中戦や海戦をよく描きました。先生や上級生に私達はよく殴られました。教室に大和魂作興棒という鞭が置いてありました。先生は神様の様に尊く、鬼の様に恐ろしい方でした。
冬は雪がよく降りましたがゴム長靴は店に無いのでツギだらけの靴やわら靴で、時にははだしで通学したものです。時々クラスに一、二足の靴が配給ざれ先生はその配分に苦労されました。当った人は教壇の先生の机の上に立って「皆に済まんけどああ嬉し」と大声で言いました。空襲も多くなり防空壕を堀ったり阿良須神社への待避訓練をしました。防空頭巾をかぶり自分で編んだ草履をはいて通学しました。
五年の頃から勉強どころではなく学校へは行かず安岡・鹿原・松尾などへ農地開墾や炭焼きに出かけました。重い唐鍬をかついで、イモや南瓜の弁当持って泉源寺から松尾まで歩いて登り荒地開きに精出しました。
担任の塩見先生も出征されました。終いには校舎も軍隊に取上げられてしまいました。銃の撃ち方や竹槍の使い方も習いました。自分達が銃後を守るんだと張切っていました。
戦争が終り学校へ帰ってみると校舎の天井は取払われ雨の日は雨漏りの中で授業でした。床板も盛上っていました。教科書は軍国主義的な部分に墨を塗らされ無残な姿となり勉強する気もおこりませんでした。
このような得がたい実生活のきびしい教育を受けた経験は戦後の混乱期をたくましく生きる支えとなった事と思います。
悲しくなつかしい言葉
昭和二十年度卒業
福村 弸(吉坂)
「大東亜戦争」これはすべての人びとにとって忌わしい言葉に相違ない。
私の小学生時代もほとんど戦争一色であった。
駅頭で「出征兵士を送る歌」を力一杯歌い、防空頭巾をかぶり登校する。校門を入ると奉安殿に最敬礼をしなければならなかった。
いろいろと先生の話を聞き竹槍訓練で。パンツが破れるほどしごかれる。また、校長先生の教育勅語に威儀を正し直立不動で緊張したものである。
家に帰ればオヤツは胡瓜・さつまいも・柿といったもので燈火管制のため黒い覆いをつけた暗い電燈の下で勉強しながら、古ぼけたラジオから雑音と共に流れる大本営発表に祖父母と一喜一憂、空襲警報発令に身体がふるえて困ったこともある。 八月十五日、この頃になると松尾寺駅も出札、改札係の人は女性ばかりになっていたが、私が遊びに行っていた時、その女性達がラジオを聞いて突然泣きだしたので驚いて尋ねると「日本は敗けたの」といわれてビックリして家にとんで帰って祖父に伝えると、「そんな馬鹿な事があるか!」とどな
られ、何が何だかわからなかったことを憶えている。
「ほしがりません、勝つまでは」という言葉を精神的・肉体的に理解していたかどうかはわからないが、ただ一つ間違いのないことは、今の時代のようにすべて疑いの目でものを見ることがなかった、という事だろうか。
雨の日にバス通学の子らを見て
裸足で通いし頃なつかしむ
太平洋戦争とともに
=激動と耐乏の六年間=
昭和二十一年度卒業
上西 正樹(田中)
軍人万能
あおいとり ことり
なぜなぜ あおい
あおいみなたべた
それは、ちょうど音楽の時間が始まってから三十分が過ぎみんながようやく歌詞と音譜にも慣れ、大きな口を開いて無心に歌いはじめていたときであった。
突然、教室の戸がガラガラッと乱暴にあけられ、教頭先生が緊張した面もちで入ってこられ、潮見先生を手まねきされた。
二言三言何ごとか小声で耳打ちされると潮見先生の顔が一瞬さっと青ざめ、深く一礼されたが、教壇へ戻ってこられる足どりから、私達は何か重大な事件が起ったことを子供心にも感じとったのである。
「みなさん 皇居に向って起立しなさい。いま、日本の国は米・英と戦争をはじめたのです。必ず勝つことを祈って黙祷をささげましょう」。
昭和十六年十二月八日午前十時三十分、志楽国民学校へ入学して、わずか九か月後に国と国民の運命を一変させた太平洋戦争へ突入、それまで平和な日々を送っていた私達は、軍国主義一辺倒の時代へと引き込まれて行ったのである。
戦時下にあっては、軍人万能となるのは当然であるが、二年生になると学習の面においても算数・理科に比べて修身(今の道徳ともいうべきか)はもちろん国語・歴史・地理、それに図画の時間が多くなってきた。
国語の時間は、もっぱら戦地で闘っている兵士への慰問文を書いたり、歴史では武人、軍人を讃えたものが多く、地理は戦場となっている東南アジア・中国方面の地図を中心に学んだ。
私は、絵を描くことが好きであったので図画の時間がふえたのがうれしかった。
戦争を礼讃したボスター。
敵艦を攻撃し騒沈させるゼロ戦、雄姿を太平洋上に浮べて堂々の行進をする連合艦隊、それらすべてが、クレオンや絵筆を持つ手をふるわせ、いやがうえにも興奮させ熱中させた。
当時は、戦勝によって国民はみな酔いしれていた良き時代で、旗行列に参加したり戦争映画がよく講堂で上映されたものである。
三年生時代。 それは、わが国がガダルカナルの撤退、アッツ島守備隊の玉砕など敗色がただよいはじめた年で、政府も戦意高揚と人心一新をはかるため〃一億一心火の玉だ〃と団結と勇気をふるい起こさせるための精神教育と帝国主義に基づいた洗脳教育が盛んに行われ〃心を入れ替えてがんばろう〃、〃戦地の兵隊さんに負けないよう銃後の守りを固めよう〃といった気運が生徒の間にも高まりつつあった。
お前は、大きくなったら何になるか-。と聞かれれば即座に「陸軍大将か海軍大将になります」と答えたものである。
輸血のための血液検査が行われたのもこの頃で、胸に血液型と住所、氏名、年齢を記入した布を縫い込んだ上着を着用し、カバンの中には必ず日の丸の小旗を入れて登校した。また、戦争の激化とともに英霊の出迎えと出征兵士の見送りが日を追って多くなった。
いまだに深く印象に残っているのは、阿良須神社で行われる出征兵士の壮行会(武運長久祈願)に参加したのち、国道を……
〃勝って来るぞと 勇ましく 誓って国を出たからにゃ手柄たてずに 死なりょうか--〃
と軍歌を歌いながら田中橋まで見送り、兵士の姿が山かげに見えなくなるまで小旗を打ち振り歌い続けたことである。後年、父が出征する際も同じようにして見送った。
三年三学期には、男の先生も応召でめっきり少なくなり、高等女学校を卒業したばかりの先生(代用教員)が多くなった。
弁当泥棒
そして四年生へ。
〃男女席を同じゅうせず〃と一学期から男女別々の教室に分けられて学ぶことになった。
爆撃こそなかったが、敵機(B二九)が舞鶴の空にも現われはじめ、緊迫した空気が流れはじめていた。このような情勢を反映して、子供達の遊びも学習内容もすべてが戦争に結びついたものとなった。
楽しいはずのチャンバラごっこ、戦争ごっこが青竹での殴り合い、上級生による下級生への体罰や派閥間、部落間の抗争。それに軍事教練の実施(五、六年)、先生のビンタ(制裁)、軍人勅諭の暗唱、どれ一つをみても焦燥から生まれたものというほかない。
こうした殺伐とした学校生活の中で育った私達は、現在、その反動として必要以上に子供を甘やかす父親になってしまったのではないだろうか。
「いまから運動靴と学生服の抽せんを行います。これまでに当ったことのある人は今度はだめです」。
衣類、日用雑貨品が店頭から姿を消しはじめ、学生服も上着とズボン別々に抽せんにかけられ、しかも年間を通して一学級にせいぜい運動靴で七足、学生服で五着程度の配給だったため、私などくじ運の弱い者はなかなか順番が回ってこなかった。
食糧品については、もっとひどく手に入る量は配給通帳に記入された家族数や年齢構成によってきめられており、魚類の配給などは朝五時ごろから長蛇の列ができた。
配給される魚は、サバ・イワシ・アジなど大衆魚ばかりで配給日に水揚量が少ないと、たとえばサバなどは、頭と胴としっぽの三つに切り分けられ、もっとひどい時には二時間も待たされたあげく品切れという日もたびたびあった。
このため、子供達も朝早くから順番取りに行かされたものである。
白いご飯に真赤な梅干「日の丸弁当」はもう食べられない。
農家の子でも、定められた保有米を残し、あとは全部強制的に供出させられサツマイモかジャガイモ、カボチャの代用食、良くて大豆、大根入りご飯、それに自分の目玉が映るような〃ぞうすい〃が毎日の食事となり、学校では弁当泥棒が横行。盗られた弁当箱はからになると便所の中へ捨てられてしまった。(便所でかくれて食べるため)
青くやせこけた顔に眼だけが異様に光る。
飢えとひもじさから校庭(運動場)では集団暴行事件がひんぱんに起ったのである。
私達の学級は、入学当時三十四名の少人数であったが、戦火の拡大とともに田中地区に五百戸(現在の田中中と西町内に建設されていたが、戦後、福井市の大震災罹災世帯用として取り壊わされ移築された)と鹿原地区に百戸(現在の鹿原西)の軍需産業に働く人たちの大団地が建設されたのをはじめ、軍人、軍属世帯が農家の離れを借りて住みはじめたことなどによって一挙にふくれ上がり、五年の一学期が始まる頃には、さらに都会や市街地からの疎開者が加わって、各学年とも寿司ずめの二クラス編成となった。
志楽の地に生まれ育った生徒と、新しく他所から転校してきた生徒との間に、激しい争いが日夜起ったのもこの頃である。
ある日のこと、白い七つボタンの制服を着た二人(郷土出身の谷奥昭、森田茂(旧姓上西)の両氏)の海軍甲種飛行予科練習生が学校を訪れ、軍隊生活と戦況報告会が開かれた。
この時のりりしい予科練服姿と講演に感動したことは、今も忘れることはできない。
〃忠君愛国〃「天皇陛下とお国のためにぼくも予科練に入って敵艦を沈めてやろう--」
食糧増産
五年生。それは最も苦しい時代であった。
進級と同時に行った最初の作業は、教室の天井に張ってあったテックスを落すことであった。これは、屋根に落ちた焼夷弾が屋根を突き抜け天井に止まった場合、天井裏に火が早く回り消火活動のさまたげになるためで、五・六年生が棒倒しや肥桶かつぎに使う竹竿で下から突き上げ、全教室のテックスを破り落した。このほか空襲の防備策として爆撃目標となる白壁をコールタールで、まだらに塗りつぶしたりもした。後に天井が張られるまでの年月、いくらストーブを焚いてもぬくもらずガタガタふるえていたものである。
朝八時、二列縦隊に並んで上級生を先頭に草履ばきで登校。
校門を入ったところで隊列を整えてから奉安殿と二宮尊徳像に向って最敬礼。
八時半朝礼の鐘が鳴ると学年別に全員講堂に集合。「君が代」の斉唱の後、校長先生の教育勅語の朗読と訓話を聞き、教室に戻ると、われ先にと農具を取りに倉庫へ駆けて行き、すぐさま校庭に整列。
点呼を受けたのち開墾地めざして出発するのが日課となった。
くわ、かま、つるはし、すこっぷ……それに二人一組になって肥桶をかついだ幼い少年達の勤労作業隊が軍歌を合唱しながら、一糸乱れず行進するざまは、何ともいじらしくも頼もしい姿であった。
食糧欠乏、戦地の兵隊さんに少しでもおいしい物を食べていただき、ぼくたちは〃ほしがりません勝つまでは〃をモットーに食糧増産に励んでいたのである。 当時、開墾地として学校側が借りていたのは松尾、吉坂、鹿原、安岡、小倉、泉源寺などで、ほとんどが山あいの休耕畑で、かや刈り場であったり雑木林と化している荒地であった。一株掘り起こすのに小さな株でも最低三十分から一時間もかかった。
しかし、整地し大豆やイモをまき終ったあとの気分は壮快なもので、明日への希望をわかせてくれた。
また、日曜日には道路わきにヒマの種をまいたり、松根掘りやドングリ拾いに行ったものだが、これらは航空機の燃料や工業用・薬用油の原料になるのだと聞かされていた。
さて、三、四か月が過ぎていよいよ収穫期となり、かごをかついで開墾地へ行ってみると兎や野鳥、野ねずみに食い荒されており、大豆にいたっては、いくら山畑とはいえ種の量より少なかったのは誠に残念であった。
私が属していた青葉山部隊は、道のりも遠く急斜面の山道を登らなければ目的地に着けないなど、腹はへり人一倍疲れたが、それでも楽しいこともあった。山野には桑、ヤマイチゴ、クルミ、イチョウ、グミ、クリなどの木がたくさんありおいしい実をつけていたし、フキ、ワラビ、ゼンマイ、イタドリなどの山菜もたくさん採ることができた。
何といっても楽しかったことは、木綿糸と針金で作った釣道具で松尾寺の池のコイやフナを釣り上げ弁当がらに詰め込んで持ち帰り、塩焼きにして食べたことである。
戦時下の最も苦しかった時代に少年期を過ごした私達にとって、遊び道具といえば竹トンボ、紙・杉鉄砲、模型飛行機、パン(めんこ)程度であったが、戦争が悪化した四年生ごろからは、何も買うことはできなくなり、棒切れ(または青竹)を大小二本腰に差して遊び回るというありさまで、金属製のものは
兵器を造るための原料として全部供出させられてしまった。
学生服に付いていた金ボタンなども供出させられ、かわりにからつ製(または、木製)のものが配ばられたのである。
野球、バレーボー化 卓球、テニスなど外国で生まれた球技は一切禁止されていたので、もっぱら男子は長馬、相撲、木登り、魚とりなどを、女子は花つみ、あやとり、お手玉、石けりなど古来の遊びそのままであった。
一方、学校での勉強はほとんどなく晴れた日には前述の農作業を、雨が降れば精神統一のため座禅を組んだり、〃鬼畜米英〃〃撃ちてし止まむ〃など、とくに米・英国に対して憎悪の念と敵愾心をかりたてる標語を書いて、電柱や町内の掲示板に貼って回った。
しかし、このような学校生活にもかかわらず一学期の通知簿はもらった。
その成績評価(優、良上、良、良下、可の五段階)はたいへんなもので、たとえば農作業中まじめにやっていれば修身国語は優、木の根っこを、何個掘り起こせるかで体操の成績が決まる。種まきが上手にできないと理科が良下といった具合で、すべてが学校での生活態度で評価された。
五年生になってから終戦までの四か月半、学習なしの試験なしという学校生活を送れたのは、まったくうれしいかぎりであった。
一学期も終わろうとしていた頃には、日に何度となく敵機が来襲、空襲警報の連続で、サイレンが鳴り響くたびに防空頭巾をかぶり、農作業中の場合は草むらや木陰へ、授業中であれば校庭のイモ畑(当時、校庭の三分の二はイモ畑となっていた)の中へと避難し、目と耳を両手でふさいで地面に伏せた。
もう、勉強はもちろん農作業も安心してやれない。
戦争が末期を迎えた七月から八月にかけては、食糧不足による栄養失調によって登校すらできない生徒が続出。それでも夏休み返上でがんばったが、連日の空襲のため自宅待機の日が多くなった。
七月三十日の舞鶴空襲は本格的なもので、最初で最後の大規模なものであった。敵小型機(グラマン戦闘機)約二百三十機が午前と午後の二回にわたって飛来し、軍事施設を爆撃とくに湾内に停泊していた艦船はほとんど撃破されてしまったが、校区内への爆弾投下は皆無であった。
八月十五日終戦の日は自宅で迎えたが、その二日後の十七日全員登校。
講堂は、軍需物資の倉庫として使用されていたので、校庭に集まり校長先生からあらためて敗戦を知らされた。
先生と上級生の中から鳴咽とすすり泣きの声が起こり、私も青葉山をにらみつけながら大粒の涙を流した。
ただ、ひたすらに勝利を信じていたのに。
その後、学校内での混乱はなく、これまでの農作業中心からやっと開放され、本来の学業が少し受けられるようになり十一月から二桁の割り算、掛け算を習いはじめた。
先生の授業態度も極端に軟化し、何をしてもあまり叱られなくなったため、これまでの反動もあってか学習態度は悪く時間中に弁当を食べる者、ストーブで餅を焼いて食べる者、ビー玉をころがして遊ぶ者など気ままに過ごした。
学校給食
六年生。
終戦とともに教育内容も民主主義に基づいたものへと大きく変革された。
まず、私達を驚かせたのは、これまでの歴史、修身、地理の教科書は使用禁止、国語についても戦意高揚、神話などの記載か所は墨で消して使用したこと。また、新しく配られた教科書も新聞紙大の雑用紙に印刷されており、四つに折りたたんで、上、下と左側を切り離し、右側をとじると一冊の本になるという簡単なものであったことである。
さらに、ホームルームなるものがとり入れられたことであった。
議長を選んだり、何事もクラス全員の討議によってすべてを決めるという、まったく新しい学校生活にとまどったものである。
野球をやり始めたのもこの頃からで、イモ畑となっていた校庭も五月には整地され体操の時間や放課後には、ゴムボール(軟式テニスのボールと同じ)でよく遊んだ。
学習態度にもようやく落ち着きがみられるようになった七月頃には、四・五年当時八十名を越していた級友達も大半が故郷や両親のもとへと去り、五十名たらずに減少していた。
楽しかった戦後はじめての運動会も終り、秋も深まりをみせはじめた頃、志楽小学校でも進駐軍の援助物資による学校給食が実施されるようになり、私達六年生はあとわずかで卒業するため、下級生より早く食べさせてもらった。
食糧難を切り抜けてきた者にとっては、何よりもうれしく大歓声をあげて教室内をはしゃぎ回ったものである。
粉ミルク、砂糖、肉のかん詰……。
なかでも肉のかん詰を切り、各家庭から持ち寄った大根、白菜、ジャガイモと一緒に煮込んだ肉汁はほんとうにうまかった。(ご飯と汁入れ茶わんは各自持参)
しかし、イモやカボチャを主食としていた胃腸は、あまりの御馳走にびっくりしたのか、下痢、腹痛、じんましんを起こし、半数近くが寝込んでしまった。
また、米兵に品物をよくねだったものである。
朝来の吉野地区(現在、国立舞鶴工業高等専門学校)に戦時中、火薬廠があったため巡視のジープが毎日行き来していたが、そのジープが学校前を通るたびに、みんなが校門前に駆け出し口ぐちに 「ヘーイ ガムガム プレゼント」(おーいチューインガムをください)と敗戦の屈辱感を忘れたかのように呼びかけた。
戦地で死闘を続ける兵士に励ましの手紙を書いた同じ手で今度は「進駐軍の兵隊さんありがとう」と援助物資に対する感謝状を書き送ったものである。
一方、英語を知らない者は人にあらずとばかり、三学期にローマ字を習った。…
大正七年度卒業
山本此衛太郎(田中)
… ストライキ!志楽小学校外史ともいう可き顕現されざる大事件が五年の時に起こった。空前にして絶後、一年先輩の六年生と複式授業を受けていた。先生は京都師範出身二十四・五歳だったと思うが厳格なスパルタ式教育の実践者であった。殴られた者も数人あった。たしか秋九月の終り頃であったと思う。同監休校!昼食が終って午後の授業が始まる前、われわれ悪童のリーダー○ちゃん、六年生のリーダー○ちゃんボスである。「勉強止めて遊びに行こう」と号令を出した。何の抵抗もなく五六年の男子全員学校裏の志楽川堤防に集った。一部の者は自分の字まで帰って遊んだ、何の話合いもなく各自寝ころんだり走ったりして、結構楽しく時を過した。ストライキをやる確かな理由も何もなかった。先生に対する一種の疎外感がみんなの頭の中にあったと思われる。そして数時間が経過した。「早く学校へ帰って来い」と指令が来た。ボツボツ全員教室に帰った。顔面蒼白の先生が教壇に突っ立って居られた。みんな着席するや、先生は「馬鹿ッ」と一言叫んで握り拳をふるわしておられた。何んとなくその日は終った。
翌日中村校長先生の特別訓戒・説諭をうけた。
「昨日お前達のやったことはストライキと英語で言うものである。君達のやったことがどんなに異常事でどんな結果が生れるかわからない。等々時間一パイ或は教え、或は諭し、或は叱りを受けた。一同はこどもながら徐々に事の重大さが理解され出した。当局ではいろいろ問題があったらしい。まもなく森先生は転任になった。最近全国的な学園ストを新聞でテレビで見るたびに往時を回顧して感慨に耽るのはわたくし一人であろうか。…
儀式・制裁のこと
昭和十五年度卒業
谷奥 昭(田中西)
儀式
学校では、一年間に一月一日の四方拝、二月十一日の紀元節、四月二十九日の天長節、十一月三日の明治節という祝日があり、全校生徒が参列する式があった。
その儀式の様子を紹介しょう。
式のある日は、朝九時に学校へ行った。
まず、奉安殿の前に校長先生が教育勅語を捧持され、歩かれる道幅を中央にして両側に生徒・先生が整列した。
奉安殿というのは、天皇陛下の御写真(御真影と呼んでいた)と教育勅語を収めておく倉である。志楽校の場合、今の岩石園のところにありました。鎖に囲まれていて、普通の場合だれも立ち入ることはできなかった。また、御写真は宮内庁から京都府知事を通して下賜され、保管していた大切な写真であった。明治天皇の場合も、大正天皇の場合もお亡くなりになった時は、その写真は返されたそうである。
さて、全校生徒が整列し最敬礼した中を、校長先生は御写真を奉持され、講堂の御写真安置所に向われる。校長先生の捧げ持たれる手に真白い手袋が着用されているのが印象的であった。
まず、全校生徒が講堂へ入場する。正面に向って左から一年、二年の順番であった。一番右側の窓ぎわに先生が入場され、次に一番左側の窓ぎわには、村長さんを始めとして来賓の方々が着席されました。
駐在所のお巡りさんが、金ピカの礼装に長いサーベルをつった姿が印象的でした。生徒は立ったままで約一時間三十分の長い式であった。
「ただいまから○○○式を挙行いたします」と開会が宣せられ、全員起立してオルガンに合わせて一同礼、来賓、先生方は着席される。この時は咳払いもできず、鼻水をすずることもできなかった。
次に、御写真安置所の幕が開かれる。(御開帳といった)校長先生がステージに上られて、白い手袋をはめられた手で右、左とレールの音もおごそかに開かれ、天皇陛下の御写真が目に映る。
そこで国歌「君が代」の斉唱があった。
そして、御写真に向って最敬礼をする。最敬礼をするときは、校長先生がステージ下の中央に御写真に向って、うやうやしく立たれ、最敬礼をされる。一同はこれにならって最敬礼するのだった。
この後、校長先生がステージにお立ちになる。そこで次席の先生が教育勅語を捧持される。教育勅語は巻物になっていて、黒いおぼんに入れて、その上にふくさがかけてあった。校長先生は、うやうやしくお受け取りになり、ふくさを取って、巻物を押しいただいてからひもを解かれ、ひもを巻物の端に順序よく巻きかけられ、巻物が静かに開かれ一礼される。そのとき一同は静かに頭をたれる。おごそかな声で〃朕オモウニ〃から始まり、最後が〃御名御璽〃であった。
この教育勅語奉読の頃になると、生徒の中には長時間の起立と緊張のため、目まいを起してバタンと倒れる者が出ることがしばしばあった。式の時間中、多いときは四、五人も倒れたことを覚えている。
教育勅語の奉読が終ると、勅語奉答歌〃あなとうとし おおみこと〃を歌った。
奉答歌が終ると御写真の閉帳があった。
そして、校長先生の〃今日の佳き日〃にちなんだお話しがあった。その頃生徒達は疲れ切っていた。寒い時には、足が棒のようになって冷たかったし、しもやけの手がうづいたりした。鼻水をすする音、咳払いする音が目立ちはじめるのもこの話しの頃であった。したがって私などは、お話しは耳に入る前に忘れてしまっていた。
最後に祝日の奉賛唱歌を歌った。寒い日は、歯がガツガツ鳴って満足に歌えなかった。
式が終ると教室へ入って、今日の式の行儀について、たいてい小言を聞いた。けれど紅白のマンジュウをもらったのはうれしかった。
制裁
支那事変が激しさを加える頃になると、何とはなしによく先生に叱られた。
いきなり何の理由もなしに、横面に先生の大きな手がとんでくることもまれではなかった。
授業中は、黒板を指す竹のムチが頭に降ってきたこともあるし、チョークをぶっつけられたこともあった。
先生には、それなりに〃良い子〃〃強い子〃にしようとしての制裁だったことはわかるが、今もって疑わしい無暴な制裁も幾度か経験した。
若い軍隊帰りの先生で、ささいなことで女生徒を殴り倒すというハプニングを見せつけられたこともあった。
戦時の国民学校
昭和二十年度卒業
奥本 和暢(神戸市)
昭和十五年に志楽尋常高等小学校の最後の一年生として入学した私達三十五人の学年は、翌二年生から国民学校となりました。
徴用工員世帯や疎開児で人数が増えて七十人を越すようになって五年から男女二組になり、昭和二十一年春最後の国民学校児童として卒業しました。昭和十六年から太平洋戦争が始り二度と繰返したくない異常な小学時代を経験しました。
国民学校の教科書は生命を投げ出して皇室を中心に神国日本を敵国から守る事を教える内容で一杯で、朝礼では校長先生から戦局の話ばかり、歌うは軍歌ばかり、図画では空中戦や海戦をよく描きました。先生や上級生に私達はよく殴られました。教室に大和魂作興棒という鞭が置いてありました。先生は神様の様に尊く、鬼の様に恐ろしい方でした。
冬は雪がよく降りましたがゴム長靴は店に無いのでツギだらけの靴やわら靴で、時にははだしで通学したものです。時々クラスに一、二足の靴が配給ざれ先生はその配分に苦労されました。当った人は教壇の先生の机の上に立って「皆に済まんけどああ嬉し」と大声で言いました。空襲も多くなり防空壕を堀ったり阿良須神社への待避訓練をしました。防空頭巾をかぶり自分で編んだ草履をはいて通学しました。
五年の頃から勉強どころではなく学校へは行かず安岡・鹿原・松尾などへ農地開墾や炭焼きに出かけました。重い唐鍬をかついで、イモや南瓜の弁当持って泉源寺から松尾まで歩いて登り荒地開きに精出しました。
担任の塩見先生も出征されました。終いには校舎も軍隊に取上げられてしまいました。銃の撃ち方や竹槍の使い方も習いました。自分達が銃後を守るんだと張切っていました。
戦争が終り学校へ帰ってみると校舎の天井は取払われ雨の日は雨漏りの中で授業でした。床板も盛上っていました。教科書は軍国主義的な部分に墨を塗らされ無残な姿となり勉強する気もおこりませんでした。
このような得がたい実生活のきびしい教育を受けた経験は戦後の混乱期をたくましく生きる支えとなった事と思います。
悲しくなつかしい言葉
昭和二十年度卒業
福村 弸(吉坂)
「大東亜戦争」これはすべての人びとにとって忌わしい言葉に相違ない。
私の小学生時代もほとんど戦争一色であった。
駅頭で「出征兵士を送る歌」を力一杯歌い、防空頭巾をかぶり登校する。校門を入ると奉安殿に最敬礼をしなければならなかった。
いろいろと先生の話を聞き竹槍訓練で。パンツが破れるほどしごかれる。また、校長先生の教育勅語に威儀を正し直立不動で緊張したものである。
家に帰ればオヤツは胡瓜・さつまいも・柿といったもので燈火管制のため黒い覆いをつけた暗い電燈の下で勉強しながら、古ぼけたラジオから雑音と共に流れる大本営発表に祖父母と一喜一憂、空襲警報発令に身体がふるえて困ったこともある。 八月十五日、この頃になると松尾寺駅も出札、改札係の人は女性ばかりになっていたが、私が遊びに行っていた時、その女性達がラジオを聞いて突然泣きだしたので驚いて尋ねると「日本は敗けたの」といわれてビックリして家にとんで帰って祖父に伝えると、「そんな馬鹿な事があるか!」とどな
られ、何が何だかわからなかったことを憶えている。
「ほしがりません、勝つまでは」という言葉を精神的・肉体的に理解していたかどうかはわからないが、ただ一つ間違いのないことは、今の時代のようにすべて疑いの目でものを見ることがなかった、という事だろうか。
雨の日にバス通学の子らを見て
裸足で通いし頃なつかしむ
太平洋戦争とともに
=激動と耐乏の六年間=
昭和二十一年度卒業
上西 正樹(田中)
軍人万能
あおいとり ことり
なぜなぜ あおい
あおいみなたべた
それは、ちょうど音楽の時間が始まってから三十分が過ぎみんながようやく歌詞と音譜にも慣れ、大きな口を開いて無心に歌いはじめていたときであった。
突然、教室の戸がガラガラッと乱暴にあけられ、教頭先生が緊張した面もちで入ってこられ、潮見先生を手まねきされた。
二言三言何ごとか小声で耳打ちされると潮見先生の顔が一瞬さっと青ざめ、深く一礼されたが、教壇へ戻ってこられる足どりから、私達は何か重大な事件が起ったことを子供心にも感じとったのである。
「みなさん 皇居に向って起立しなさい。いま、日本の国は米・英と戦争をはじめたのです。必ず勝つことを祈って黙祷をささげましょう」。
昭和十六年十二月八日午前十時三十分、志楽国民学校へ入学して、わずか九か月後に国と国民の運命を一変させた太平洋戦争へ突入、それまで平和な日々を送っていた私達は、軍国主義一辺倒の時代へと引き込まれて行ったのである。
戦時下にあっては、軍人万能となるのは当然であるが、二年生になると学習の面においても算数・理科に比べて修身(今の道徳ともいうべきか)はもちろん国語・歴史・地理、それに図画の時間が多くなってきた。
国語の時間は、もっぱら戦地で闘っている兵士への慰問文を書いたり、歴史では武人、軍人を讃えたものが多く、地理は戦場となっている東南アジア・中国方面の地図を中心に学んだ。
私は、絵を描くことが好きであったので図画の時間がふえたのがうれしかった。
戦争を礼讃したボスター。
敵艦を攻撃し騒沈させるゼロ戦、雄姿を太平洋上に浮べて堂々の行進をする連合艦隊、それらすべてが、クレオンや絵筆を持つ手をふるわせ、いやがうえにも興奮させ熱中させた。
当時は、戦勝によって国民はみな酔いしれていた良き時代で、旗行列に参加したり戦争映画がよく講堂で上映されたものである。
三年生時代。 それは、わが国がガダルカナルの撤退、アッツ島守備隊の玉砕など敗色がただよいはじめた年で、政府も戦意高揚と人心一新をはかるため〃一億一心火の玉だ〃と団結と勇気をふるい起こさせるための精神教育と帝国主義に基づいた洗脳教育が盛んに行われ〃心を入れ替えてがんばろう〃、〃戦地の兵隊さんに負けないよう銃後の守りを固めよう〃といった気運が生徒の間にも高まりつつあった。
お前は、大きくなったら何になるか-。と聞かれれば即座に「陸軍大将か海軍大将になります」と答えたものである。
輸血のための血液検査が行われたのもこの頃で、胸に血液型と住所、氏名、年齢を記入した布を縫い込んだ上着を着用し、カバンの中には必ず日の丸の小旗を入れて登校した。また、戦争の激化とともに英霊の出迎えと出征兵士の見送りが日を追って多くなった。
いまだに深く印象に残っているのは、阿良須神社で行われる出征兵士の壮行会(武運長久祈願)に参加したのち、国道を……
〃勝って来るぞと 勇ましく 誓って国を出たからにゃ手柄たてずに 死なりょうか--〃
と軍歌を歌いながら田中橋まで見送り、兵士の姿が山かげに見えなくなるまで小旗を打ち振り歌い続けたことである。後年、父が出征する際も同じようにして見送った。
三年三学期には、男の先生も応召でめっきり少なくなり、高等女学校を卒業したばかりの先生(代用教員)が多くなった。
弁当泥棒
そして四年生へ。
〃男女席を同じゅうせず〃と一学期から男女別々の教室に分けられて学ぶことになった。
爆撃こそなかったが、敵機(B二九)が舞鶴の空にも現われはじめ、緊迫した空気が流れはじめていた。このような情勢を反映して、子供達の遊びも学習内容もすべてが戦争に結びついたものとなった。
楽しいはずのチャンバラごっこ、戦争ごっこが青竹での殴り合い、上級生による下級生への体罰や派閥間、部落間の抗争。それに軍事教練の実施(五、六年)、先生のビンタ(制裁)、軍人勅諭の暗唱、どれ一つをみても焦燥から生まれたものというほかない。
こうした殺伐とした学校生活の中で育った私達は、現在、その反動として必要以上に子供を甘やかす父親になってしまったのではないだろうか。
「いまから運動靴と学生服の抽せんを行います。これまでに当ったことのある人は今度はだめです」。
衣類、日用雑貨品が店頭から姿を消しはじめ、学生服も上着とズボン別々に抽せんにかけられ、しかも年間を通して一学級にせいぜい運動靴で七足、学生服で五着程度の配給だったため、私などくじ運の弱い者はなかなか順番が回ってこなかった。
食糧品については、もっとひどく手に入る量は配給通帳に記入された家族数や年齢構成によってきめられており、魚類の配給などは朝五時ごろから長蛇の列ができた。
配給される魚は、サバ・イワシ・アジなど大衆魚ばかりで配給日に水揚量が少ないと、たとえばサバなどは、頭と胴としっぽの三つに切り分けられ、もっとひどい時には二時間も待たされたあげく品切れという日もたびたびあった。
このため、子供達も朝早くから順番取りに行かされたものである。
白いご飯に真赤な梅干「日の丸弁当」はもう食べられない。
農家の子でも、定められた保有米を残し、あとは全部強制的に供出させられサツマイモかジャガイモ、カボチャの代用食、良くて大豆、大根入りご飯、それに自分の目玉が映るような〃ぞうすい〃が毎日の食事となり、学校では弁当泥棒が横行。盗られた弁当箱はからになると便所の中へ捨てられてしまった。(便所でかくれて食べるため)
青くやせこけた顔に眼だけが異様に光る。
飢えとひもじさから校庭(運動場)では集団暴行事件がひんぱんに起ったのである。
私達の学級は、入学当時三十四名の少人数であったが、戦火の拡大とともに田中地区に五百戸(現在の田中中と西町内に建設されていたが、戦後、福井市の大震災罹災世帯用として取り壊わされ移築された)と鹿原地区に百戸(現在の鹿原西)の軍需産業に働く人たちの大団地が建設されたのをはじめ、軍人、軍属世帯が農家の離れを借りて住みはじめたことなどによって一挙にふくれ上がり、五年の一学期が始まる頃には、さらに都会や市街地からの疎開者が加わって、各学年とも寿司ずめの二クラス編成となった。
志楽の地に生まれ育った生徒と、新しく他所から転校してきた生徒との間に、激しい争いが日夜起ったのもこの頃である。
ある日のこと、白い七つボタンの制服を着た二人(郷土出身の谷奥昭、森田茂(旧姓上西)の両氏)の海軍甲種飛行予科練習生が学校を訪れ、軍隊生活と戦況報告会が開かれた。
この時のりりしい予科練服姿と講演に感動したことは、今も忘れることはできない。
〃忠君愛国〃「天皇陛下とお国のためにぼくも予科練に入って敵艦を沈めてやろう--」
食糧増産
五年生。それは最も苦しい時代であった。
進級と同時に行った最初の作業は、教室の天井に張ってあったテックスを落すことであった。これは、屋根に落ちた焼夷弾が屋根を突き抜け天井に止まった場合、天井裏に火が早く回り消火活動のさまたげになるためで、五・六年生が棒倒しや肥桶かつぎに使う竹竿で下から突き上げ、全教室のテックスを破り落した。このほか空襲の防備策として爆撃目標となる白壁をコールタールで、まだらに塗りつぶしたりもした。後に天井が張られるまでの年月、いくらストーブを焚いてもぬくもらずガタガタふるえていたものである。
朝八時、二列縦隊に並んで上級生を先頭に草履ばきで登校。
校門を入ったところで隊列を整えてから奉安殿と二宮尊徳像に向って最敬礼。
八時半朝礼の鐘が鳴ると学年別に全員講堂に集合。「君が代」の斉唱の後、校長先生の教育勅語の朗読と訓話を聞き、教室に戻ると、われ先にと農具を取りに倉庫へ駆けて行き、すぐさま校庭に整列。
点呼を受けたのち開墾地めざして出発するのが日課となった。
くわ、かま、つるはし、すこっぷ……それに二人一組になって肥桶をかついだ幼い少年達の勤労作業隊が軍歌を合唱しながら、一糸乱れず行進するざまは、何ともいじらしくも頼もしい姿であった。
食糧欠乏、戦地の兵隊さんに少しでもおいしい物を食べていただき、ぼくたちは〃ほしがりません勝つまでは〃をモットーに食糧増産に励んでいたのである。 当時、開墾地として学校側が借りていたのは松尾、吉坂、鹿原、安岡、小倉、泉源寺などで、ほとんどが山あいの休耕畑で、かや刈り場であったり雑木林と化している荒地であった。一株掘り起こすのに小さな株でも最低三十分から一時間もかかった。
しかし、整地し大豆やイモをまき終ったあとの気分は壮快なもので、明日への希望をわかせてくれた。
また、日曜日には道路わきにヒマの種をまいたり、松根掘りやドングリ拾いに行ったものだが、これらは航空機の燃料や工業用・薬用油の原料になるのだと聞かされていた。
さて、三、四か月が過ぎていよいよ収穫期となり、かごをかついで開墾地へ行ってみると兎や野鳥、野ねずみに食い荒されており、大豆にいたっては、いくら山畑とはいえ種の量より少なかったのは誠に残念であった。
私が属していた青葉山部隊は、道のりも遠く急斜面の山道を登らなければ目的地に着けないなど、腹はへり人一倍疲れたが、それでも楽しいこともあった。山野には桑、ヤマイチゴ、クルミ、イチョウ、グミ、クリなどの木がたくさんありおいしい実をつけていたし、フキ、ワラビ、ゼンマイ、イタドリなどの山菜もたくさん採ることができた。
何といっても楽しかったことは、木綿糸と針金で作った釣道具で松尾寺の池のコイやフナを釣り上げ弁当がらに詰め込んで持ち帰り、塩焼きにして食べたことである。
戦時下の最も苦しかった時代に少年期を過ごした私達にとって、遊び道具といえば竹トンボ、紙・杉鉄砲、模型飛行機、パン(めんこ)程度であったが、戦争が悪化した四年生ごろからは、何も買うことはできなくなり、棒切れ(または青竹)を大小二本腰に差して遊び回るというありさまで、金属製のものは
兵器を造るための原料として全部供出させられてしまった。
学生服に付いていた金ボタンなども供出させられ、かわりにからつ製(または、木製)のものが配ばられたのである。
野球、バレーボー化 卓球、テニスなど外国で生まれた球技は一切禁止されていたので、もっぱら男子は長馬、相撲、木登り、魚とりなどを、女子は花つみ、あやとり、お手玉、石けりなど古来の遊びそのままであった。
一方、学校での勉強はほとんどなく晴れた日には前述の農作業を、雨が降れば精神統一のため座禅を組んだり、〃鬼畜米英〃〃撃ちてし止まむ〃など、とくに米・英国に対して憎悪の念と敵愾心をかりたてる標語を書いて、電柱や町内の掲示板に貼って回った。
しかし、このような学校生活にもかかわらず一学期の通知簿はもらった。
その成績評価(優、良上、良、良下、可の五段階)はたいへんなもので、たとえば農作業中まじめにやっていれば修身国語は優、木の根っこを、何個掘り起こせるかで体操の成績が決まる。種まきが上手にできないと理科が良下といった具合で、すべてが学校での生活態度で評価された。
五年生になってから終戦までの四か月半、学習なしの試験なしという学校生活を送れたのは、まったくうれしいかぎりであった。
一学期も終わろうとしていた頃には、日に何度となく敵機が来襲、空襲警報の連続で、サイレンが鳴り響くたびに防空頭巾をかぶり、農作業中の場合は草むらや木陰へ、授業中であれば校庭のイモ畑(当時、校庭の三分の二はイモ畑となっていた)の中へと避難し、目と耳を両手でふさいで地面に伏せた。
もう、勉強はもちろん農作業も安心してやれない。
戦争が末期を迎えた七月から八月にかけては、食糧不足による栄養失調によって登校すらできない生徒が続出。それでも夏休み返上でがんばったが、連日の空襲のため自宅待機の日が多くなった。
七月三十日の舞鶴空襲は本格的なもので、最初で最後の大規模なものであった。敵小型機(グラマン戦闘機)約二百三十機が午前と午後の二回にわたって飛来し、軍事施設を爆撃とくに湾内に停泊していた艦船はほとんど撃破されてしまったが、校区内への爆弾投下は皆無であった。
八月十五日終戦の日は自宅で迎えたが、その二日後の十七日全員登校。
講堂は、軍需物資の倉庫として使用されていたので、校庭に集まり校長先生からあらためて敗戦を知らされた。
先生と上級生の中から鳴咽とすすり泣きの声が起こり、私も青葉山をにらみつけながら大粒の涙を流した。
ただ、ひたすらに勝利を信じていたのに。
その後、学校内での混乱はなく、これまでの農作業中心からやっと開放され、本来の学業が少し受けられるようになり十一月から二桁の割り算、掛け算を習いはじめた。
先生の授業態度も極端に軟化し、何をしてもあまり叱られなくなったため、これまでの反動もあってか学習態度は悪く時間中に弁当を食べる者、ストーブで餅を焼いて食べる者、ビー玉をころがして遊ぶ者など気ままに過ごした。
学校給食
六年生。
終戦とともに教育内容も民主主義に基づいたものへと大きく変革された。
まず、私達を驚かせたのは、これまでの歴史、修身、地理の教科書は使用禁止、国語についても戦意高揚、神話などの記載か所は墨で消して使用したこと。また、新しく配られた教科書も新聞紙大の雑用紙に印刷されており、四つに折りたたんで、上、下と左側を切り離し、右側をとじると一冊の本になるという簡単なものであったことである。
さらに、ホームルームなるものがとり入れられたことであった。
議長を選んだり、何事もクラス全員の討議によってすべてを決めるという、まったく新しい学校生活にとまどったものである。
野球をやり始めたのもこの頃からで、イモ畑となっていた校庭も五月には整地され体操の時間や放課後には、ゴムボール(軟式テニスのボールと同じ)でよく遊んだ。
学習態度にもようやく落ち着きがみられるようになった七月頃には、四・五年当時八十名を越していた級友達も大半が故郷や両親のもとへと去り、五十名たらずに減少していた。
楽しかった戦後はじめての運動会も終り、秋も深まりをみせはじめた頃、志楽小学校でも進駐軍の援助物資による学校給食が実施されるようになり、私達六年生はあとわずかで卒業するため、下級生より早く食べさせてもらった。
食糧難を切り抜けてきた者にとっては、何よりもうれしく大歓声をあげて教室内をはしゃぎ回ったものである。
粉ミルク、砂糖、肉のかん詰……。
なかでも肉のかん詰を切り、各家庭から持ち寄った大根、白菜、ジャガイモと一緒に煮込んだ肉汁はほんとうにうまかった。(ご飯と汁入れ茶わんは各自持参)
しかし、イモやカボチャを主食としていた胃腸は、あまりの御馳走にびっくりしたのか、下痢、腹痛、じんましんを起こし、半数近くが寝込んでしまった。
また、米兵に品物をよくねだったものである。
朝来の吉野地区(現在、国立舞鶴工業高等専門学校)に戦時中、火薬廠があったため巡視のジープが毎日行き来していたが、そのジープが学校前を通るたびに、みんなが校門前に駆け出し口ぐちに 「ヘーイ ガムガム プレゼント」(おーいチューインガムをください)と敗戦の屈辱感を忘れたかのように呼びかけた。
戦地で死闘を続ける兵士に励ましの手紙を書いた同じ手で今度は「進駐軍の兵隊さんありがとう」と援助物資に対する感謝状を書き送ったものである。
一方、英語を知らない者は人にあらずとばかり、三学期にローマ字を習った。…
吉坂堡塁(舞鶴市吉坂) |
明治の遺産・吉坂堡塁探索
上安 福田照男
潮騒
だれかの「吉坂堡塁」を見たいとの声に成影務氏が早速行動開始した。登山ルートを探り砲台跡の確認など現地へ下見すること二回、地元の人にレクチャー受けるなど大変な準備をしていただきました。
吉坂堡塁は舞鶴市と高浜町にまたがる吉坂トンネルの上層にあり、トンネルを高浜町側へ抜けた六路地区に、国道からすぐ左に杉森神社がありここから登ります。この神社には全国に約二十本しかないといわれる貫重な国指定天然記念物「オハツキイチョウ」があります。
鳥居の右側から小さな土階段を上り、東へコースをとって行くと上と下の分かれ道があり、上の道へ登っていくと小規模な六路砲台跡です。Uターンして下の道へ行くとアップダウンしているが、落ち葉が積もった感触のよい歩きやすい山道へと続いています。途中前方には松尾寺の碧い屋根が木々の問から垣間見ることができ、素朴な日本の原風景を見ているような落ち着きを感じました。
道すがら山の木や植物を探索しながら、「スローツーリング」を楽しみ歩くこと約百分、昼前に目的の堡塁に到着です。ここは前庭のような日当たりのよい盆地で、落ち葉の絨毯を敷いた小さな自然公園の中で、「よろずは長閑にきこえむ」といった気分を味わいました。
本陣へは荒涼とした熊笹の中へ薮漕ぎしながら進み、石造りの関門を通りさらに進むと重厚な煉瓦造りの建物やコンクリート造りの弾庫が点在し、草木に埋もれた砲座も確認できました。
元の前庭で昼食を済ませ帰路は西へコースをとり、付属施設跡を見ながら広い道を下り、寒葵の花を探す人、天南星の赤い実を摘む人、人それぞれの初冬の日差しを浴び森林浴と酒落てみました。旧国道とT字交差し左へコースをとり、旧国道を東へ進めば山を切り開いた道の両側に、自然石がきちっと積まれ、苔むした石垣に時代の流れを見ることができました。
舞鶴には「明治の遺産」がたくさん残っています。これを生かして利用すればよいのか、風化し埋もれてもよいのか、読者の皆さんも機会があれば考えてみて下さい。これも舞鶴の資源です。
上安 福田照男
潮騒
だれかの「吉坂堡塁」を見たいとの声に成影務氏が早速行動開始した。登山ルートを探り砲台跡の確認など現地へ下見すること二回、地元の人にレクチャー受けるなど大変な準備をしていただきました。
吉坂堡塁は舞鶴市と高浜町にまたがる吉坂トンネルの上層にあり、トンネルを高浜町側へ抜けた六路地区に、国道からすぐ左に杉森神社がありここから登ります。この神社には全国に約二十本しかないといわれる貫重な国指定天然記念物「オハツキイチョウ」があります。
鳥居の右側から小さな土階段を上り、東へコースをとって行くと上と下の分かれ道があり、上の道へ登っていくと小規模な六路砲台跡です。Uターンして下の道へ行くとアップダウンしているが、落ち葉が積もった感触のよい歩きやすい山道へと続いています。途中前方には松尾寺の碧い屋根が木々の問から垣間見ることができ、素朴な日本の原風景を見ているような落ち着きを感じました。
道すがら山の木や植物を探索しながら、「スローツーリング」を楽しみ歩くこと約百分、昼前に目的の堡塁に到着です。ここは前庭のような日当たりのよい盆地で、落ち葉の絨毯を敷いた小さな自然公園の中で、「よろずは長閑にきこえむ」といった気分を味わいました。
本陣へは荒涼とした熊笹の中へ薮漕ぎしながら進み、石造りの関門を通りさらに進むと重厚な煉瓦造りの建物やコンクリート造りの弾庫が点在し、草木に埋もれた砲座も確認できました。
元の前庭で昼食を済ませ帰路は西へコースをとり、付属施設跡を見ながら広い道を下り、寒葵の花を探す人、天南星の赤い実を摘む人、人それぞれの初冬の日差しを浴び森林浴と酒落てみました。旧国道とT字交差し左へコースをとり、旧国道を東へ進めば山を切り開いた道の両側に、自然石がきちっと積まれ、苔むした石垣に時代の流れを見ることができました。
舞鶴には「明治の遺産」がたくさん残っています。これを生かして利用すればよいのか、風化し埋もれてもよいのか、読者の皆さんも機会があれば考えてみて下さい。これも舞鶴の資源です。
吉坂堡塁
舞鶴市市場から高浜町に至る国道に、吉坂峠がある。峠の東北方約一○○メートル、標高一八三メートルの高地に、吉坂付属堡塁が、さらに付属堡塁の北方約五○○メートル、標高二四二メートルの高地に、吉坂本堡塁がある。築造工事は明治三十三年七月着工、同三十五年十一月竣工した。本堡塁砲台の備砲は、一二センチカノン砲六門(初め鋼製九センチ臼砲六門)、付属堡塁砲台の備砲は、クルップ式三五口径中心軸一二センチカノン砲二門で、三十四年十二月、火砲の据え付けに着手し、三十五年七月完了した。本堡塁の目的は、内浦湾・高浜湾に上陸し、舞鶴に侵攻する敵を迎撃するための陸正面防御にあって、両湾より舞鶴に至る通路を制扼するように、堡塁を配置した。
一二カノン砲台は、二門を一砲座とし、砲座中心間隔を二○メートルとして、三砲座を構え、首線方向はSE六二度、射界一二○度である。各砲座間に横墻を設けて、その下部に砲側庫を構築した。更に第三砲座左側に、翼墻を設けて、その下を砲側庫とした。コンクリート胸墻の前庭は、下り傾斜となっており、二五メートル先は空壕である。空壕の左端からは、機関銃射撃ができるように、側防施設が作られてある。砲台長位置は、側防施設と、第三砲座のほぼ中間に設けてある。第一および第二砲座の後方約二○メートルに、地下掩蔽部の入口がある。掩蔽部の大きさは幅二四メートル、奥行一○メートルである。
本堡塁の付属建造物として、砲兵庫・弾廠・兵舎二棟・監守衛舎・火薬支庫・掩蔽部・貯水所・倉庫二棟・厠が設けられ、また付属堡塁には、番人舎・砲兵庫・弾廠・砲側庫・掩蔽部・貯水所・厠が設けられた。糧食庫・炊事場・浴室・調理所。天然貯水所は戦備工事として、各その建設位置を予定しおき、日露戦争突入の明治三十七年六月これを実施した。
付属塗塁砲台の一二カノン砲二門は、一門一砲座とし、中間に横墻を置き、横墻の下は地下砲側庫である。胸墻はコンクリート造で、高さは一・四メートルである。首線方向SE七二度、射界は一二○度である。胸墻前庭は下り傾斜をなし、標高一八二メートルの一線に、側防機関を配置するように作ってある。第二砲座の左後方に、地下掩蔽部と貯水所を設け、その他番人舎・砲具庫・弾廠・厠を配置し、糧食庫・炊事場・浴室・調理所・天然貯水所を戦備工事として実施した(図)。
舞鶴市市場から高浜町に至る国道に、吉坂峠がある。峠の東北方約一○○メートル、標高一八三メートルの高地に、吉坂付属堡塁が、さらに付属堡塁の北方約五○○メートル、標高二四二メートルの高地に、吉坂本堡塁がある。築造工事は明治三十三年七月着工、同三十五年十一月竣工した。本堡塁砲台の備砲は、一二センチカノン砲六門(初め鋼製九センチ臼砲六門)、付属堡塁砲台の備砲は、クルップ式三五口径中心軸一二センチカノン砲二門で、三十四年十二月、火砲の据え付けに着手し、三十五年七月完了した。本堡塁の目的は、内浦湾・高浜湾に上陸し、舞鶴に侵攻する敵を迎撃するための陸正面防御にあって、両湾より舞鶴に至る通路を制扼するように、堡塁を配置した。
一二カノン砲台は、二門を一砲座とし、砲座中心間隔を二○メートルとして、三砲座を構え、首線方向はSE六二度、射界一二○度である。各砲座間に横墻を設けて、その下部に砲側庫を構築した。更に第三砲座左側に、翼墻を設けて、その下を砲側庫とした。コンクリート胸墻の前庭は、下り傾斜となっており、二五メートル先は空壕である。空壕の左端からは、機関銃射撃ができるように、側防施設が作られてある。砲台長位置は、側防施設と、第三砲座のほぼ中間に設けてある。第一および第二砲座の後方約二○メートルに、地下掩蔽部の入口がある。掩蔽部の大きさは幅二四メートル、奥行一○メートルである。
本堡塁の付属建造物として、砲兵庫・弾廠・兵舎二棟・監守衛舎・火薬支庫・掩蔽部・貯水所・倉庫二棟・厠が設けられ、また付属堡塁には、番人舎・砲兵庫・弾廠・砲側庫・掩蔽部・貯水所・厠が設けられた。糧食庫・炊事場・浴室・調理所。天然貯水所は戦備工事として、各その建設位置を予定しおき、日露戦争突入の明治三十七年六月これを実施した。
付属塗塁砲台の一二カノン砲二門は、一門一砲座とし、中間に横墻を置き、横墻の下は地下砲側庫である。胸墻はコンクリート造で、高さは一・四メートルである。首線方向SE七二度、射界は一二○度である。胸墻前庭は下り傾斜をなし、標高一八二メートルの一線に、側防機関を配置するように作ってある。第二砲座の左後方に、地下掩蔽部と貯水所を設け、その他番人舎・砲具庫・弾廠・厠を配置し、糧食庫・炊事場・浴室・調理所・天然貯水所を戦備工事として実施した(図)。
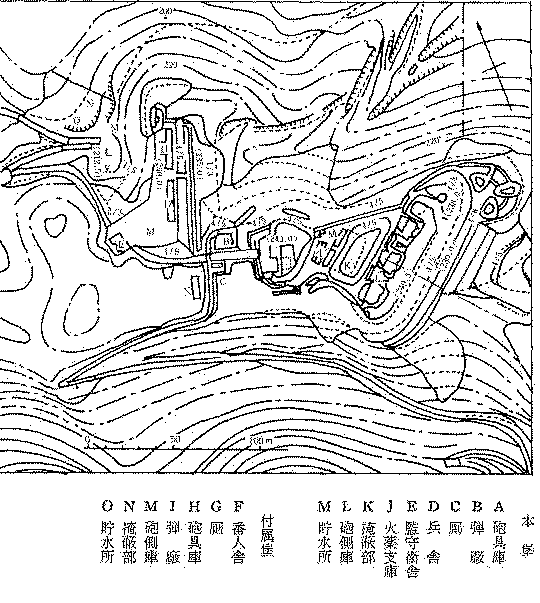
吉坂番所(舞鶴市吉坂) |
吉坂峠番所 (吉坂)
吉坂は若狭街道吉坂峠の峠下集落であり、青葉山麓の松尾寺への参詣道に当たる交通上の要地でもある。くれ谷、中谷、下の谷などがあり、これらの谷に家屋が点在している。
中世志楽荘春日部村の地である。吉坂村安永名内の田地が当地にあった西願寺に寄進されたと、承久元年(一二一九年)安永吉永田地寄進状写(金剛院文書)に記されている。
近世に入り、慶長検地郷村帳に、高一七一、三四石吉坂村とあり、土目録では田一五三石余、畑一七石余、運上として渋柿一斗、端折紙三束などが記される。延享三年(一七四六年)、郡中高常付覚によれば農家戸数三七、丹後、若狭両国の国境であったので領地番所があり、小数の武士、足軽がいたとある。
若狭街道の要所であり、田辺藩としても、小浜藩、高浜城主が常に、田中城、泉源寺城、鹿原城を攻めほろぼしたいとうかがっているので、番所で行ききするものに目を光らせていなくてはならなかった。
正徳三年(一七一三年)に幕府の奉行から出された掟書によれば
一、関所を出入りする者、笠や帽子をとらす
一、乗物で出入りする者、戸を開かせること
-、関所より外に出る女は、くわしく証文と引き合わせて通す。なお乗物で出る女は、番所の女
を出して細部調べさせる事
一、けが人、死人、あやしき者は、証文がなければ通さぬこと
一、幕府の人々、諸大名の行き来は、前から連絡があった場合はそのまま通す
もしあやしいことがある場合は、どんな人でも取調べること
一つの領地の境に番所が立っていることは、住民にとって、どれだけ不便で不自由なことだっ
たか……。
私はこの間、吉坂の古老の話によると、この番所はつい六年前まであったのだが、古くなり離れ部屋を作るためにつぶしたとのこと。幼いときに遊びに行ったということだ。広いものでなく間口三間、奥行二間の建物で、御目箱、すずり箱、寄棒のたてかけるところ、刀たてなどがあったとのこと。もう少し早く聞いておれば写真でも撮っておくのだったとくやまれた。
吉坂は若狭街道吉坂峠の峠下集落であり、青葉山麓の松尾寺への参詣道に当たる交通上の要地でもある。くれ谷、中谷、下の谷などがあり、これらの谷に家屋が点在している。
中世志楽荘春日部村の地である。吉坂村安永名内の田地が当地にあった西願寺に寄進されたと、承久元年(一二一九年)安永吉永田地寄進状写(金剛院文書)に記されている。
近世に入り、慶長検地郷村帳に、高一七一、三四石吉坂村とあり、土目録では田一五三石余、畑一七石余、運上として渋柿一斗、端折紙三束などが記される。延享三年(一七四六年)、郡中高常付覚によれば農家戸数三七、丹後、若狭両国の国境であったので領地番所があり、小数の武士、足軽がいたとある。
若狭街道の要所であり、田辺藩としても、小浜藩、高浜城主が常に、田中城、泉源寺城、鹿原城を攻めほろぼしたいとうかがっているので、番所で行ききするものに目を光らせていなくてはならなかった。
正徳三年(一七一三年)に幕府の奉行から出された掟書によれば
一、関所を出入りする者、笠や帽子をとらす
一、乗物で出入りする者、戸を開かせること
-、関所より外に出る女は、くわしく証文と引き合わせて通す。なお乗物で出る女は、番所の女
を出して細部調べさせる事
一、けが人、死人、あやしき者は、証文がなければ通さぬこと
一、幕府の人々、諸大名の行き来は、前から連絡があった場合はそのまま通す
もしあやしいことがある場合は、どんな人でも取調べること
一つの領地の境に番所が立っていることは、住民にとって、どれだけ不便で不自由なことだっ
たか……。
私はこの間、吉坂の古老の話によると、この番所はつい六年前まであったのだが、古くなり離れ部屋を作るためにつぶしたとのこと。幼いときに遊びに行ったということだ。広いものでなく間口三間、奥行二間の建物で、御目箱、すずり箱、寄棒のたてかけるところ、刀たてなどがあったとのこと。もう少し早く聞いておれば写真でも撮っておくのだったとくやまれた。
吉坂領境番所
吉坂番所が吉坂村内に在ることは「田辺府志」などで判っていたが、その場所については最近まで判らなかった。
場所は白鬚神社参道を入った右側、山添義秀氏宅の離れが建っている場所である。番所の建物は木造(杉材)藁葺き平屋建て、屋根は異常に高く造られていた。
建物は、間口六間、奥行き二間。間取りは、居間二つと土間からなり、中の間には炉が設けられていた。炉の部屋の天井は竹を編んだ天井であった。
窓は、無双窓(引戸を引いて閉じると、すき間が入れ違って一面の板張りの様になる窓)と突き上窓(のぞき窓ならん)があった。
板戸には、「御番所破るべからず」と墨書したものがあったという。(山添義秀氏より)この番所には常時足軽二人が居て、通行人の監視と荷物の移出入を取り締まっていた様で、正徳五年乙未十二月の御書上によると、
「足軽二人宛差遣申候、尤往還之男女、其外改尋不仕候、領分境故、右之通り申付置候、御高札掟書等も無御座候 以上」
とある。田辺藩では番所を通る通行人には、余り厳しく取り締まっていなかった様である。
さて、吉坂の人々が江戸時代どんな暮らしをしていたのか。順礼記に記しており、大変興味あるので記述する。
「扨、此辺の人は、よく稼ぐ所なり、此所で小休しをして茶店にしばらく休んでいる所に、戻り駕籠が来て申故、「お客さん方、安くいたします」と申故、見れば一人は男なり、一人は女なり、是れを見れば此辺は、いかけ(夫婦ならん)で働くとあい見える。
扨、休んでいると、外の人が値段きはめて、夫より乗りましたが、片棒は亭主後がたわ女なり、扨々珍らしき駕籠を見ました。
小休所の茶店で雪が三月に山々にありしを見た故、尋ねたならば、茶店の亭主が申事には、「今年は極月(文政二年十二月)の廿八日に降りましたが雪が一丈二尺ばかりで御座いましたが、又、夫より正月二日より降りだして一丈八尺の雪で御座いました。一尺や二尺の雪は珍らしきことはない」と申候。
夫より内(家)を見れば志き(敷居)の上下に柱がつはり当(つっぱり)にしてある。
尚又、家の建て方は、いづれも皆々棟がけんそにしてある。其の入口は雪よけがしてある。
そのかたち(絵参照)、雪よけ、見れば、かくのごとに棟が高い。此所へ卯の三月廿四日小休いたし見れば、かくのごとく、うそでなし、参りて志れる」
ここに書いている夫婦らしき駕籠屋は、松尾寺へ参詣する順礼者を運ぶ仕事をしていたのであろう。それにしても、松尾の山道を女が後棒で駕籠をかつぐとはよほど昔の女の人は屈強であり、吉坂の人々はよく働いたと見える。
又、この辺りは、冬にはよく雪が降る所で、一尺や二尺(三十~六十センチ)の雪は珍しくなく、一丈二尺から一丈八尺(約三・六~五・四メートル)の雪が降ったと書いているが、これは少し大げさに申している様に見受けられる。
文禄二年(一五九三)二月に貝原益軒が松尾寺へ詣でた時に書かれた「西北紀行」によると、松尾寺の積雪について次の様に述べている。
「この辺、冬に雪ふかし観音堂(松尾寺本尊)の前の高さ七尺(約二・一メートル)の石燈籠あり、雪に埋もれ見えざる事多し、又、石燈篭の上に二尺、三尺(六十~九十センチ)も降り積ることもあり」と書いている様に、江戸時代この辺りでは二メートル程度の雪は普通で、時には三メートルに及ぶ大雪も降ったことが判る。
この観音堂前に立っていた石燈籠は、今は無くなっている。
この様に、この辺りの人々は昔から生活の智恵として大雪から家を守るため屋根の勾配をつけたり、家の周囲に雪除けを立てかけて冬を過ごしていたと見える。当地に近年まで遺っていた番所の建物もやはり、屋根が高く勾配のきつい建物であった(山添氏の話)という。
吉坂番所が吉坂村内に在ることは「田辺府志」などで判っていたが、その場所については最近まで判らなかった。
場所は白鬚神社参道を入った右側、山添義秀氏宅の離れが建っている場所である。番所の建物は木造(杉材)藁葺き平屋建て、屋根は異常に高く造られていた。
建物は、間口六間、奥行き二間。間取りは、居間二つと土間からなり、中の間には炉が設けられていた。炉の部屋の天井は竹を編んだ天井であった。
窓は、無双窓(引戸を引いて閉じると、すき間が入れ違って一面の板張りの様になる窓)と突き上窓(のぞき窓ならん)があった。
板戸には、「御番所破るべからず」と墨書したものがあったという。(山添義秀氏より)この番所には常時足軽二人が居て、通行人の監視と荷物の移出入を取り締まっていた様で、正徳五年乙未十二月の御書上によると、
「足軽二人宛差遣申候、尤往還之男女、其外改尋不仕候、領分境故、右之通り申付置候、御高札掟書等も無御座候 以上」
とある。田辺藩では番所を通る通行人には、余り厳しく取り締まっていなかった様である。
さて、吉坂の人々が江戸時代どんな暮らしをしていたのか。順礼記に記しており、大変興味あるので記述する。
「扨、此辺の人は、よく稼ぐ所なり、此所で小休しをして茶店にしばらく休んでいる所に、戻り駕籠が来て申故、「お客さん方、安くいたします」と申故、見れば一人は男なり、一人は女なり、是れを見れば此辺は、いかけ(夫婦ならん)で働くとあい見える。
扨、休んでいると、外の人が値段きはめて、夫より乗りましたが、片棒は亭主後がたわ女なり、扨々珍らしき駕籠を見ました。
小休所の茶店で雪が三月に山々にありしを見た故、尋ねたならば、茶店の亭主が申事には、「今年は極月(文政二年十二月)の廿八日に降りましたが雪が一丈二尺ばかりで御座いましたが、又、夫より正月二日より降りだして一丈八尺の雪で御座いました。一尺や二尺の雪は珍らしきことはない」と申候。
夫より内(家)を見れば志き(敷居)の上下に柱がつはり当(つっぱり)にしてある。
尚又、家の建て方は、いづれも皆々棟がけんそにしてある。其の入口は雪よけがしてある。
そのかたち(絵参照)、雪よけ、見れば、かくのごとに棟が高い。此所へ卯の三月廿四日小休いたし見れば、かくのごとく、うそでなし、参りて志れる」
ここに書いている夫婦らしき駕籠屋は、松尾寺へ参詣する順礼者を運ぶ仕事をしていたのであろう。それにしても、松尾の山道を女が後棒で駕籠をかつぐとはよほど昔の女の人は屈強であり、吉坂の人々はよく働いたと見える。
又、この辺りは、冬にはよく雪が降る所で、一尺や二尺(三十~六十センチ)の雪は珍しくなく、一丈二尺から一丈八尺(約三・六~五・四メートル)の雪が降ったと書いているが、これは少し大げさに申している様に見受けられる。
文禄二年(一五九三)二月に貝原益軒が松尾寺へ詣でた時に書かれた「西北紀行」によると、松尾寺の積雪について次の様に述べている。
「この辺、冬に雪ふかし観音堂(松尾寺本尊)の前の高さ七尺(約二・一メートル)の石燈籠あり、雪に埋もれ見えざる事多し、又、石燈篭の上に二尺、三尺(六十~九十センチ)も降り積ることもあり」と書いている様に、江戸時代この辺りでは二メートル程度の雪は普通で、時には三メートルに及ぶ大雪も降ったことが判る。
この観音堂前に立っていた石燈籠は、今は無くなっている。
この様に、この辺りの人々は昔から生活の智恵として大雪から家を守るため屋根の勾配をつけたり、家の周囲に雪除けを立てかけて冬を過ごしていたと見える。当地に近年まで遺っていた番所の建物もやはり、屋根が高く勾配のきつい建物であった(山添氏の話)という。
国道27号線の冬場の難所でよく雪による事故が起こり、事故車両を取り除く間の何時間から何日は通行止めとなる。
丹後の伝説33 メニュー |
|---|
資料編の索引
| あ | い | う | え | お |
| か | き | く | け | こ |
| さ | し | す | せ | そ |
| た | ち | つ | て | と |
| な | に | ぬ | ね | の |
| は | ひ | ふ | へ | ほ |
| ま | み | む | め | も |
| や | ゆ | よ | ||
| ら | り | る | れ | ろ |
| わ | ||||
市町別 |
| 市町別 |
|---|
| 市町別 |