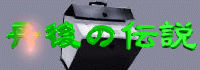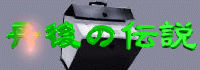丹後の伝説:61集
−旧網野町の伝説(一) −
 お探しの情報はほかのページにもあるかも知れません。ここから探索してください。超強力サーチエンジンをお試し下さい。 お探しの情報はほかのページにもあるかも知れません。ここから探索してください。超強力サーチエンジンをお試し下さい。
浦島伝説
『丹後国竹野郡誌』
 浦鳥太郎宅跡並に之に関する伝説遺跡 浦鳥太郎宅跡並に之に関する伝説遺跡
宅跡 字網野銚子山の東麓畑中にあり、古き榎木一本あり、口碑に浦島太郎の皺を投げ付けたる木なりといふ、
(宮津府志)網野郷 中略 浦島子の宅址あり
(丹後旧事記)水江能野長者日下部曾却善次は浦島太郎長男にて、允恭天皇の御代の臣下なり、此善次に子なし、天に祈りて男子を得る是所謂浦嶋児なり、雄略天皇二十二年仙亀に引れて蓬莱宮に到る、淳和天皇二年再旧里に帰て死す、其年間三百四十七年、風土記、日本紀等の勅じょうの書にあらはす名所部神祇部を見るぺし
(大日本地名辞書)
略)
『丹後の民話』
 浦の嶋子 浦の嶋子
むかし、ずっと昔、今の旧網野村が松原村と福田村という二つの村にわかれていた頃の話です。
ここに水の江の長者とよばれていた日下部氏の家があり、その頃、丹波(たにわ)(今の丹後も丹波も一つであり丹波国(たにわのくに)といっていた)の北岸でこの家は二十七か村の支配を許されていたといいます。屋敷は今の銚子山古墳のある丘陵の地つづきにありました。
この水の江の長者、日下部曽却善次の代に夫婦の間に子供がなく、なんとかして子宝に恵まれたいと百日の祈願をして毎日、天に祈りました。そしてちょうど満願の夜、夫婦は不思議に同じ夢を見たのです。神の姿があらわれて、二人の心からの願いを聞き届けよう。明朝、福島まで来いというお告げを聞いたのです。
翌朝、二人は喜んで福島まで出かけて見ますと、生まれたばかりの赤子が布団にくるんで置かれていました。さっそく抱いて帰り嶋子と名ずけて大切に育てました。元気ですくすくと成長した嶋子は、釣りが好きで、毎日釣竿を肩に出かけたのです。
そんなある日、嶋子が福島の白鷺が鼻という海辺で釣りをしていると、たいへん美しい婦人に出会い、それが乙姫様であることがわかりました。声をかけられた嶋子は一目で感じてしまい、二人は夫婦の約束をしたのです。そして、両親のいる竜宮城に行こうと、乙姫様のたってのすすめにより、二人は小舟で出かけました。
竜宮城に着いてみると、乙姫様の両親はじめ多くの人々に迎えられ、毎日毎日手厚いもてなしをうけ、楽しい日々をおくっていましたので、またたくうちに三年の月日が流れてしまいました。
やがて嶋子は、両親のいる故郷のことを思い出す日が多くなり、打ち沈んでいる姿を見かけた乙姫様は、嶋子の心を察して帰ることを認め、
「もし再びここへおいでになりたくなったら、いつでも来て下さい。お別れにこの手箱を差し上げます。再びおいで下さるお心持ちがあるなら、決して中をおあけなさいますな」と言って、美しい玉ぐしげを嶋子に渡しました。
嶋子は、そのほか数々のおみやげ物をいただき、舟に乗ってなつかしい網野の浜へ帰ってきました。屋敷から二キロほど離れた万畳浜へ着いたのです。嶋子は早く両親に逢いたいものと、わが家への道を急ぎました。道で出会う顔は、どれもみな知らない人ばかり。両親の名を言って尋ねてみても誰一人知っている者はありません。やっと屋敷まで着いて見ると、これはどうしたことでしょう。もとの家はなく、屋敷跡は雑草が茂り、一面の荒野原になっているのです。わずか三年と思ったのですが、竜宮での一年は、人間界の何十年にもなるのですから仕方のないことです。
嶋子は、なげき悲しみ途方にくれていました。もしやこの際、乙姫様からもらった、この玉くしげを開けてみれば、ひょっとして昔にさかのぼり、故郷があらわれて両親にも逢えるかも知れないと思い、ついにその箱のふたを開けてしまったのです。
するとどうでしょう。中から白い煙が立ちのぼったと思えば、たちまち嶋子の髪は白くなり、顔にはしわができて、すっかりおじいさんになってしまいました。あまりのことに驚いた嶋子は、思わず自分の頬のしわをちぎっては榎に投げつけたということです。
それから、とても長い年月がたった、ある日、浅茂川の海岸に大亀が流れついたのです。村人が一生懸命に介抱しましたが、ついに生きかえることはありませんでした。
人々は、乙姫様が亀に姿をかえて、嶋子あいたさに竜宮からやって来たにちがいないと、島児神社のかたわらに「霊亀の塚」をたて手厚く葬ってやったということです。
又、嶋子がしわを投げつけたという榎は「しわ榎」といわれ、今でも飄然と立っています。 (俵野・井上正一様より)
『ふるさとのむかしむかし』
 浦島子の出生地 浦島子の出生地
網野町は浦島子の出生地であり、乙姫さんと初めて逢った土地という伝承があります。
島子の家には子がなかったので、両親が天に祈って福島で島子を授かったいいます。また関係のある神社も多く、島子を祀った網野神社と島児神社、乙姫さんを祀った福島、それに島子の父をはじめ一族を祀った下岡の六神社があります。
島子の屋敷跡もあり、乙姫さんからもらった玉手箱を開いて白髪の老人となった榎の元の伝承で有名な「しわ榎」もあります。(竹野郡誌))
『網野町誌』
 浦島伝説 浦島伝説
『浦島さん』の伝承は丹後だけのものではなく、全国の人々に知られた「昔話」である。したがってその内容について述べることは略す。この名高い伝説の原典は、和銅六年(七一三)から霊亀元年(七一五)の二年間に撰進されたという『丹後国風土記』である。この『風土記』は全文のうち一部分が残るのみだから、正しくは原典は『丹後国風土記逸文』のなかに記されていることになる。(続いて養老四年(七二〇)に撰述された『日本書紀』に、簡略な浦島伝説の記載があり、さらに『万葉集』第九巻には、高橋虫麻呂が浦島をうたった「長歌」が載せられている)さて、「逸文」のなかの浦島伝説は、もと丹後の国司であった伊預部馬養連が記録したことになっている。
馬養は漢文学者だったので、このとき中国の神仙思想をたくみにプラスしたといわれるが、彼が丹後に赴任していたのは七世紀末ころと推定されているので、浦島伝説が語られはじめたのは六世紀、またはそれ以前のことだったと思われる。
そうかんがえるとこの物語は、朝鮮・中国から伝えられてきたものか、または黒潮が運んできた「夢」であった可能性も強まる。いずれにせよ海に生きる人々が一度は空想したであろうロマンが結晶したもので、それゆえ同類の説話が国内はもちろん、世界の各地に広がっていても不思議とはいえない。
たまたま丹後では漁民の首領のような存在であった氏族の日下部氏が、始祖伝承として浦島伝説を取り入れ、それが『丹後国風上記逸文』に姿をとどめたと推測されている。
当町内では『浦島さん』は網野神社に祀られ、また下岡六神社では浦島子とその一族が、浅茂川では島児神社に浦島子が祭祀され、さらに福島の福島神社は神女(いわゆるオトヒメさん)が祭神である。
補注 与謝郡伊根町字本庄にも、浦島子を祀る有名な宇良神社があって、同町字新井の新井崎神社には「徐福」が祀られている。共に不老長生の常世願望で一致した伝承を持つ。
『網野町誌』
コラム
三重県伊勢・志摩地方の民話に、浦島伝説によく似た伝説があり、また丹後から伊勢への海人・海女の大移動したことが語られているという。大移動は一五〇〇年ほども昔のことで、先述の豊受神を丹後から伊勢外宮へ遷祀したことと関係があるとする見方がある。五世紀の初めごろ、気候変動があって日本海は寒さがきびしく、特に潜水する海人の漁法は困難となり、温暖な南海を目指して移動したものらしい。丹後から播磨・大阪湾から紀伊に出て志摩へ到達したというのだ。もとより伊勢・志摩には先住の海人がいたので、さまざまな争いが生じた。『紀』応神記三年条の「処処の海人さばめきて命に従はず」、という記事は右の事実を書いたものかともいわれる。また、以来、伊勢神宮の供え物の主体が、アワビとなったのだともいう。
『ふるさとのむかしむかし』
 節分に鬼やらいを行わない家 節分に鬼やらいを行わない家
それは、だいぶん昔の話です。何代か前の島の足達家の主人が、京都から帰る途中、道に迷い、陽は暮れるし、あせればあせるほど、山の中に迷いこみ、もはや歩く気力もなくなり、とうとう山の中で倒れておりました。
夜もふけてきてから、どこからか鬼があらわれて、
「おいこんな所に、お前は何をしとる」と問うので、おそるおそる、
「道に迷ってこんな山中に入りこみました。おなかがすいて、もうどうにもなりません」と答えますと、
「そうか、それはかわいそうだ。それではおれが、送ってやろう。目を閉じ、おれがよいというまで開けてはならんぞ」といって、目かくしをされ、しばらくすると、
「そら帰ったぞ」と言うので 目かくしを取ると、そこは自分の家の前でありました。
このような不思議なことがありましたのでその後、足達家一族は節分の夜の鬼やらい(鬼は外)はしないということです。 (原話 島津 糸井芳蔵)
 節分の晩に豆まきはしない 節分の晩に豆まきはしない
むかし、私の家の祖先さまが、宮津の殿さまの言いつけで京都へお使いに行きました。
京都から帰る途中、道に迷ってしまいました。日は暮れてしまって困っていました。その日は節分
の日だったそうです。
すると、どこからか、ひゃっかけ(鬼)が出てきて、
「どこへ行くのか」と聞きました。
「三津へ帰りたいのだが、道がわからなくなって困っています」と言うと、ひゃっかけは、
「節分の晩に豆まきをするな、そうしたら送ってやる……さあ、わしの背中に負われて 目をつむれ。
もうよいと言うまで、ぜったいに目をあけるな」と言いました。
言われたとうりにして、しばらくすると、
「目をあけ」と言うから、開けたらいつのまにか三津の自分の家に着いていました。
それで先祖さまは
「節分の晩に豆まきしてはいけな」 と、自分の子供たちにも言い伝えました。それで私の家は、豆まきがしたくても、できないのだそうです。 (原話 三津 末次みな子)
※追って、三津には末次という姓の家が十五軒以上もありますが、現在でも節分の晩に豆まきをする家と、しない家とはっきりわかれています。
『ふるさとのむかしむかし』
 黄金埋蔵の伝承 黄金埋蔵の伝承
切畑区のうち、郷地区に近いあたりに、岩倉という小字があり、寺谷という谷があります。ここは今郷区にある岩倉山明光寺の元地だと言伝えています。
何年か前、この附近で、田圃の整地を行った際、土器が出土し、中には黒色土の詰った土器を附近の川で洗ったところ、少し下流の川水が一面に朱色に染ったと言い伝えています。その後、この地区の基盤整理をした人の話によると、仏具と思われる陶器の破片が、数多く出土したとも聞いています。
附近に白つつじの株と、石地蔵があるが、黄金の鳥の鳴いたという話も聞かず、附近を大がかりな整地されたこともないので、この地に何か宝物が埋められているかも知れないという老人もあるが、今の若い人たちは耳もかしません。
(原話 切畑区 長寿会代表)
○
 故立野啓蔵氏談。字郷にはいつの頃からともしれず、こんな諺が口伝えに伝えられています。
いけば左 もどれば左 朝日夕日さす
つはの木のもと 黄金千両 縄千束
これだけでは、いっこうに意味がわからないのですが、実はこの地に戦いがあって 明光寺は亡ぼされてしまいました。その時に、財宝を土中に埋めこまれたのだといいます。この諺はその埋められた場所をこのような形で後世に残したものだといいますが、その場所を掘りあてた人は今に至るも無いとのことです。
また切畑のある人の話では、諺はこれとすこしちがって
岩倉地蔵から西へ一町 黄金千両
と伝えられているそうです。
後藤宇右衛門談。私の聞いたのでは、右の諺の終りの方「縄千束」ではなく「わらび縄千束」と聞 いています。
「往けば左、戻れば左」という土地はとこを差すのか、どうもよくわかりません。
「朝日 タ日さす」地とは、東西に開けた谷間か、あるいは高山でも指すのでしょうか、「つわの木」もようわかりませんが、榎だとも、柳の木だとも言われています。
切畑ではこれを、「椿の木に黄金の鳥がひとつがい、金が七つぼ、七通り」と言う人もあって、この黄金の鳥が、幾人かの夢枕にあらわれて鳴いた夢を見たら掘り出してもよいと言い伝えています。
その地はもと古いお寺のあった岩倉という土地だということですが、そのような夢を見た人もなく、掘ったこともありません。
『ふるさとのむかしむかし』
 千匹狼 千匹狼(とねんが婆の話)
ずっとむかし、ある日の夕暮ごろ 六部さんが旅につかれて、生野内(網野町)のあたりまでたどりつきました。
そのうち小字竹倉部(たけくらべ)の森のかたわらにある小さな祠を見つけ今宵の宿と定めました。
旅のつかれも出て、すぐに寝入りましたが、夜ふけてから、なにか獣のほえる声に目をさまし、もしもここまでおそって来たら、どうしてそれを避けようか、と考えているうちに、その叫び声は、だんだん数が多くなり、今にもここへ飛びこんできそうな気配なので、六部は、あわてて、そばにあった榎によじ登った。
くらやみを透してよく見ると、数えきれないほどの多くの狼がむらがって、榎の木の本に押しよせ、六部めがけて、ものすごくほえています。
狼の上に別の狼が乗り、その上に他の狼と、丈継ぎして、六部の足元にしだいに接近してきた。この時、頭らしい狼が、
「もう一匹足らん、郷の石田のとねんが婆あをすぐ呼んでこい」と命じると、一匹が飛んで行った。
しばらくすると、その狼が、別の狼を連れてやってきた。それが一ばん上の狼の背に飛びあがり、今にも六部の足にかみつこうとする気配です。六部は持っていた短刀をふりおろし一番上の狼に切りつけました。
すると、丈継ぎしていた狼が、ばたばたと崩れ落ち、取巻きの狼がいっそう強く、ものすごくほえたてた。しかし、どうしたわけか、しばらくすると、次つぎと逃げ散ってゆきました。
榎の上にしがみついていた六部は生きる気もせず、やがて明け方近くなったので、木から降りましたが、あたりは静かで昨夜の出来ごとは、まったく悪夢のような恐ろしい出来ごとでした。
それにしても不思議なことだ。石田のとねんが婆あとは何者か、ともかくこれから出かけて村の人に尋ねてみようと、石田までやって来ました。
近くのある一軒家へ立寄ってみると、どうやら家の中は取り込んでいるらしい。聞いてみると、この家の老婆がゆうべ何者かに斬られたのだという。ますます不思議に思い、「わしは廻国の六部であって少々呪術も心得ているから、ご希望なら治して進ぜよう」と言い、家人の辞退をも聞かんふりで病人の居間へはいった。
すると、ものすごい顔の老婆がふせて、うなっている。
六部は数珠を手に呪文を唱えて悪魔退散を祈ると、老婆の顔はみるまに獣の相に変り、眼をいからせ、口から火を吹いて 今にも六部に飛びかかる身がまえするので、六部は手にした数珠をえいと投げつけた。
すると、白雲が舞いあがり、老婆はその雲に乗って戌(西北)の空へ飛び去りました。
まったくあっと思う間のできごとで 家人や、集ってきた近所の者たち一同は、この恐ろしい出来ごとに、恐れおののいて声を出す者もありません。
そこで六部は、昨夜の狼の事件を物語り、
「このお家も古びたお家だが、何をやって暮していられるか、またこれまで何か変ったことはなかっ
たでしょうか」と尋ねると、この家のおやじが言うには
「私の家はもとこの向いの和田垣に住っておりまして、その当時はかなりの裕福に暮していたのですが、ここへ移ってから暮しも苦しくなり、妻にも先立たれて、長らくやもめで暮しておりました。ところが先年、どこからか、今の婆あがやってきて
なにくれとなく まめまめしくよく働き、夜業にはこう薬をつくって、あちこち売り歩き、などいたしました。そのこう薬がよく効くので、売れゆきもよく、そのため暮しむきも楽になって悦んでおりました。
ところが昨夕、誰かに呼び出されて 出て行きましたが、何者かに斬られ、血まみれになって、ころげ帰りました。そこですぐ婆あの作ったこう薬をつけてやりました。その時あなた様がおい出なされたわけで、何とも恐ろしいことばかりで……」と語りました。
おやじがぜひにと頼むので、六部はしばらくこの家に泊っていましたが、さいわい隣村の生野内に大慈寺という無住のお寺があったので そこへ移り住むようになったといいます。
(原話 郷 後藤宇右衛門)
註 「六部さん」とは書写した法華経を六十六カ所の霊地に一部ずつ納める目的で、諸国の社寺を遍歴する巡礼のことで、六部とは、六十六部の略です。
 遊部落の観音さま 遊部落の観音さま
むかし、有名な太鼓浜に近い遊部落のある家の主婦が、目をわずらっていましたが、ある日の朝、まだ暗いうちに浜辺に行き、浜を見おろしていました。するとなにか人影が見えるので、よく見ると、毬をついたり、舞をまったりしている人があります。
この朝早くから、へんなこともあるものだと、すぐ引き返して 家族や、近所の者にそのことを知らせました。
「目の悪いお前が、何かの見ちがいだろう」と言って皆本当にしてくれない。けれどもあまりしつこく言うのて ともかく行ってみようと、近所の者といっしょに浜辺に来てみると、もうその時は朝明けでしたが、浜辺には彼女の言うような人影は見あたらず、ただ一つ何かを見付けたので、近付いてよく見ると、それは観音の像でありました。
なぜこんな場所に置かれているのか、不思議なことだと話し合いましたが、相談の結果、大切に持ち帰って さっそくお堂を建ててお祀りしました。
その後、その目のわるい主婦は、毎朝日参して居るうちに、日一日と驚くほどよくなりました。そのことを伝え聞いた人々がお諸リするようになり、しだいに近郷近在の目の悪い人たちが、ぞくぞくお詣リしてご利益をうけるようになり、誰から始めたともなく祈願のしるしに、手毬を奉納しております。
目だけではなく、何か一つはかなえて下さるそうなと言う人もあります。 (原話 遊 玉井国次)
このお像を発見した小さな浜辺を「舞浜」と言っております。
 毘沙門さんの転居 毘沙門さんの転居
字公庄の寺谷に毘沙門を祀る古いお寺がありましたが、住む僧とて居ないし、村人の管理の手もとどかず、荒れるにまかされていました。
ずっとむかしのことです。雪の夜、ご本尊の毘沙門さんが、ある村人の夢枕にたたれ
「わしは村の者に見離されたらしい。居ずらいので 今は郷の明光寺に来ておるのだ。たとえ村の者が迎えに来ても帰らんぞ」と申された。
不思議な夢だなと思い 夜が明けてから雪道を寺谷の寺まで行って見たら、ご本尊様の姿はなく、外の雪の上には、てんてんとして、妙な形の跡がついている。人の足跡とはちがう。
急いで帰って村役人に知らせ、村役人とともに、その妙な跡をたどって行くと、郷の明光寺まで続いておりました。
そこで住持さんとともに、本堂へまわって見ると、毘沙門さんはたしかにござる。
一同はこの不思議なできごとに、まったく驚いた。でも今さら背負って帰るわけにもゆかず、相談の上、このまま明光寺で祀ってもらうことにしたそうです。 (原話
後藤宇右衛門)
 下岡落谷のババメ 下岡落谷のババメ
むかし下岡の落谷には「ババメ」が棲んでいた。 「ババメ」とは大蛇のことである。
二人の村人が、落谷に山仕事に出かけた。「ババメ」は、すぐそれを見付けて、あっという間に一人を横ぐわえにした。もう一人はびっくりしてふるえあがり、そっと木蔭にかくれて見ていると、「ババメ」は上半身を空中に立ちあげてから、地面めがけてふりおろし山にたたきつける。この行為が何回か行われた。これを見ておそろしくなり、後をも見ずに、飛ぶように村に帰り、村人にその模様を告げた。勇敢な若者たちが、
「ようし、敵を討ったる」と言って、二人が退治に向った。
「ババメ」はすぐこれを見つけるや、まず一人の若者をまる呑みにした。他の一人は勇気をふるって、何くそと躍りかかり、友だちがぐんぐん呑まれつつある咽首のあたりを目がけて、持ってきた刃物で切りさいた。
呑まれていた友だちは鎌を腰に差していたので、呑まれるにつれて、鎌が「ババメ」の咽の肉を切ってはいる。内外から咽首を切りさかれたので、友人は助け出された。
「ババメ」は咽首を切りさかれ、深でを負って退散した。
呑まれた男は一命を助かり、元気を取り戻したが、頭髪は抜け落ち、再生しなかったという。
その後、呑まれた人の夢枕に「ババメ」があらわれ、
「われは長き世代に、あまたの生きものを呑み殺した。最後にお前を呑んで、咽首を切りさかれて命つきた。今後、わが霊は、今までの罪ほろぼしに、すべての生きものの命を守るであろう」と告げたという。
このことがあってからずっと後の話であるが、大雨洪水の時、落谷に山津波が起って、山が崩れ、土砂が引原谷に流れ出し、下岡田圃にたて臼のような「ババメ」の背骨がゴロゴロ流れてきて村の人を驚かせた。
その骨の元のあり場所は、高天山東山腹のババメ谷であったことがわかった。向うの尾根から、谷一つ越えて、こちらの尾根に真一文字に横たわって白骨体があったという。
「ババメ」は歯がないので、呑んだものは生きたまま丸呑みするが、大きなえものは、くわえて、上半身を空中に立て、地面にたたきつけ、つぶして呑みこむのだという。
 切畑の大蛇(おろち)退治 切畑の大蛇(おろち)退治
ずっと昔の話ですが、切畑部落にたいへん気丈な権作という老人がありました。ある年の秋、権作さんが、水無大橋谷という村の奥の焼畑へ出かけました。そこには、ソバや、アワを作っており、実が熟して
刈取りの時期がきたので、鎌とか、にない棒とか必要なものを持って畑までやってきました。ところがどうでしょう。ソバの穂が喰い荒され、ふみ倒されて、一面にむざんな姿となっている。
「狸めても喰い荒したのかな」と独りごと言いつつ 焼畑の上の段に目を移すと、どえらい大きな蛇が、ソバの実を食べている。驚くより腹がたった。
「ひとがせっかく苦労して作ったソバをスル(註)とは不届きなやつだ」と思いましたが、手道具はただ腰に差いえ鎌があるだけだ。
「いんで道具取ってくるまでそこに待っとれ」と言い捨てて、急いでわが家に帰りました。
家から鉈を持ってきて 途中の道の端にあった「青だらの木」(註)の末がふたまたになっているのを伐って、それを持って馳けつけたところ、大蛇は鎌首をもたげ、目をかがやざし赤い舌をチョロチョロ出し、今にもこちらへ、おそいかからんばかりだった。
強気な権作さんは、針だらけの「青たち」の木で蛇めがけてさんざん打ちおとし、なぐりつけた。そしてとうとう大蛇を打ち倒してしまった。
この闘いのためソバはよけいめちゃくちゃになってしまって、その惨状にぼうぜんとしたが、あきらめて、ソバは一本も刈らずに帰ってきました。
しばらく休んでから、まずひと風呂あびてと思って風呂場へ行ったところ、なんと、風呂場一面にたくさんの子蛇が居ります。そいつを外へ放り捨てて、入浴を終り、つぎに夕飯をと、箱膳のふたを取ると、そこにも子蛇が居ったので、これも放り捨てて
夕食をすませた。
やれやれと思って寝床へ入ろうとしたら、寝床の中にまで子蛇が居り、いかな強気な権作さんも気味わるく思いながらそいつも始末して寝入ってしまいました。
このような子蛇の攻勢はこれで終らず、その後もたびたびそんな事件に出合ったので さすがの権作さんも、いささか反省し、いくら相手が動物でも、年を経た大蛇の命をうばったことが原因で、そ怨念が残っているにちがいないとさとりました。
それからまず仏の加護にすがり大蛇の霊を供養することを思いたち、六部姿で霊場めぐりのため全国を巡国しました。
何年か後に帰国し、村の端に大きな廻国供養塔を建立し、僧の読経をもらい、村人にも供養をうけました。
こんなに尽してもなおその怨念が断ち切れなかったとみえ、この家では息子の代になってからもいろいろ不幸なことが続きましたので、息子もまた廻国供養に出かけ、帰村してから同じく供養塔へ墓を立てました。
さて話かわって、権作さんの退治した蛇はぞっとするような大きなもので その死がいが谷間の溝へ落ちこみ、その腐り汁が下流まで流れ出して その後、三年間ばかりは、牛馬がその水を呑まなかったと言い伝えています。
(原話 切畑 吉岡常夫)
註 スルとは食い荒すことの方言。
註 「青だらの木」とは幹にも枝葉にも一面にぎっしり針のある木。
 行基は本当に丹後に来たか 行基は本当に丹後に来たか
奥丹後には僧行基の開基になる寺院、または行基と関係のある寺院が多いので その寺伝によって来丹の年号を取りしらべてみました。
その第一は大宝二年(西暦七○二)行基自刻の十一面観世音像を郷村岩倉の地に祭祀したのが真言宗明光寺の創始。
それより二十八年後の天平二年(七三○)行基自刻の阿弥蛇如来像を祀られたのが、久美浜町本願寺の創建となり、それより十二年後、天平十四年(七四二)行基自刻の薬師如来像を祀って
網野町字木津、上野区に真言宗法貴山薬玉寺創建、その後中性院と改める。
以上のほか、網野町字尾坂、真言宗尾坂寺は天平年間(七二九〜四九)に行基が開基したと伝えられている。
また網野町生野内の大慈寺はもと大悲寺と称したが、年次不詳、行基自刻の聖観世音像を祀って創建されたが、伽藍は兵火のため焼失したと伝えている。
つぎに久美浜町如意寺は、天平年中、行基が、久美浜の地に滞在中創建されたものだと伝えられている。
つぎに中郡大宮町周枳の木積山薬師堂は、昔は真言宗であり行基の開基と伝えられている。
 愛宕山(わたごさん)の霊光
旧網野町、仲禅寺村、郷村の三か町村に裾をひく愛宕山があるが、海抜はさほど高くはないが、あたりの山々が底いので、ひときわ高く見える。
この山はむかしは高雄山といい、素戔嗚尊を祭神とした高雄神社があったのです。そこに一本の老松があって「神の松」と呼ばれて居ります。
延宝六年、すなわち今から三百年ばかり昔、この松に、毎夜、毎夜、夜灯がともり、村人は不思議に思って登ってみたら、愛宕さんのお祠子があったので、社屋を建立して、これに移したのだといいます。
その後、岡山半左衛門、嵯峨根半左衛門の両人がここへ、「愛岩山影向之松」と刻んだ石柱を建立し今に残っています。
今の若い人たちは、愛宕神社だけが祭祀されていると思い 高雄神社も共に祭られていることを知らない人が多いようです。 (原話 島津の老人)
 網野の前田六軒衆 網野の前田六軒衆
網野には、むかし、前田六軒衆というのがあり、財力豊かな豪族で 村の幹部とし役職は交代で勤められたという。
網野の地はかって中世に勅領地であったので その荘園の代官として赴任された人々の末裔ではないかと言われている。その一族は、広瀬を筆頭に、前田・前川・中矢・堀江・小山などがあります。
網野には中世に、 寺領を有した毘沙門堂の記録が、 丹後田数帳にてうかがえますが、おそらく勅領時代に創建のものではないかと思われる。 (原話 網野 中矢徳治)
 三津の夫婦塚 三津の夫婦塚
三津部落から、問人に通ずる街道の途中に夫婦塚と呼ばれる古墳があります。言い伝えによると、この古墳は 長慶天皇(南朝)が御退位後、病気療養のため、皇妃御同伴にて但馬湯島温泉に御入湯中であったが、思うほどの効験がみられなかった。その後、療養地として
丹後海岸の風光明媚な地を求められ、遂に、この地に足を止められたが、御滞在中御崩御となり、供人はもとより皇妃は、悲嘆のあまり殉死なされた。
土地の人々相計って 古例により寝棺に納めて、この地に埋葬し奉ったのだと、このような伝承があります。だが何ら文献はありません。 (原話 網野 中矢徳治)
 霊光によって救われた水夫たち 霊光によって救われた水夫たち
文化十四年(一八一七)九月二十六日、越中国放生津町の柴屋彦兵衛という人の持船で 三百五十石積、これに船頭吉左衛門、水夫五人乗組み、綿百五十四本を積んで、隠岐島を出帆しました。
ところが夜九つころ、西北風はげしく、雨をともない、高浪が押し寄せ、翌二十七日朝大風雨となり、帆をおろし、もはや浪まかせにした。やがて夜になり、山手・海手の見当もつかず、案じていた。
すると、はるか向うに霊光かと思はれる光を発見した。これぞ神仏のおはからいかと一同勇気をだし、帆を二合ばかり巻きあげると船はこの光目あてに岸へ向っていた。
しかし、いぜん風強く、二・三回高浪をうけて船中に海水をうけ、船は浪に打ち砕かれてきたので、乗員一同は何とかして、一命を助かりたいと、本船から小船をおろしたが、浪が高くて思うにまかせず、いよいよ最後だと思い
全員海水に飛びこんで、浜手に向って泳ぎ、幸いにして全員が助かりました。
その泳ぎ着いた所が、浅茂川村の浜辺でありました。
その後、浅茂川村人の好意・援助によって、積荷も少しは拾いあげ、船の破片も若干引きあげてもらいました。
船奉行所の改役員の検分も終り、拾いあげた物の処分も終ったので、一同は命の助かった原因となったのは船から見た霊光であるとして、その浜辺の山上に、不動明王の祠を建てて感謝、報恩の意をあらわしました。
現在、この山を不動山と言い 祭神は浪切不動さんで 今でも海に働く人々の信仰を集めています。 (原話 茨浅川 田浅井喜平治)
 かぶろう清水の話 かぶろう清水の話
今から四百年も前、天正十年にさかのぼります。下岡部落の後の山に下岡城があって、高屋駿河守が城主としてこの城により、附近の木津城主赤尾但馬守など立てこもって
攻軍一色忠輿とのはげしい戦いの結果、落城して多くの城兵は城と運命をともにしました。
その際、攻軍の重囲を脱したものも若干あり、高橋にあった平岡城主今井能勢治郎もその一人で、下岡城を逃れて、居城の平岡城までたどりつきました。
合戦の疲れと、空腹のため、よろよろして歩いていると、そこを通りかかった婦人を見つけ食を求めたが、女は恐れて逃げようとしたので、いきなりその婦人に斬りつけた。妊婦であったことがわかりました。
そしてかたわらの小池で刀を池って水を赤くにごしました。
その後、この池は、毎月七日の九ッ時(昼十二時)になると池の水が赤くなるので
月の七日や 日の九つに
かぶろ清水は 飲まぬもの
と、こんな文句が村人の間に伝えられています。
(原話 高橋 高家常之助)
 細陰の城物語(一) 細陰の城物語(一)
新庄部落の奥に霧降滝があって そこに籠堂があります。
神事に深い信仰をもつ人がお詣リして、堂の前ではつと霊感に打たれました。元来このようなお堂は修業の場所である筈なのにここのお堂はそれとはまた異るものを感じられ、これはどうもなにか深い事情があるにちがいないと思い、村の古老についていろいろ取調べられた結果、次のようなことが判明しました。
「このお堂に籠っていると、夜中に子供などの泣き声が聞えるかと思うと、打掛など着た奥方や、女中らしい婦人の姿や、傷ついた馬や、武士の顔などが、くらやみの中に浮び出ては消えなどする」のだと聞かされた。なお調べてみると「この地にむかし城があって、将兵が守っていたが、ある時代にほかから攻めたてられて落城した。
その際、婦女子などは、近くのお寺にかくまってもらった。当時はお寺に身を寄せて居れば、命は助けられる定めであったが、攻軍の兵はかまわず、寺ぐるみ焼打ちしてしまったので、全員が死亡した。
そのためその亡霊が出てくるのだと判明した。そのお寺跡かと考えられる屋敷跡があり、石垣など残存している」
○
字郷の森垣に、大松という地がある。ここに見事な枝ぶりの老松があったが、昭和二年丹後震災の頃伐採して今はない。この大松の地に残る言い伝えに、
むかし、新庄の城山で戦さのあったとき、城主の妻女がここまで逃れてきて、この松の元で自殺の覚悟をして、村人に
「わたしのなきがらは、新庄の城の見える所に葬って下されよ」と言い残した。
村人は遺言通りの場所に埋葬したのであると。
もしこのような伝承が事実であるとすると今の郷の明光寺の旧蹟であるという岩倉の地にあった伽藍こそその寺ではなかったか、同寺の寺記にも、岩倉の伽藍は兵火に焼かれたことを記しています。
 細陰の城、物語(二)
新庄城の別名を古い時代に「細陰の城」と称したようであります。
現在の地勢で考えると、こんな不便な場所を選んでなぜ城を築いたかと不審に思われるが、江戸時代までは現在のような引原峠道はまだ開通しておらず、もっぱら坪坂越えの道路が街道として唯一のものでありました。すなわち坪坂峠を越えて日和田を経由、熊野郡に通じる幹線道であって、この道路に添って新庄城(細陰城)が築かれていたのです。
築城者や、その年代は不明であるが、次に述べる戦いなどから案して南北朝の頃ではなかったかと考えられます。
正慶二年(元弘三)(一三三三)足利尊氏は、京都における鎌倉幕府勢が敗北したので、伯耆の船上山から後醍醐天皇をお迎えして 京都にお送りするため、その通路にあたる山陰方面の幕府勢を討伐する必要があるので、部下の熊谷直清、直久に命じ、とりあえず丹後方面の討伐に向わせました。
熊谷勢は海路を進み熊野郡浦明に上陸して、そこにあった浦明滅を討ち落しつづいて日和田を越えて、新庄城(細陰の城)へ向いました。ここには三浦安芸前司が拠っていたが、優勢な攻撃のために落城しました。
○
その後、室町時代までのこの城の歴史は明らかでないが、その頃は丹後の領主山名満幸の支配に属していたようであります。
室町幕府の三代将軍足利義満の時代に、山陰を中心として、丹後など十一か国を領し、強大な勢力を有する山名の存在は、幕府にとって脅威であったので、山名一門の離反を策した。それに乗ぜられた氏清と満幸は、京都で反幕の兵をあげた。これが史上有名な明徳の乱であります。
この戦いによって氏清は討死し、満幸は逃れて、丹波地を馳けぬけ、わが領土である丹後へはせ戻ってまいりました。
そして木津荘の細陰の城(新庄城)にたてこもったのです。
この時山名満幸の考えては、丹後は自分の領国なのだから、国内の地侍たちは、領主の帰国を悦び迎えることであろう。うまくゆけば丹後で兵をととのえて、再び京都に向って反撃の兵を進めてもよいと考えていたのです。ところが、事実は一人も馳せ参ずる者なく、国人までが自分から離反したのかと、さとって
そこには居たたまれず、主従十二・三騎にて、伯耆を指して落ちて行ったと「明徳記」に記されています。
この城には以上のような史実が残されているが、戦らしいたたかいのあったのは前記、正慶二年(元弘二年)の時のようであります。戦いの詳しいことがわからないのが残念であります。 (原話 井上正一記)
 下岡城落城 下岡城落城
その昔、足利氏は、その一門である一色氏を丹後守護に任じたとぎ、一色氏はその部下を丹後全土の八十五か城に配置して領土の守りをかためました。
網野町地城の下岡城では高屋駿河守良閑がこれに拠り、弟の高屋治郎左衛門を勝山城にその他の部下を周辺の各城に配置しました。
天正十年(一五八二)織田信長の命をうけた、細川藤孝のひきいる大軍の一部は、水軍の加勢をうけ、兵船二五○艘をもって田辺(舞鶴)より丹後半島をまわり、三手にわかれて
丹後半島へ上陸しました。
細川興元の指揮する二番手は、浅茂川港に上陸し、山を越えてからめ手より下岡城に迫った。
下岡城を守っていたのは城主高尾駿河守、その子遠江守、勝山城の高屋治部左衛門、高橋の平岡城主今井能勢次郎、公庄城主森忠左衛門、木津城主赤尾但馬守、大森城主松本内蔵之助らおよびこれに従う武士たちであった。
だが攻軍細川勢は優勢、守軍は劣勢でたち向った。両軍はげしい合戦の末、ついに下岡城は落城し、城主はじめ多くの将兵たちは計死しました。
それ以後、この城は再興されることなく今日に至っています。
 船山城主の最後 船山城主の最後
郷の船山城は築城の時代も不明であり、その歴史も明らかでないが、地元に残る伝承にこんなのがあります。
それは何時の、どんな戦いであったかよくわかりませんが、城主を今西和泉守といった。その落城の日にその妻女は自刃したが、その際言い残した言葉に
「今はもうすべてを失い、子孫に残すなんのかたみの品もない。せめて城主の一字をとって子孫は泉の姓を用いるように」と申されたという。 (原話
郷 後藤宇右衛門)
 尾坂寺のこと 尾坂寺のこと
尾坂寺はもと網野町字尾坂にありましたが、門前村として発達した尾坂村は、昭和三十四年の伊勢湾台風による被害が原因で、三十九年には全戸離村し、その際尾坂寺も、仏像を丹後町徳光の徳運寺に移されました。
尾坂寺跡には今でも南の坊、向坊、住信坊、熊住坊などの小字が残っており、その全勢時代にはまだまだ多くの坊があり、大寺だったのです。
この寺は天平年間(七二九〜四九)に僧行基の開基になるものと伝えられており、康正元年(一四五五)の「丹後田教帳」によると、三町歩の寺領があったようです。また天文九年(一五四○)の「丹後国御檀家帳」には「おさか寺、中の坊、大なる城主なり、国のゆみやとりなり」と記されているから、この時代には多くの僧兵が拠っていたものと思われます。
元亀二年(一五七一)織田信長によって、「丹後の真言倒し」が行われ、丹後の真言寺院は、僧は追放、伽藍は焼かれた。
こんなことがあってから尾坂寺もしだいに衰退したようであります。
 石塔に小便かけて死んだ子供 石塔に小便かけて死んだ子供
網野の銚子山の寛平法皇塚の近くに一基の石塔があった。いぜんから、この石塔に小便かけたら命がないとの言い伝えがあり、誰も恐れて近寄る者はありませんでした。
その附近が子供の遊び場であったので、ある月、やんちゃ坊主で知られていた子があって、みんなとともに遊んでいるうち、その子がその塔の上に登った。ほかの子供らが、
「おいそんなと二へ登ったらたいへんだ」「降りてこいよう」とやかましく言ったが、降りない
「なにがたいへんだあ、わしが小便かけちゃる」と言って、ジャアジャアやらかした。
ほかの子供たちは、後のたたりを恐れてみんな走って帰ってしまいました。
ところが翌日になって、たいへんなことを聞いたのです。それは昨日小便かけたやんちゃ坊主が、腹痛のため死んでしまったという。 (原話 網野 井上保治)


|