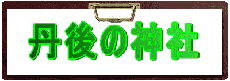| 加佐郡神名帳 |
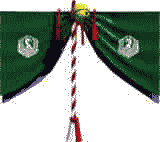
![]() 丹後国
丹後国
![]() 現在のどの神社にあたるかの比定は私の判断です。別にどこかに公認されているわけではありません。当たっているのもあれば間違いも多いと思います。鎮座地も祭神もよく変わるようです。
現在のどの神社にあたるかの比定は私の判断です。別にどこかに公認されているわけではありません。当たっているのもあれば間違いも多いと思います。鎮座地も祭神もよく変わるようです。
ここは10世紀以前の記録と考えられる資料です。今に伝わるもっとも古い記録で、古い時代にはこうした神社があった。もう少し古くなればと社殿を構えた神社はなかったと思われる。岩や木の元でお祀りしたと言われる。
日本人とは何物。どこから来て、どこへ行くのか。こうした疑問に答えるには、このあたりを調べるより道はない。
| 比定社の画像及び現在の所在地 (画面中央の小さな |
『丹後風土記』残欠・神名帳(記載順) | 延喜式神名帳(延喜5年・905) (記載順は()に入っている数字順) 加佐郡十一座(大一座小十座) |
備考 祭神等 |
当サイト内へのリンク (主なもの) |
|---|---|---|---|---|
 |
青葉社 | |||
 |
天藏社 | |||
 |
山口坐祖神 | |||
 |
日尾月尾社 | |||
 |
志東社 | |||
 |
大倉木社 | 一説に布留山神社とする。 |
||
 |
御田口社 | |||
 |
河辺坐三宅社 |  一説に北吸の三宅神社(左写真。舞鶴市北吸)。「河辺坐」とあるから、ここではないと思える。 一説に北吸の三宅神社(左写真。舞鶴市北吸)。「河辺坐」とあるから、ここではないと思える。『京都府地誌』に、 八幡神社 村社々地東西二十七間南北三十間面積六百二十五坪村ノ東ニアリ誉田別尊猿田彦命ヲ祭ル里老云原ト三宅明神ト称セシ?中古今ノ称ニ改ムト当社享保年度ノ幟ニ三宅神社トアリ祭日八月十八日境内末社三座アリ |
||
 |
鳴生葛島社 | |||
 |
同将軍社 | |||
 |
杜坐弥加宜社 | |||
| 高田社 | ||||
 |
倭文社 | |||
 |
砧倉社 | |||
 |
手力雄社 | |||
 |
日原社 | |||
| 出雲社 | かなり古い時代に廃絶したものと思われる。「室尾山観音寺神名帳」以外にはこの社の資料は何も伝わらない。申し訳なし。 | |||
 |
伊加里姫社 | |||
 |
笠水社 | |||
 |
笶原社 | 笶原神社の比定地は古来3箇所ある。紺屋町・野原・与保呂である。これは私見による比定地である。 | ||
 |
伊吹戸社 | |||
 |
十二月栗社 | |||
 |
石崎坐三輪社 | |||
| 凡海坐息津島社 | ||||
| 凡海息津島瀬坐日子社 | ||||
 |
大川社 | |||
 |
伍藏社 | |||
| 布留社 | ||||
| 船戸社 | ||||
 |
伊知布西社 | 伊知 |
||
| 麻良多社 | ||||
| 水戸社 | ||||
| 奈具社 | ||||
| 神前社 | ||||
| 気比社 | ||||
| 剱社 | ||||
| 阿良須社 | ||||
| 「室尾山観音寺神明帳」 |
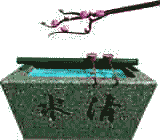 元亀三年(1572)の写本の奥書があるものは伝わらないのであるが、おそらくその時代以前成立のものと考えられている。加佐郡だけででなく、丹後の全郡がそろっている。写本が二系統伝わるそうで、それが少しずつ違う。下の表の左が舞鶴の金剛院に伝わったもの、次はは観音寺のものだそうである。
元亀三年(1572)の写本の奥書があるものは伝わらないのであるが、おそらくその時代以前成立のものと考えられている。加佐郡だけででなく、丹後の全郡がそろっている。写本が二系統伝わるそうで、それが少しずつ違う。下の表の左が舞鶴の金剛院に伝わったもの、次はは観音寺のものだそうである。
観音寺で調査された舞鶴地方史研究会の杉本嘉美氏によれば「神明帳はもともと丹後国分寺が諸神の冥通を願い修正会に奉誦していたものと解される」。平安時代には既に成立していたと考えられるという。(『両丹地方史』(1988.5))
現在のどの神社にあたるのか、その比定はたいへんに困難である。わかりそうなものだけ比定しておく。ただし私の判断である。
| 現在の比定神社 画像 現在の所在地 |
位階 | 神社名 『元初の最高神と大和朝廷の元始』 |
神社名 『舞鶴市誌』 |
神社名 『加佐郡旧語集』 |
備考 | |
 |
正一位 | 大河明神 | 同左 | 大川明神 | 式内社 | |
 |
正一位 | 同左 | 田力尾 | |||
| 正二位 | 松尾明神 | 同左 | 松尾 | |||
| 正二位 | 奈具明神 | 同左 | 奈具 | 式内社 | ||
| 正二位 | 同左 | 嶋満 | ||||
| 正二位 | 布留明神 | 布留 | ||||
| 正二位 | 息津嶋 | |||||
 |
正二位 | 葛島 | ||||
| 従二位 | 三宅明神 | 三 |
三宅 | 式内社 | ||
| 従二位 | 丸田明神 | 丸田添 | 式内社 | |||
| 従二位 | 同左 | 千滝 | ||||
| 従二位 | 湊明神 | 湊 | ||||
 |
従二位 | 市布施明神 | 市布施 | 式内社 | ||
| 従二位 | 牧 | |||||
| 従二位 | 伊 |
伊津岐 | ||||
 |
従二位 | 日原明神 | 日原 | 式内社 | ||
 |
従二位 | 同左 | 加佐姫 | |||
 |
従二位 | 同左 | 加佐彦 | |||
| 正三位 | 千滝 |
千滝雨引 | ||||
| 正三位 | 有 |
有栖 | 式内社 | |||
| 正三位 | 高 |
志 |
志呂 | |||
| 正三位 | 太社明神 | 大社 | ||||
| 正三位 | 多礼売 | |||||
 |
正三位 | 倭文明神 | 委文 | 式内社 | ||
| 正三位 | 高田明神 | 高田 | 式内社 | |||
| 正三位 | 物部明神 | 物部 | ||||
| 正三位 | 郡立明神 | 郡立 | ||||
 |
正三位 | 波多明神 | 波多 | |||
| 正三位 | 桑田明神 | 奈多 | ||||
| 正三位 | 藤津明神 | 藤津 | ||||
| 正三位 | 大宇賀明神 | 大 |
大宇賀 | |||
| 正三位 | 高鞍明神 | 高鞍 | ||||
| 正三位 | 御陰明神 | 御陰 | 式内社 | |||
| 正三位 | 三宅明神 此一社二重書と相見候 即ち此の社を除き七十七座 |
− | ||||
 |
正三位 | 笠売 | ||||
| 正三位 | 雨引明神 | 雨引 | ||||
| 正三位 | 筒 | |||||
| 正三位 | 太祢明神 | 太祢 | ||||
 |
正三位 | 猪鞍明神 | 猪鞍 | |||
| 正三位 | 同左 | 津夫衣 | ||||
| 正三位 | 船度明神 | 船度 | ||||
| 正三位 | 気比明神 | 気比 | ||||
| 正三位 | 境明神 | 境 | ||||
| 正三位 | 神 |
神並 | ||||
 |
正三位 | 如意明神 由良神社歟 |
如意明神 | 如意 | ||
| 正三位 | 神前明神 | 神 |
神前 | |||
| 正三位 | 山口明神 | 同左 | 山口 | |||
| 正三位 | 青山明神 | 同左 | 青山 | |||
 |
正三位 | 砧倉() | ||||
 |
正三位 | 伊加利比売明神 | 伊加利 |
伊加利比売 | ||
| 正三位 | 芝束 | |||||
| 正三位 | 加和良明神 | 加和 |
加和良 | |||
| 正三位 | 介地明神 | 介比 | ||||
| 正三位 | 劒明神 | 剱 | ||||
| 正三位 | 河辺明神 | 河辺 | ||||
| 正三位 | 大倉明神 | 大 |
大倉 | |||
| 正三位 | 村津明神 | 木津 | ||||
| 正三位 | 宮嶋明神 | 宮 |
宮前 | |||
| 正三位 | 小嶋明神 | 小嶋 | ||||
| 正三位 | 笠原 | 式内社 | ||||
| 正三位 | 阿具明神 | 阿具 | ||||
| 正四位上 | 大歳(大蔵カ) | |||||
| 正四位上 | 中村明神 | 同左 | 中村 | |||
| 正四位上 | 国津明神 | 同左 | 周津 | |||
| 正四位下 | 天藏明神 | 天藏 | ||||
| 正四位下 | 市施明神 | 同左 | 布施 | |||
| 従四位上 | 福徳嶋明神 | 同左 | 福徳 | |||
| 正五位下 | 息津島 | |||||
| 従四位上 | 池内明神 | 池田 | ||||
| 従五位下 | 同左 | 曽保谷山口 | ||||
| 従五位上 | 大冨明神 | 大 |
大冨カ | |||
| 従五位上 | 津社明神 | 同左 | 津社 | |||
| 従五位上 | 伊加利明神 | 同左 | 伊加利 | |||
| 従五位上 | 津嶋明神 | 同左 | 津嶋 | |||
| 従五位上 | 初施明神 | 布施明神 | 布施 | |||
| 従五位上 | 出雲明神 | 出雲 | ||||
| 従五位上 | 伊波比明神 | 伊 |
伊波井 | |||
| 従五位上 | 猪半 | |||||
| (参考)加佐郡郷名帳 |
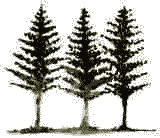 記載順通り
記載順通り
加佐郡は丹後国5郡の中では最も郷が多い。それは人口が最も多かったということである。少なくとも『和名抄』の作られた頃(10世紀前半)には、加佐郡が丹後国内では最も大都会だったということになる。従って文化や政治、経済の中心地であったと思われる。
古代の遺跡も古墳もたいしたものがなく、いつも肩身の狭い思いの加佐郡であるが、古代の終わりの時代にもなれば一番の「都会」であった。何ゆえにこれだけの人口がいたのであろうか。丹後国内でどうした役割を演じたのであろうか。誰も未だ解明はしていない。古代史における加佐郡を見直す時がきているのかも知れない。
| 『丹後風土記』残欠の郷名帳 | 『和名抄』 高山寺本 |
『和名抄』 刊本 |
中世文書 | 備考 | |
| 志楽 本字領知 | 志楽 之良之 | 志楽 | 志楽庄 | 志楽小学校 | |
| 高橋 本字高椅 | 椋橋 | 高橋 | 倉橋郷 椋橋庄 |
倉梯小学校 | |
| 三宅 本字前用 | |||||
| 大内 今依前用 | 大内 | 大内 | 大内郷 大内庄 |
舞鶴市大内 | |
| 田造 今依前用 | 田邊 | 田造 | 田邊郷 田名部庄 |
田辺城(舞鶴城) | |
| 餘戸 | 余戸 餘部里 |
余部上・余部下 | |||
| 凡海 今依前用 | 凡海 於布之安末 |
凡海 於布之安萬 |
|||
| 志託 本字荒蕪 | 志託 之多加 | 志託 | 志高庄 | 舞鶴市志高 | |
| 有道 本字蟻道 | 有道 安里知 | 有道 | 有道郷 | 大江町北有路・南有路 | |
| 川守 今依前用 | 川守 | 川守 | 河守庄 | 大江町河守 | |
| 余戸 | 餘戸 | ||||
| 神戸 | 神戸 |