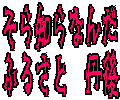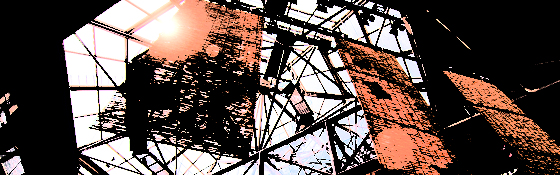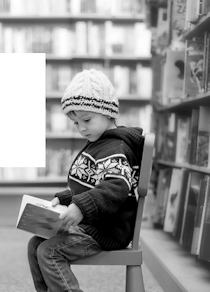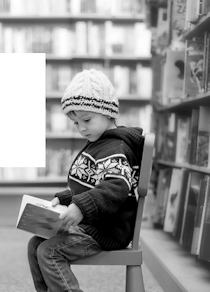

少年易レ老学難レ成、一寸光陰不レ可レ軽
脳が若い30歳くらいまでに、せめて千冊は読みたい

友を選ばば書を読みて…と与謝野鉄幹様も歌うが、子供の頃から読んでいるヤツでないと友とも思ってはもらえまい。
本を読めば、見える世界が違ってくる。千冊くらい読めば、実感として感じ取れる。人間死ぬまでに1万冊は読めないから、よく見えるようになったとしても、たかが知れたものである。これ以上の読書は人間では脳の能力上、生物の寿命上、言語能力上不可能なことで、コンピュータ脳しかできまい。
 いい書籍との出合いを! いい書籍との出合いを!
当サイトはどなたからも費用を頂いているわけでもありません、取材費が莫大になりボランティア精神だけではどうにもならなくなり始めました。スポンサーといえばナニですが、世界一の本屋さんの手伝いです。
いい人との出合いは運次第、思うようには巡り会えないかも知れません、それが人生。
しかしいい本との出合いは、この本屋さんを探せば、テンコモリです。
GOOD LUCK !
 そのほかも大盛りすぎ そのほかも大盛りすぎ
田舎暮らしの不自由なことは、ショッピングに、特に現れるのでないでしょうか。地元商店で購入したい、地元に多少ともそんなことででも貢献したいとは思って、のぞいてみても、ナニもコレといったモノは売られていない。もうチイとらしいモンはないんかい。と、もしかして思われているならば、バですが、ここで探してみて下さい。
さらに加えて配達は抜群に速い。今日の午前中に注文すれば、明日には到着する(在庫あるものならば)(ネダンは安いし会員なら配達は無料)。
-PR-


アマゾンで史書を探す


もしミュージック(全ジャンル)を聴くなら



アマゾン・タイムセール(これはお得) |
|
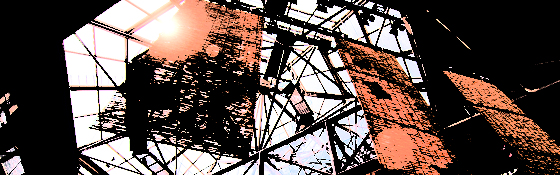
 『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。 『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。
放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。
 真倉は西舞鶴市街地の南、伊佐津川上流の綾部市黒谷と接する所にある集落名である。JR「真倉駅」がある。 真倉は西舞鶴市街地の南、伊佐津川上流の綾部市黒谷と接する所にある集落名である。JR「真倉駅」がある。
この手前に十倉という集落があり、古くは真倉と十倉は一村であったと伝わる。マグラといいトクラといえば、何か関係のない地名のように思えるが、一村だったというのだから、同意の地名なのであろうか。恐らく古くはシンクラ(真倉)とジュウクラ(十倉)と呼んでいたのではなかろうか。それならばほぼ同名の地名であり、これらの地名ならたぶんシラかソフルの転訛であろう。
兵庫県氷上郡青垣町小倉神楽に鎮座の神楽神社(佐次神社)は、志牟良大明神とも呼ばれた。これから考えればシムラ、シフルが転訛してシグラとなったものと思われる。しかしまた神楽は漢字の通りならシンラ、シンラクで、シラ(斯羅=新羅の国名)のことであろう。
ソフル(新羅の別称)の転訛ともシラの転訛とも考えられるが、どちらにしても新羅を意味するものであろうか。
尚、佐次は山の幸のことで鉱物のこととする説(『鬼伝説の研究』)があるが、阿羅斯等のシトの転訛かも知れない。
シンクラは新座郡がある。ニイザと読むのが一般的で、今は埼玉県新座市となって郡名が残っている。新座郡は元は武蔵国新羅郡で、いつの間にか表記法が変わったのだが、表記に使われている漢字の意味ではなく、新座は新羅を意味した地名に後に当てた当字であるようである。
新座はこのように漢字で表記されると、ニイザ、ニイクラ、シンザなどとも呼ばれるようになるが、シンクラと読むのが本来の読み方ではなかろうか。先の神楽と同じと思われ、シフル、シムラ、シンクラと転訛したものか。
舞鶴の真倉も同様かと思われる。真倉だけなら決め手がないが、十倉、十倉神社とセットなので、元々はシンクラと呼び、新羅を意味したが、漢字に引きずられて今のようにマグラと呼ぶようになり、元々の意味がわからなくなったものであろう。
 十倉の地名や社名は当地だけでなく見られ、福知山市大江町北有路に鎮座する阿良須神社(式内社)も、十倉神社とも呼ばれたという。 十倉の地名や社名は当地だけでなく見られ、福知山市大江町北有路に鎮座する阿良須神社(式内社)も、十倉神社とも呼ばれたという。
加佐郡有地郷は十倉神社だらけである。
『大江町風土記2』
十倉五社のこと
有路には、十倉神社という宮さんが五つあります。これは兄弟が五人あって、一番上が野上、二番目が阿良須、三番目が矢津、四番目が五日市、五番目が二カ村にまつってあるということです。祭神は、五つとも“木花さくやひめ”という女の神さんです。このの五つの内一番大きなのが阿良須神社で、式内社になっています。(有路小 真下直司)
五人の兄弟がまつってあると書いてありますが、これは十倉山のふもとに住みついた一族が、だんだん勢力ができてきたので、おなじ氏神をまつって、わかれて住んだのではないでしょうか。
十倉山は十倉一宮神社(南有路森安)の背後の姿の美しい山で、この社は元はこの山の上に祀られていたという。一宮と呼ばれるくらいだから、当地の阿利叱智一族はこの麓から広がっていったのかも知れない。そうだとすれば十倉は渡来系の名でなかろうか。トクラと呼んでいるが、たぶん古い読み方はジュウクラであろう、厳密に発音通りの漢字を当てたわけではなく、好字を取っている。元々の地名であったシフル、シクラをこのように書いたものと思われる。
シクラは万葉集に詠われている古い地名である。当サイトどこかでも書いたが、もう一度とりあげてみよう。
叔羅川(シラキ川、シクラ川)
『万葉集』大伴家持の歌(19巻4189番歌)。
天離る 鄙としあれば そこここも 同じ心ぞ 家離り 年の経ゆけば うつせみは 物思ひ繁し そこゆゑに 心なぐさに 霍公鳥 鳴く初声を 橘の 玉にあへ貫き
かづらきて 遊ばむはしも 大夫を 伴なへ立てて 叔羅川 なづさひ上り 平瀬には 小網さし渡し 早き瀬に 鵜を潜けつつ 月に日に しかし遊ばね 愛しき我が背子
同じ(19巻4190番歌)に
叔羅川瀬を尋ねつつ我が背子は鵜川立たさね心なぐさに
叔羅(しくら)川は越前の日野川だが、信露貴川、白鬼女川などとも書いて、叔羅はシクラ、あるいはシラキと読んだという。
『角川地名辞書』は、「万葉集」巻19の大伴家持の歌に詠まれる「叔羅川」は「シラキ」または「シクラ」と訓み、現在の武生市街地に所在した越前国府近くを流れる日野川に比定される。
『南條郡誌』
此川(日野川)を古へは叔羅河といひ、後には白鬼女川と呼び、白川〔今立郡舟津村鯖江の一部之も白鬼女川の路〕の渡をも白鬼女渡と稱し古来有名なりき(〔絵図記〕の一本には此渡を丹生南條郡境とせり)
〔萬葉集一九〕
…叔羅河…
叔羅河…(賀茂眞淵 翁云叔羅川は越前の人云府に白鬼女川有り神名帳に…白城神社ありさればこの叔羅は新羅の誤にてしらき川なるへしといはれき元暦本に叔??とあれば誤字近し
〔古名考〕新羅ヲシラキト読ツケレハ固新羅城ナリシヲ下ノ城ノ字ヲ省キテナホシキトイヒシコトナレバ叔羅ト書シモ城ノ字ヲ省ケル仮字ナラム
〔名蹟考〕 新羅川を叔羅訶と後世誤れる亊必せり
〔梅田笑談〕叔羅ハ新羅ノ同例ニテシラキノ仮名ナリ
〔名所志留倍久佐〕 叔羅河は…今の白鬼女河なることを必せり
〔足羽社記〕信露貴川今云白鬼女川下而謂之日野川石田川奇津川出于信露貴山麓〔今云夜叉池山〕
〔鯖江志〕 白姫川後世誤稱白鬼女川蓋姫鬼音同故謬且略姫之旁爲女也…渦(日野山)麓又稱日野川者土人云稱也或云河之上流往古祭皇女白姫之靈古有其祠因名之云皇女未詳何帝之女云
…
こうしたことで十倉も新羅であろうかと推測されるのである。まぐら、とくら、あらすをセットで考えた先人はない。
真倉、十倉の鎮守社の十倉神社(山崎神社、一宮神社)。
「神社旧辞録」に、
山崎神社 祭神 天照皇太神荒御魂 同市字十倉
往昔より真倉及び十倉の鎮守であって一ノ宮様で罷通った古社である。田辺郷九社明神の一、「一ノ宮」郷司の順拝巡位によるともいふ。
社名は喜多村の宮崎神社と同様の意にて、山の前鼻サキに鎮座あるゆゑの呼称と睹られる。土記及び寺記の砧倉社に比定さる。
一宮神社と国道27号に面した道路縁に案内板があるが、陸橋へ登る手前、伊佐津川のほとりの鎮守の森の中で、境内にレストランがある。
土記というのは丹後国風土記残欠、寺記は観音寺の丹後国神名帳七七社を言っているのだが、砧倉の砧はトンとは読めない、キヌタのことであるが、チンとしか読めない。砧倉は正しくはチンクラ神社と読むのであろう。シとチはよく互転する語なので、チンクラとはシンクラのことであろう。シフル(ソフル)神社であり、この地一帯の開拓者新羅系天日槍までさかのぼる人々が祀った社と推測される。
川下側の田辺郷内は九社とか笠水とかクシ、カサ系の名が知られる。クシフル系の地名と見られる、当地の人々が広がっていった地かも知れない。これらも新羅と関係ありそうである。後にとりあげてみたい。
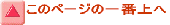
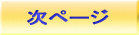

『京都新聞』(20200509)(写真も)
*「天道花」復活の輪広げ
*舞鶴・真倉地区の民家門前60年ぶり
*豊作祈願で
竹ざおの先に季節の花々をくくり付けて掲げる「天道花」が8日、舞鶴市真倉地区の民家の玄関近くや寺の境内に立てられた。多くの門先で掲げられるのは約60年ぶりで、「田の神」を迎える「より代」とされる天道花に住民らが豊作を願った。
2月に住民らで結成した「真倉元気村」が企画した。同団体によると、地元の善通寺では以前、5月8日に釈迦の誕生を祝う仏生会が行われ、各家庭で天道花を門先に立てていたが、昭和30~40年ごろ途絶えたという。
同地区の俳句会員らが10年前から復活に取り組み、昨年は2軒が続けていた。同団体が「昔ながらの風習をもっと広めよう」と呼び掛け、15力所で掲げられた。
住民らは、事前に山から切り出してきた約3メートルの竹ざおに結んだペットボトルに、ツツジやフジなどの花々を束ね入れ、慎重に立てかけていった。
10日まで飾る予定で、上野昭生代表(68)は「新型コロナウイルスの終息も願った。再び人々が集まれる時が来たら、地元が元気になる催しを企画したい」と話す。
郷土の研究や復旧、普及に熱心な地である。
 音の玉手箱 精神に翼をあたえ、想像力に高揚を授ける、音の宝石 音の玉手箱 精神に翼をあたえ、想像力に高揚を授ける、音の宝石
 Bella Ciao (Canto dei partigiani):さらば恋人よ(パルチザンの歌) Bella Ciao (Canto dei partigiani):さらば恋人よ(パルチザンの歌)
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
bellaは美しい人とかいう意味だそうで、恋人(女)に対する呼びかけ語。
ciaoは逢ったとき、別れる時の挨拶語。
マスク姿は戦いに倒れた人々、此の世の者ではないことを意味するものだろうか。
作詞作曲不明。第二次大戦中イタリアパルチザンの誰か若い戦士が作ったものであろうか。曲の詳細が不明なのは、彼が予感のとおり戦いの中に倒れたのであろう。彼の墓のそばに咲く美しい花がこの歌であろう。終戦記念日、日本ではそう言うが、解放記念日(4/25)には必ず歌われるという。日本には倒れた幾万の戦士への鎮魂と戦いへのホコリと勝利の歓喜を持って敗戦日に歌える名誉の歌はない。
FM曲のライブラリーにはなかろうと思い、たずねもしなかったので、ここで紹介。
(5) Milva - Bella Ciao (Live Version) - YouTube (2) Milva - Bella Ciao (Canto Dei Partigiani) - YouTube
(1) Bella Ciao in piazza a Genova il 25 aprile 2015 - YouTube
(1) Bella Ciao - Nuit Debout - YouTube
(99) Bella Ciao - Orchestra Roma Sinfonietta @ Festa del 1° Maggio 2011
- YouTube
(1) イタリア軍歌民謡「さらば恋人よ」伊日字幕ベラチャオBerra ciao It.Jp.Sub.啊朋友再見 - YouTube
(1) 【Megurine Luka】イタリアパルチザンの歌: Bella ciao. (Japanese) 【Vocaloid 2】巡音ルカ
- YouTube
イタリアは日本とは同盟国であったが、彼国には反ファシズムのパルチザン運動があった、内戦と呼ばれるほどに強く、市民が武器をとって自国のファシストと戦い、ファシズム同盟の中では最も早く解放の日を迎えた。一番遅れに遅れた国にいて、このあたりを忘れると全世界から冷笑されよう、ぜひ覚えよう。

コロナとの今の周回遅れの戦争の中でも、こうした苦い過去が繰り返されているように感じてしまう。マスクもなかった、検査数が少なすぎる、ワクチンはいつになったら接種できるのか、病床が急に半減以下となった、野戦病院は名ばかりで医師なく看護師なく薬なく弾薬なく食糧すらなく実際は死を待つだけ、GoToや五輪しか頭にないタケヤリ戦等々…敵を知らず己を知らず口先だけカッコいい大ウソを重ねた大本営も顔まけ、こうした者どもの戦争指導能力を疑うが、しかし日本政府政治だけが周回遅れではない、日頃から市民レベルでもまた医療インフラなど自分の命にかかわるものにすらも目も向けず怠惰で遅れに遅れがちなのではなかろうか、おカミにまかせっきりにしている。おカミが信用できるかどうかを歴史に学ばない。
↑こうした不理屈な者とは断固戦う伝統をハード、ソフト両面で持たない「近代市民」がほとんどであり、ワレラはその子や孫やひ孫なので、いろいろな分野で心配なことである、郷土史の世界でもそうしたことはないのであろうか…せめて半歩でも進んでいこう。

有名な歌。さらばさらば恋人よ。
ある朝、私は目を覚まし侵略者を見つけた。さらばさらば恋人よ。パルチザンよ、私を連れていってくれ。私は死ぬような気がする、パルチザンよ私を連れていってくれ。私がパルチザンとして死んだら、山の中の美しい花の影の下に埋めてくれ。通り過ぎる人はみんな私に「なんて美しい花なんだろう」と言ってくれるだろう。「これはパルチザンの花です」「これは自由のために死んだパルチザンの花です」と。恋人よさらば、さらば、さらば…
ファシズムにバンザイバンザイしていたような者は世界から見れば、後世の子孫から見れば何もホコリでもジマンでもありえない。そうした言葉は自由のために命を捧げた幾万の人の前では、平和を求める世界の人々の前では口が裂けても口にできない言葉である。女王ミルバともなればチャウ、目が覚めそうな歌になる。バンザイバンザイ末裔などでは足元にもよれない迫力がある、そんな者どもとはチャウチャウチャウ。
こんなにすごいのはピアフが歌うフランス国歌(La Marseillaise)くらいではなかろうか。
(5) EDITH PIAF - LA MARSEILLAISE.WMV - YouTube
武器を取れ市民らよ 隊列を組め 進もう進もう
見たところそこらの貧相なオバちゃんといった感じだが、市民よ進もう進もうと大声はり上げて歌う、タマシヒから出ている声だ、どこかのバンザイイナカモンとは、市民としてのタマシヒがまったく違う別物である。
「カサブランカ」という映画を思い出す
(1) La Marseillaise Casablanca - YouTube
バルチザンとして戦ったのはイタリアやフランス市民だけではない。
(5) 【ロシア語】小麦色の娘 (Смуглянка) (日本語字幕) - YouTube
(8) 【和訳付き】小麦色のモルドバ娘(ロシア民謡)"Смуглянка молдoванка" - カタカナ読み付き -
YouTube
|
 資料編のトップへ 資料編のトップへ
 丹後の地名へ 丹後の地名へ
資料編の索引
|