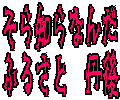 |
安壽姫伝説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
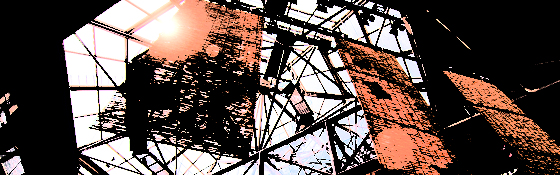 放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 安壽姫伝説 京都府宮津市由良に「安壽と厨子王の像」↑と案内↓がある。  安寿と厨子王
像は越後の方を指さし、ふるさとの越後の向いている。筑紫の国に流された父を尋ねて、毋と共に越後を旅立った姉弟「安寿と厨子王」。旅の途中、人買いに取られ母は佐渡へ、姉弟は丹後由良の山椒大夫の所へと売られた。姉は命と引換えに弟を逃し、も都に出た厨子王は丹後の国守となり悪人を成敗し盲目となった毋と再会したという。 山椒太夫伝統の里「丹後由良」にはこの伝説に因んだ遺跡が点在しています。 この伝説を知らぬ人はなかろうが、この伝説は、伝説といっても巨大なもので、1ペーシ(30分)や、そこらではすべてを取り上げることができない。 ここでは安壽姫だけ、それも簡単に、特に潮汲みや製塩の部分だけに絞って、しかも簡単に取り上げてみようかと思う。 『加佐郡誌』 山庄太夫(三庄太夫)
由良ケ嶽の麓石浦の里に三庄太夫の遺趾といふのがある。三庄太夫は丹波氷上郡の産で世々蜀椒を鬻ぐのが家業であったが丹後の由良に来て住むやうになってからこの家が頗る富み栄え付近三ケ荘の代官をつとめるやうになり終には千軒長者の綽名をさへ得るに至った。村上天皇の天暦年間奥州の太守岩城判官将氏寃罪を以て筑紫に譴謫せられたところでその二子姉安寿姫姫、弟津塩丸(津子王丸とも云ふ)父を慕ひ遂に母を促して郷里を出で筑紫に下らうとした。山を越え川を渡りやうやう越後の国直江の浦の逢岐橋まで辿りついたが折りあしく姦賊山岡太夫といふもののために奪はれ母は佐渡が島に售られ安寿、津塩の姉弟は宮崎三郎といふ者の舟に乗せられ由良湊に来り彼の三庄太夫に售られて奴隷になった。それから父を慕ひ母を恋ひ知る人とてもない他国に毎日々々を姉は海に水を汲み、弟は山に薪を採り手なれぬわざに名状すべからざる辛酸を嘗めた。しかも太夫の三男、三郎は勇悍強戻で鬼の如く酷使苛責至らざるなき有様で姉弟は堪え得ることが出来ず、遂に相謀った窃かに逃れ津塩丸は和江の国分寺まに隠れ住僧の義侠によって経筐に匿れて辛じて追手の難を逃れることが出来た。住僧は大いに津塩を憐み窃かに之を経筐に入れ自ら背負ふて洛陽に到り清水寺の大悲閣に送った。その時上郷中に梅津院と云ふものがあって年老いて子の無きを惑ひ大悲閣に祈願をこめて居たが一夜大悲梅津院に「汝が子は堂の裡にある」と告げられた。夢から覚めて津塩丸に逢ひ喜んで父子の契りをなし相伴ふて家に帰り顛末を帝に奏上した。やがて津塩丸の家譜が天聴に達すると共に特に旧国を賜ひ更に丹後に知府たられめられた。ここに於て津塩丸は先づ母を佐渡に省み丹後の国分寺の僧を訪ふて旧恩を謝し三庄太夫の一族を誅殺した。これより前安寿姫は太夫の家を遁れ京に上らうとする途中、中山から下東へ出る間の阪で飢餓に堪へず敢なき最後を遂げたと云ふ。今存する「三庄太夫の首挽松」と云ふ遺跡は太夫が誅戮せられる時竹鋸で道行く人が松の下に首から下は地中に埋められた太夫の首を一遍づつ挽いた処であると伝へられ、安寿姫の最後を遂げたといふ阪は「餓阪」と名づけられ今も「姫塚」と称する墳塋(下東村字建部山の麓に)が遺って居る。 安壽姫塚フェスティバル(舞鶴市下東)   伝説を知っているのか、皆やさしい目をしていた。 案内板がある。 安寿姫塚の由来
安壽姫伝説は東北(岩木山、佐渡、直江津など)から丹後まで、広い範囲に分布していて、互いに少しずつ異なるが、下東の当伝説や「和江の国分寺」などは、舞鶴だけに見られる物語である。村上天皇の天暦年間(九四七)奥州の大守岩城判官将氏は、えん罪を受け筑紫に送られた。その子姉 安寿姫、弟 津塩丸(厨子王)は母と共に父のあとを追って、越後の国 直江の浦岐橋に来たとき、姦賊 山岡大夫に母は佐渡が島へ、姉弟は宮崎の二郎に由良の湊で、三庄大夫に売られ「汐汲み」「柴刈り」にと冷酷な苦難の毎日を送っていた。 ある雪の朝、弟は浜小屋を抜け出し和江の国分寺に助けを求めた。住僧は彼を行李(こうり)の中にかくまった。追手はこれを見つけ槍で突いたが刺さらないので中をしらべると、石の地蔵さんが身代りに入っていたと言う。 難を逃れた厨子王は洛陽に行き、後に丹後の国司となり佐渡の母に再会する。 これより先、安寿姫も小屋を抜け出し京に上る途中、中山から下東に出る坂道で疲労と空腹に堪えきれず死亡した。 この坂道を後に「かつえ坂」と呼ぶようになった。 安寿姫の亡きがらは、村人の手により建部山の麓この地「宮の谷」に葬られた以後今日まで安寿塚には「かつえの神」として参詣者が絶えない。毎年7月14日は夜祭りが行われ池畔にたくさんの提灯をともし安寿姫の霊を慰めている。 由良は主に山椒太夫伝説、和江の国分寺は厨子王伝説であり、ここでは取り上げない。  重労働を強いられる製塩伝説によれば、姉は「汐汲み」、弟は「柴刈り」に日々を送っていた。いずれも塩を焼くための作業である。海水の塩分濃度は3.5%ほどで、残り96.5%は水でできている。ドラム缶(200ℓ・200㎏)一杯の海水から7㎏の塩が得られる。高さ0.9メートルのドラム缶の海水を煮詰めると底に1.5㎝ほどの塩が出来る。  わずかな塩を得るためには膨大な海水と、その水を蒸発させる熱源の大量のマキが必要であり、膨大な労働量を必要とする。これらの作業は重労働で、付近の山々はみな禿げ山となったという。 『高浜町誌』 塩生産は季節的な問題もあって多くの労苦が伴う。若狭考古学研究会の土器製塩の実験では、二〇人で三日間をついやしわずか三〇〇グラムの塩しか得ることができなかった。当初、海水を濃縮する工程にホンダワラを使ったと推定して作業をおこなったが、藻の脱色で赤茶けた塩水しかとれず、出来上った塩も黒い塩であった。藻を使ったのは『万葉集』神亀三年丙寅九月十五日、播磨国印南郡に幸し時笠朝臣金村つくれる歌として
……朝なぎに玉藻刈りつつ夕なぎに 藻塩焼きつつ海おとめ…… があり、その反歌に 玉藻刈るあまをとめども見にゆかん 船楫もかも波たくとも とうたわれているところから想定したものである。何らかの形で玉藻(ホンダワラ)を使ったことも考えられるが、実験の結果は必ずしもそれを裏付けされるものではなかった。 『小浜市史』 食見の里謡
…三方町 「片食食わえども 片袖着でも 嫌ぞや 食見の塩垂れは」、「嫁にやるまい 海辺の村へ 夏は塩垂れ 冬は苧の根を叩く」 この里謡は食見のみならず、若狭各地の塩作りの苦しみを歌っており、古代における土器製塩にも、この里謡は通ずるものがある。 古代の塩作りにも男性と女性それに子供の作業分担というものが充分に考えられ、海水を汲む作業は、女性と子供の作業であった。 塩汲み女 昭和四十四年(一九六九)に、 その結果明らかに人為的に埋葬されたもので、その方法は身体の左側を下にして、足をおりまげた屈葬を示していた。腹部には六文銭が重なって残存し、これだけが唯一の副葬品であった。角釘が検出され、木棺が使われたことも判明した。 六枚の銅銭は、元豊通宝三枚、至和元宝二枚、皇宋通宝一枚であり、いずれも北宋銭である。従って埋葬の推定年代は、鎌倉時代を考えている。 人骨については、京都大学名誉教授池田次郎の鑑定を受けた。推定年齢三四・五歳前後、身長一四五センチの女性であるとの結果が出された。池田次郎博士の人骨についての所見で興味深いのは、人骨の腕の前後骨などに筋肉付着物が認められ、かなり肉体労働に従事していたことが伺える。調査に従事した者からは、博士の人骨の所見を聞いて反射的に「塩汲み女」だという声がおこったものである。 万葉の塩作りの時にも体験したことでもあり、前述の食見の里謡にもある塩汲み作業の過酷さは、言葉ではいい尽せぬ重労働であった。恐らく、女性や子供の分担だったのであろう、山椒大夫の話を思い出す。阿納の中世の女性は、三四・五歳でかなりの重労働に従事していたことが指摘されたが、多分塩作りに加わっていた女性で、真夏の炎天下、天びん棒に桶をかついで、塩汲みに従事していた女性であろう。 『新わかさ探訪』 食見の塩つくり
明治後半まで存在した塩田 良質の塩として高い評価 古代、朝廷に税として塩を納めて以降、若狭の海辺の村では、明治の後半まで塩をつくり続けてきました。干満の差が小さい若狭では、中世以降、海岸近くに塩田を設け、人が桶で海水を汲む揚浜式の製塩が行われました。底と周囲を粘土で固めた塩田に薄く砂を敷き、そこへ海水をまいて乾くのを待ち、塩の結晶が付着した砂をかき集め、それに塩水をかけて濃い海水を取り出し、さらに釜で長時間煮詰めて塩をつくる、という方法です。 それは大変な重労働でした。夜明け前の暗いうちから、桶を天秤棒の前後につり下げて海水を運び、日の出前に塩田へまき終えると、午前中は山へ燃料の薪を取りにいき、午後からは釜炊きをする-こうした製塩作業ができるのは、6月から9月ころまでの晴天の日で、年間わずか80日ほど。子供にも手伝わせ、夏の日照時間が長い時期には、1日に2回繰り返しました。 若狭町食見に伝わる民謡に「嫁にやるまい海辺の村へ、夏は塩垂れ、冬は苧(麻の古名)の根を叩く。どこへ行こうと塩師はいやよ。朝の星から晩の星いただき、昼の真中の日輪さまの焼きつく炎天の下に働く」と、塩つくりの苦労がうたわれています。 食見は、良質の塩を生産したことで知られています。その歴史は古く、古墳時代の製塩土器(海水を煮詰めるための器)が大口川の河口近くから層になって発見されていることから、五、六世紀にまでさかのぼるものとみられます。室町期ころには、無人の村となりますが、戦国末期に三河(今の愛知県東部)の一向一揆で難を逃れた真宗門徒が、食見に移り往んだと伝えられており、以来再び製塩が行われるようになったのではないかと推測されます。 そもそも食見は、海岸部にありながら、漁業を営むことのできない村でした。北西に開いた世久見湾の最も奥にあるため、北風が吹くと、もろに高波が打ち寄せます。そのため港を造ることが困難で、戦後の昭和26年までは入漁権もない状態でした。 こうした事情もあって、食見の人々は、生活の糧を塩つくりに求めました。江戸時代には小浜藩が製塩を保護、奨励し、波浪で塩田が被害を受けたときには蔵米が下げ渡されています。 明治期には10軒が製塩を営み、いずれも所有する塩田は1反前後。規模は小さいものの、食見塩は品質が良く高値で取引されました。純白で細かくサラサラしていて、塩を入れた俵が一、二年たっても乾いていたといいます。それは、釜を毎日磨き上げ、煮上げている間も丹念に泡(不純物)を取り除くといった、食見の人たちの勤勉で丁寧な仕事ぶりによるものでした。 しかし、明治38年(1905)、日露戦争の戦費調達のため、塩の製造販売に専売制度が導人されたことによって、民間による製塩が禁止され、食見をはじめ若狭における製塩の歴史に終止符が打たれました。 丹後由良・神崎の製塩由良からは製塩土器の出土がないので、古代までは遡らないのではなかろうか。神崎には平安期と思われる製塩土器の散布地がある。もともと土器製塩は若狭が中心であり、その流れで丹後にも広まったものか。 『丹後国加佐郡寺社町在旧起』 由良村は往昔より塩焼経営塩浜の体東西二十町に及びて衣替(6月1日~6月15日頃)着半により菊月(十月)に至った
『丹哥府志』 由良村(川向)…
【塩浜】 凡神崎、由良の二村塩を焼て業とする者多し、浜の長サ一里余。 『両丹地方史20』(1974.11.20) 由良塩浜聞書
後になっても、日本海側は干満の差が大きくなく、海水の方から勝手に塩田へ入ってくれるような、入浜式の方法はとれない。海水を桶にくんで、人力で塩田へ運ばなければならない揚浜式しかとれない。安壽の時代ももちろん揚浜式であった。丹後地方史研究友の会・由良の正史をさぐる会 小谷 一郎 由良塩兵は海に面した村の百姓達が浜割をして作り、一軒が一場所ずつをもっているのが普通であった。この浜割りは幅二間半から三間の長方形に渚から畑地に向けて細長く区画され、その境界には杭を打って樽とした。こうした揚浜は規模が小さく一区画が二畝ぐらいのものであった。この狭小な塩浜を営む百姓達は 大島さん(冠島のこと)までウチの浜 などと言って気を晴らしていたのであろう。 この様子は由良浜の切図を見るとよく分る。 「塩仕」の道具として、次のようなものを用いる。 〔かおけ〕=海岸で海水を汲み塩田へ運ぶのに用い、担うための繩の取付けが桶の横木の中央に一本通して付けられているのが特徴である。 〔さら〕=板に竹釘を植えて長い柄をつけた「さらひ」(竹杷)で塩浜の眇を掻いてならし場直しをした。元来、穀類、落葉を掻き集めるのに用いた農具を利用したもの。 〔にないぼう〕=荷桶を担う棒で丸太棒。 〔えぶり〕=元来は水田の土をならし穀類を掻き集めるなどに用いる農具で、柄が長く頭は横板で歯のないのが普通であるが、塩浜では海水を撒いて砂に付着した塩で砂が一枚の板のようになると、これを掻き集めるのに用い、由良では木板に鋸歯状の凹凸を設けたものを用いた。 〔しゃく〕=径一五~二〇センチの木製で竹のタガでしめ、長い柄をつけたもので、海水を塩浜に撒くのに用いる。 〔み〕=穀類を入れてあおり、屑、殼、麈などを分け除く農具である箕を用いて、砂をさらえ運ぶのに使った。 「かおけ」は容量約二斗。一荷で約四斗を運ぶことになり、「しゃく」は余り深いと使いにくくなるが曲物を用いず木で作られるため相当の重量になるわけである。 〔ふね〕=径五尺位のタライ様の浅い平らな片口で、縁には一寸位の高さの縁がとってあり、底には溝を彫って「しのび竹」をこの溝に並べることもある。 〔がわ〕=丁度、底のない盥という形で、一枚が高さ七寸位、径は五尺位で、大体これを三枚重ねに積み上げる。 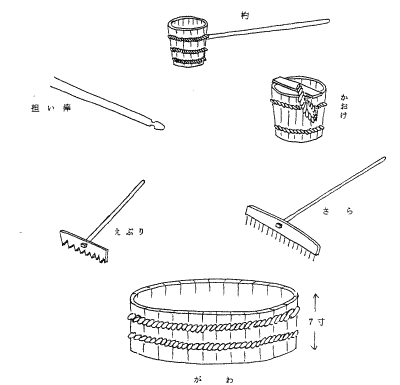 塩浜の設備は次のようにしつらえる。 先ず浜割りが出来ると隣との境界をたしかめ「ふみみち」をつくる。これは自分の塩浜の中に通路として用いる。塩浜の適当な個所に「フネ」を置きその上に「ミザラ」と「ムシロ」を積み、さらにその上に「ガワ」を三枚重ねに積み上げる。「フネ」の口の下に小桶を置く。この小桶には側を通ってきたタレ(アエ)をとる。 釜屋は、塩浜の上に直接柱を立てる藁葺き入母屋の掘立小屋である。釜屋は一枚の塩浜に一基築かれる。竃は釜の大きさに合わせて石を並べ土で固めて築き、径五尺、深さ一尺の鋳物の平釜を据える。 一区画をおおよそ「上のクマ」「中のクマ」「下のクマ」に区分し、この区画に夫々桶を置く。オキバマケと呼ばれ、海水を汲んでおく桶である。このほかに「アイバマケ」(鹹水を入れておく桶)「セイバマケ」(浸縮鹹水-モンダレ-を入れる桶で、釜の近くにおく)などがある。 「塩仕」の仕事は全く家内労働であり、一家の内で夫々の仕事の割りが決まる。 浜へ出ると先ず沙の中にあるゴミなどを拾い上げ、また粗いい砂の所には目の細かい砂を担ぎ、全体をサラでならして塩浜をととのえる。こうして準備ができると砂撒きをする。 塩汲みは男の仕事である。カオケを担って塩浜をハダシで走る。塩汲みは渚を沖に向いて膝がしらのあたりまで水に入り、カオケを前に振って波の返るのを一気に汲み上げる。担い棒で担ったまま汲むのである。一荷の水を担って塩浜を走ることは夏の日の照りつける下で、働きざかりの男にとっても相当な重労働であった。男の子供はまたそれぞれの体力に見合ったカオケの小さいものを作ってもらって手伝うこともあったのである。主婦または嫁の仕事は、海水撒きとサラカキである。海水撒きに使うシャクは重さもあり、海水を細かい霧になって万べんに散るように撒かなければならず、そのためにはシャクを返すように振るというなかなか熟練を要する仕事である。馴れなければ一か所に叩きつけるようなこともあり、仕事を駄目にしてしまうという大事な部分である。そしてこれを何回もくり返し塩浜一面に平均になるように撒く。砂をぬらした海水は天日で乾くと砂はバリバリの一枚の板のようになる。海水中の塩分が天日や風で水分を蒸発させ、塩の結晶が砂に付着するのである。 充分に乾いたところを今度はニブリで掻き集める。これは大体一家総出の仕事となり、集められたこの砂はミなどでさらえてガワの中に積み上げられていく。この仕事には女子供が使われることが多い。 ガワの中につめられた上から海水をかけると砂についた塩の結晶が溶けてガワの中を通って濾過されフネの口から下の小桶(アイバマケ)にたまる。この濃化されたタレ(アエ)をもう一度ガワの砂に注ぎかけてシエ(「精」の意味) (濃縮鹹水・もんだれ)をとる。 シエをとったあとには更に海水をかけてカケミズをとり、これは次のときのカケミズとして置き、ガワは崩され新しくガワを築いてこの作業が繰返されるのである。この一回に要する砂は大体六荷半、これでためられるシエはカオケの「かたし」(カオケー杯分)で、これを繰返しシエェ二荷半から三荷が大体一日の仕事量である。 竈たきは大体年寄りの仕事である。生乾きの葉つきの松材を燃してヒラガマでシエをたきつめると約二斗の塩をたき上げることが出来る訳であるが、ヒラガマの底にまんべんなく火が回るようにしなければならない。このたき方の上手下手で塩の出来上がりの良し悪しも分れると言われる。 由良浜の海水濃度は大体二・五~二・八%であり、シエの塩分は約一五%。これをたきつめるのであるが、そのために要する塩木は相当の量である。由良岳は享保二十年(一七三五)頃すでに「木草無シ草山也」(丹後旧語集)と言われるほどになっており、これが塩木の料に山の本が大量に伐り出されていた事を裏書きしているのかもしれない。特に明治維新以後の塩木は田辺藩による支援保護もなくなっているため、由良岳中腹までひろがっていた入会林だけがその供給源であり、時々の由良川洪水の際の寄り木(流木の流れ寄ったもの)も利用されていたのであろう。この由良浜では寄り木を最初に手をつけた者はそれを集めてそのシルシを立てておくだけで、自分のものとして使用できる風習が今も残されているのはその故ではないだろうか。 毎日の塩木伐りは、その日の最初の海水撒きの仕事が一段落する昼前の二、三時間を利用し、入会林に入って葉もちの松を伐って降りて来る。入会林の木を塩木として使っていたのである。これを浜に積み生乾きのものを燃料とした。そしてこの入会地には当時(明治年間)植林することもなかったという。それにしても由良塩浜の製塩が塩専売制施行後も引続いて明治四十三年九月まで、大規模な入浜をもつ瀬戸内の製塩の圧力に抗しながら続けられたことの裏には、この入会制が支えた部分か大きく、塩木がタダであり、労力も全くの家内労働で、金銭に計算しない時代には塩を売って得ただけのモウケとする考え方がそのままとおっていたところに、この村の貧しさを見ることもできる。 「塩仕」が作業できる期間はそのときの天候にもよるのであろうが、大体四、五月に始めて夏を最盛期に、秋に入れば十月頃までの間を利用して行なわれ、その合い間に僅かばかりの田畑を耕し、或いは山仕事をし、冬も出稼ぎに出ることがなかったという。また塩浜の仕事は夜明け頃から浜に出て始められ、夕方暗くなるまで続けられた。そしてこの仕事は塩汲みをはじめとして荷厄介な重労働であり、中世の製塩地でどこでも申し合わせたように塩汲み女にまつわる伝説や口碑が残されているのもそのあらわれであり、また由良塩浜に働く人々が 由良や神崎は塩せにゃよかろう 女山行かにゃ またよかろう と歌いついだことはその労働の激しさや厳しい条件を訴えるものであり、この人々の気持が惻々として今に胸を打つものがある。 由良塩浜は脇から松下、東崎までひろがり宮本庄五郎(故人)氏のメモによれば、慶応四年(一八六八)には反別にして二町六反五畝二歩、脇が一町二反五畝、松下、東崎で一町四反。なお当時の塩浜で仕事をしていたのは 脇 五九戸 松下 二五戸 東崎 二三戸 合計 一〇七戸 という。一戸当りの塩浜は二畝から三畝。家によっては二枚の塩浜を経営しているところもあったに違いない。また、旧幕時代には塩木として三浜(大浦)の山林を伐採することを藩から許されていたという話も伝えられるが、まだそれを裏付ける資料は発見できていない。 このようにして続けられた由良塩浜経営も明治三十八年(一九〇五)六月専売制度実施とともにその家族の人数に応じた取り分を残しその余は全部専売局の検査を受けて買上げられるようになり、その利益も薄く製塩を離れていく人も漸く出はじめ、これに決定的な打撃を与えたのは明治四十年(一九つ七)八月の水害であった。このとき豪雨のうえ更に由良川が氾濫しそのため由良の塩浜は殆ど潰滅し、明冶四十三年(一九一〇)九月には全くその姿を消すこととなる。そしてその翌年五月には国からの交付金八百円を受けて由良の製塩は廃止され、その後、昭和二十年から同二十四年由良浜で行なわれた自給製塩もこの揚浜式製塩を復活することなく、漸く二、三の業者がそれを行なったにすぎなかったのである。 ○ 右は旧由良村字協加藤長吉さん(八二歳)、小林ちよさん(八七歳)の二人からの聞きとりをもとにしてまとめたもので、私達はいまこの仕事を出発点に、由良塩浜の歴史をさぐろうとしているところである。先輩諸賢のご指導をお願いしたい。 『舞鶴の民話5』 穴観音 (神崎)
永崎寺とあるのは永春寺か。また西神崎でなく、東神崎であろう。大浦半島瀬崎の山の木が「塩木」として大量に伐り出され、神崎の塩焼きに使われていた。江戸時代の神崎が、田辺藩の塩浜であったことがわかる。永崎寺から東へ穴観音にいたる畑の中で、多くの製塩土器片が採集されている。慶長検地郷知帳に「高一二九・八五石神崎村」とあり、運上のなかに塩浜運上銀一貫三五九匁六分、入木の代わりとして塩七五俵五升六合とし、古来製塩業、海運業に従事する者が多く、とくに西神崎は製塩業がさかんであった。 『丹後国加佐郡寺社町在旧起』 神崎村は
由良に同しは塩浜なり小船余多これあり、塩を商う、… 将又名物は由良神崎の塩 『舞鶴市史(各説編)』 製塩を行っていたのは京都府下では由良と神崎の両村のみであった。両村の製塩の歴史は古く、山椒太夫の伝説にも塩浜が出てくる。江戸時代は由良川水運の一番重要な上り荷(丹波荷)であり、瀬戸内の「西塩」に対する「地塩」として丹波の各地にまで移出されている。明治九年の「京都府治一覧」によると、当時由良浜に九〇〇、神崎浜に一、三〇〇の塩釜の存在が記されている。しかし同十九年には両浜の釜数は三二五と減少し、塩田は十町五反(一〇・五ヘクタール)であった。同二十五年には両浜で四、九五〇石の生産をしているが、同三十八年に塩専売法の制定により、価格が下がり生産額も減少し、同四十三年の一〇六石を最後に同年九月製塩を中止した。
『丹後半島の旅』 『日本的思考の原型』(高取正男著)によると、由良や栗田の塩をざるに入れ、天秤棒で前後に荷なって振り売りをする塩売りの姿は、近年まで舞鶴などでよく見られたという。また、内陸部の綾部付近の山村では、昔から栗田、由良の塩は安く、上質であるといって、味噌や漬物を仕込む時期になると、人々はこの行商人めあての塩買いに舞鶴の町まで通ったという話である。
参考・山椒太夫 柳田国男の辞書解説原稿より 山荘太夫(さんしやうだいふ)
〔名義〕 山莊太夫の名稱はこの話に出る丹後由良の長者の名前から来てゐるが、古くは單に由良の長者とだけで、山莊太夫とは云はなかったものであらう。「さんしやう」の字面も、三莊・山桝・三枡・山椒などと宛ててゐる。古く土佐國には、山庄太夫と稱する一階級の人民が住んでゐたといふ事を初めとして、各地に算所・山莊・産所・山所などと稱する者があり、皆山臥・陰陽師の類であったが(山莊太夫考、郷土研き三ノ一)、これ等は卜占・祈祷の表藝の外、或は祝言を唱へ歌舞を奏して合力を受け。更にその一部は遊藝賣笑の賤業にも從った。即ち山莊太夫の名目は、最初この由良の長者の話を語って歩いたのが、この「さんしよ」の太夫であったので。いつの世にか、これを曲の主人公の名と誤解されるやうになったものかとも考へられる。 〔解説〕 寛永版の説經浮瑠璃「さんせう太夫」によれば、大體話の筋は次のやうである。 奥州五十四郡の太守岩城の判官正氏、帝の御勘気を蒙り筑紫へ流され、その子安壽姫・對王(つしわう)丸は母と共に父を慕って行き、途中越後國直江の浦で、山岡太夫といふ悪者に欺かれて、人買の船に賣渡され、母は佐渡で足の筋を切られて、粟の鳥を追ふ奴婢とされ、安壽姫・對王丸は丹後の由良港の強慾無残な三莊太夫といふ長者の僕婢となって酷使された。安壽姫は弟を思ひ家を思って我が身を殺して弟を遁す。對王は虎口を遁れて都に上り、清水寺に參籠して観世音に所願し、貴人に見出され、その養子となり、その計ひで父の罪も宥され、又佐渡の母をも救ひ、三莊太夫等を罰した。 この話の古い形が果して如何なるものであったかは、今日なほ詳かでないが、この話の原の形は、やはり單なる長者傳説(長者屋敷参照)であったらう。これを長者傳説として見れば、長者の名が山荘太夫といふ外に、これといふ特異の點もない。諸國の長者の話には朝日と夕日との二面がある。多くは原因を信心と善根の有無に歸してゐるが、一方には極度の幸運によって一朝にして巨富を得た者と、他の一方には然るべき因縁があって、さしもの大分限が夢の如く退轉して了ったと云ふ話とが語られる。山荘太夫は即ち右の長者没落の一の例であって、これに伴ふに對王丸の不思議の立身談を以てし、大體の形式はよく整ってゐる。長者が没落して行く因縁話には様々なものがあるが、山荘太夫の如く、慈悲に乏しく下人を酷使した爲めに滅びた例も段々ある。現に奥州膽澤の掃部長者などもその一つである(郷土研究二巻)。慈悲と謙遜とは観音・薬師などの最も重んじ給ふ所である。加ふるに信仰と祈念とを以てした對王丸は高い官祿を得たので、これも「今昔物語」以来、貧民が出世した普通の道筋である。次に岩城判官の三人の遺族が人買に買はれたといふ話も、少し複雑ではあるが説明が出来る。食慾なる長者が富を得る手段として悪い事をした話は、纐纈城(かうけつじやう)の筋を引いた播州姫路の平野長者の類が少くない。但しこの場合に、被害者が安壽姫・對王丸であることは、何か吾々に分らぬ別の仔細があることと思ふ。岩城判官の居館は、寛永の浄瑠璃には奥州信夫郡とあって今の福島縣らしいが、北奥の青森縣では彼は津軽から出た人と傳へ、今でも丹後の國の船が寄港すると、岩木山の神の憤りで天氣が荒れるといふことが多くの書に見えてゐる。又近い頃の弘前の人の話に昔この邊に同胞二人の娘があって姉の方を安壽姫と言ひ、山荘太夫のために苦しめられて遁れ出で、一人は東へ行って小黒山に登り、一人は西に走って岩木山に入り山の主になったといふ(共古日録巻十六)。山荘太夫があれ程有名である以上、後人の訛傳とは認め難き話の相違である。兎に角この兄弟の話の奥には、例の花萩中納言の子少將の話などと同じく(柱松考、郷土研究三ノー)、流人の子が親を慕ひ、その臨終に逢ひ得ずして後に供養をしたといふ一段が含まれてゐたことはほぼ確かである。而も岩城判官正氏が如何にも芝居の殿様然たる名である上に、奥州の大名が九州へ流されるなどは有り得べき話でないから、これは王孫沈淪の悲劇を濃厚ならしめるまでの脚色かも知れない。一體山荘太夫の話の中で最も身に沁むのは、肓目の母親が鳥を追ふ一段である。「あんじゆ戀しやほゝらほい、つし王こひしやほゝらほい」、この唄は人々の涙を誘はずには措かなかったらう。前半は石童丸に、後半は梅若丸に、よく似通った幾多の脚色は、或はこの鳥追の歌を中心として敷衍せられたのではなからうか。若しさうだとすれば、舞臺は違ふが謠曲の「鳥追舟」などは、既に又その一先型であった。こゝに注意すべきは、山荘太夫に限らず多くの長者没落譚には、農作に關する話題を伴ってゐることである。殊に鳥追は田植に次いで、農村生活に於て重要な地位を占めてゐた行事であるから、かく長者の話に結びっいてゐることは寧ろ自然であるといっていい。そしてこの話などもこの唄によって人の心に植ゑつけられ、信ぜられて傳説となったものであらう。なほもう一つは、早乙女の死んだといふ話が長者傳説には伴ひ易いと考へられる點があるので(山莊太夫考)、若い安壽姫の非業の死、竝にその母の肓目にして鳥を追ふといふ哀れな話も單に由良長者の口碑として不調和な取合せでないのみならず、寧ろ山荘太夫の由来を明かにする良い手掛りであると思ふ。勿論浄瑠璃の山荘太夫となるまでには多くの脚色を經てゐるにしても、これ等鳥追の歌や、早乙女の話の如きは、後代の技巧が到底偶然には添附し難き部分であるのを感ずる。尤も實を言へば、これ等鳥追の歌や早乙女の話は、長者の滅亡退轉とは寧ろ調和の出来ぬ事柄であるから、多分はこの長者傳説が、その最初の形、即ちその榮華繁昌を傳へられてゐた時代から、長者に附いて廻ってゐた口碑の一つであったらうと思ふ。 安壽姫伝説の時代と広がり森鴎外の小説とか、丹後の伝説とかいった範囲でなく、ずっと古くからずっと広く安壽姫は語られている。もともとが口承芸能なので、古い物はわからないのだが、文章になっている物は、いたこ祭文「お岩木様一代記」、説教節「さんせう太夫」が知られる。今に伝わる物はいずれも江戸期のものだが、もっと古くから語られていたものと見られる。 岩木山(津軽富士)と弘前城↓  安壽姫は後に岩木山の神となった。丹後の船が 岩木山はお岩木さまと呼ばれる、岩木山には岩城判官の娘・安壽姫が祀られているともいわれてきた。津軽地方の伝承によれば、岩城判官将氏は丹後出身の家人・大江時廉に謀られて滅びた。安壽姫と厨子王は、丹後由良の長者・山椒太夫に売られ、労役に酷使される日々を送った。ある日、安寿姫は厨子王を逃がしてやるが、自分はその罪で長者にいびり殺されてしまった。安寿姫の霊魂は岩木山へ飛び戻り、弟を見守って岩城氏を再興させたと伝えられる。 この伝承により、津軽人は丹後の国人や、丹後の船を、極端に忌み嫌ったという。津軽藩(弘前藩)では長雨、荒天に見舞われると、領内300キロ余にわたる沿岸の津々浦々に、藩の探索方を出張らせ、碇泊中の船にまで立ち入りして、丹後の人間がいないかどうか、厳しく詮議を行ない、見付けると早速に追放処分にしたほか、牢につないで置いて、橋普請や城普請の人柱にまで立てたと伝えられる。 津軽藩が発した安政5年(1858)5月24日の布令書は「日ごろ天気正しからざるに付いて、御領分へ丹後者入り込み候やも計り難きに付き、右の躰の者見当り候者、早速送り返し候様。なおまた勧進なども吟味仕り候様仰せ付けられ候間、御家中並びに在町、寺社とも洩らさず候様、この段、申し触れられ候。以上。 御目付」としたためていた。 丹後人には身の毛もよだつばかりの憎悪である、「身に覚えがない。そんな事言われても、知らんデ、確かに安壽姫を苦しめ、あるいはそうして殺してしまったというハナシなら聞いている、しかしそれは伝説のハナシだろ、それもずうっと昔の…」と、笑ってすませそうにもないコワイ空気のようである。 津軽藩はたびたび飢饉に襲われた、そのたびに死者の山を築き、犬・猫・牛・馬・家畜類を食い尽し、遂には親を殺し、子を喰うと云う、と伝わる、それだけではない一つの失政にはさらに多くの失政があるもので、1件の死亡事故の裏には29件の重大事故があり、さらに300件のヒヤリハットがあるのハインリッヒの法則のようなことで、そうした大小多くの内政失政を、外の丹後人のせいにして押しつけたという面が否定できないともいうが、しかしそうは言っても津軽藩の勝手な都合だけでは、いきなりにこうも厳しくはできまい、津軽藩は江戸期の話だが、それ以前から伝説の裏に実際にいろいろ彼の地の人々を苦しめる何か伝説や史実があったのかも、と考えたくなってくる。 考えられるとすれば、ずっと古く「蝦夷征伐」と拉致であろうか。日本海側は古くから海路が開かれていたので、丹後や若狭から征伐船が出たことであろうし、製塩や製鉄の労働力として彼の地の人々を、安壽や厨子王のようにラチってきたかも知れない。丹後人がそうしたというわけではなく、大和王権がそうしたのであって、その手先として、あるいは一番乗りだとか調子に乗ってバンザイバンザイで、あるいはムチャなことをするなよ、とイヤイヤ従っていただけであろうか。どちらにしても怨みをかったのかも知れない、文献記録にはないので想像するより手はない。 佐渡や越後直江津のあたりにも、当伝説が伝わるという。
|
資料編の索引
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Free Copyright © 2022 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







 音の玉手箱
音の玉手箱